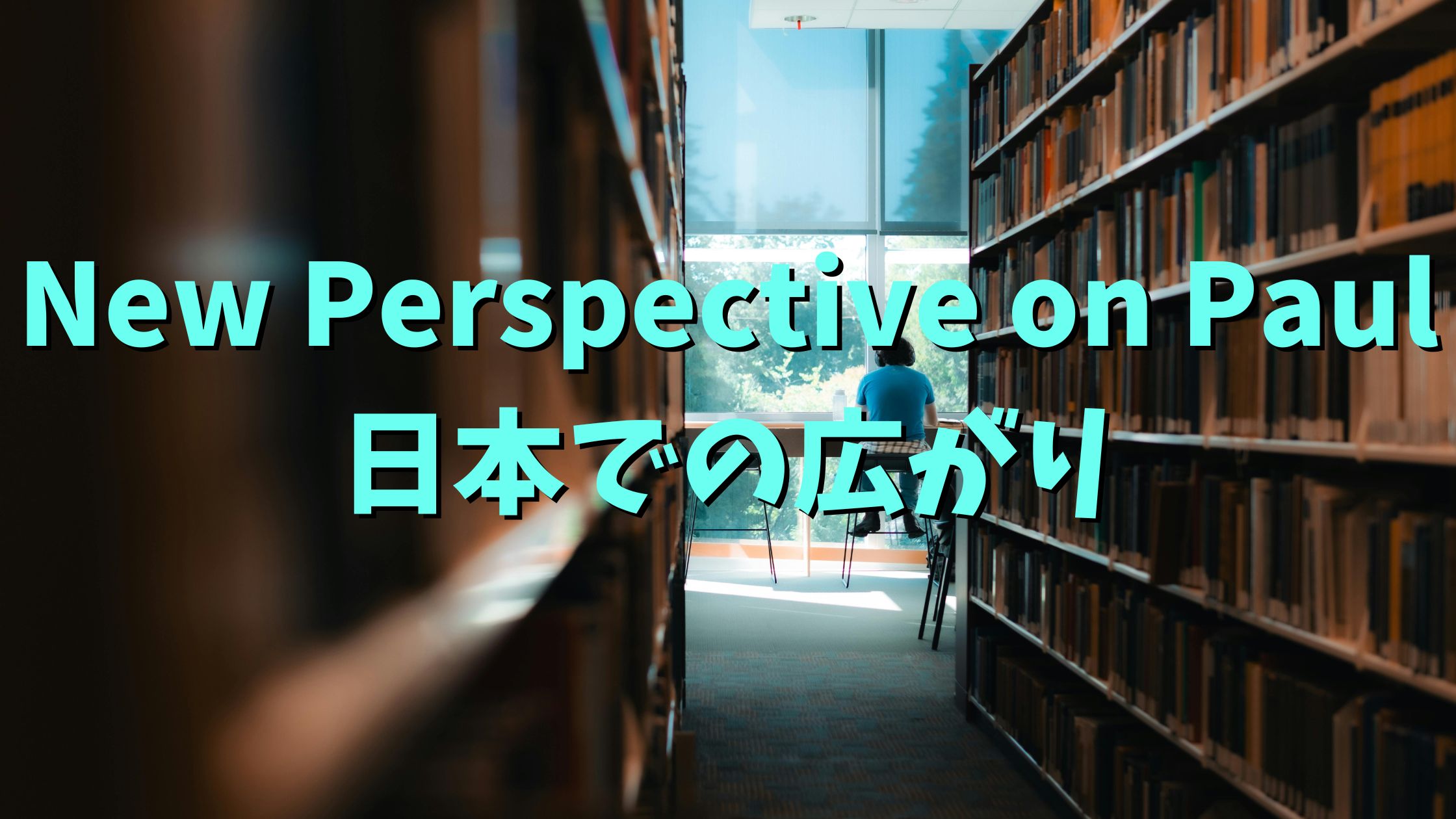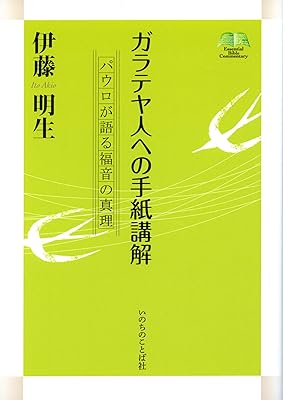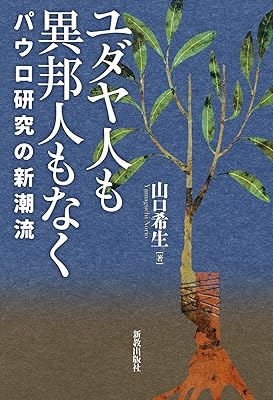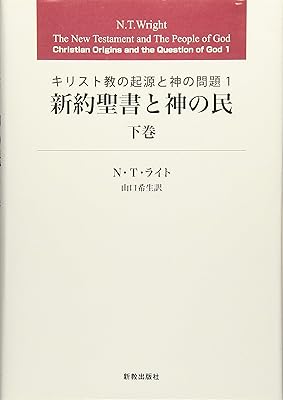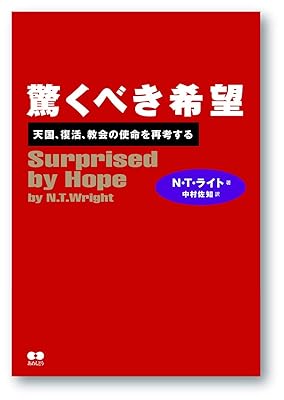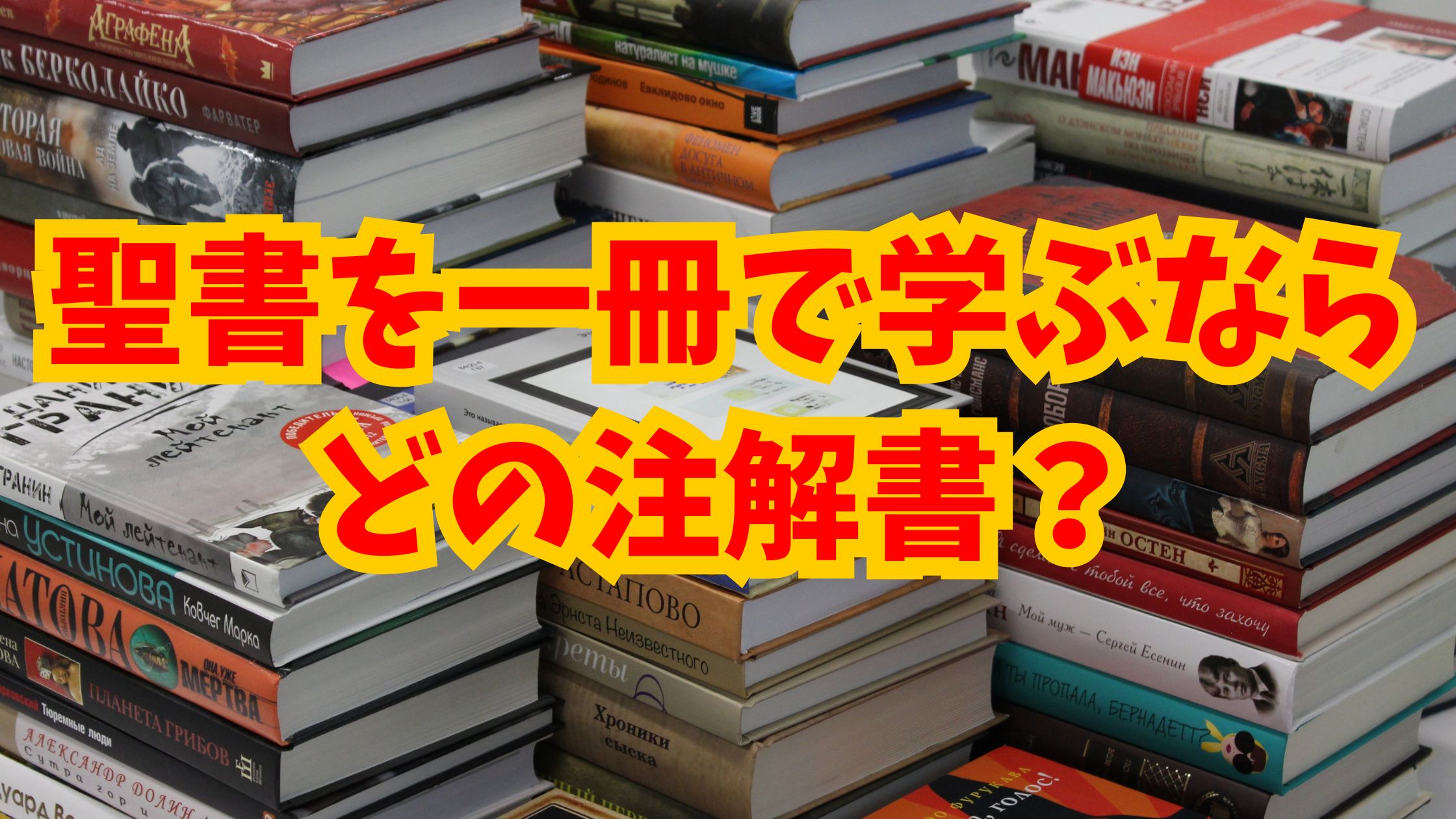10年ほど前から、「パウロ神学の新しい視点(New Perspective on Paul)」(以下:NPP)に関する邦訳本が出版されるなど、日本の教会でも広く馴染みのある言葉となってきました。もちろん、研究自体は、欧米を中心に、半世紀以上も前からされてきたわけですので、単に日本の教会レベルまでは浸透していなかったというだけではあります。ですので、研究者の中には、欧米で学んだ方々をはじめ、すでにNPPに触れている方も大勢おられたと思われます。
実は、NPPが本格的に日本で広まる前に、すでにNPPを提唱する学者について言及されている本もありました。
例えば、2010年に出版された『ガラテヤ人への手紙講解〜パウロが語る福音の真理〜』(いのちのことば社)の「あとがき」にて、伊藤氏はこのように述べています。
振り返ると、三十年以上も前、浪人時代に練馬バプテスト教会に初めて導かれた際に、当時の泉田昭牧師がガラテヤ諸教会宛ての手紙を主日礼拝で連続講解説教していました。また、神学校時代に宮村武夫先生が担当されたガラテヤ書の授業をなつかしく思い出します。さらには、留学時代にトム・ライト博士(セント・アンドリュース大学教授)がオックスフォード大学で担当したガラテヤ書講義から多くを学ぶことができました。
伊藤明生『ガラテヤ人への手紙講解〜パウロが語る福音の真理〜』(いのちのことば社、2010年)、365頁
この「トム・ライト博士」は、今でこそNPPの提唱者の一人として広く認知されている人物です(N.T.Wright)。彼の書籍でおそらく最初に邦訳されたのは、2008年出版の『ティンデル聖書注解 コロサイ人への手紙、ピレモンへの手紙』(いのちのことば社)だと思われます。しかし、この時はそこまで日本の教会にライトが知られることはなかったように思われます。
本格的にライトの書籍が邦訳され始めたのは、2015年出版の『クリスチャンであるとは〜N.T.ライトによるキリスト教入門』(あめんどう)です。これを皮切りに、多数の出版社からライトの書籍が邦訳出版されるようになりました。

しかし、実は日本でライトに注目が集まるきっかけになったのは、2013年に邦訳出版されたスコット・マクナイトの『福音の再発見』(キリスト新聞社)だと思われます。マクナイトの主張はまさにNPPに通じるものであり、本書もライトによって推薦されています。ライトの推薦の言葉から、一部を引用します。
スコットが提案する革命は広範囲に及ぶものだ。あまりに広範囲に及ぶため、彼の同僚にしても、そして私自身にしても、その提案の細部すべてにわたってただちに同意できるかどうかは分からない。私たちは皆、物事を少しずつ違う表現で説明したり、異なる点を強調したり、別の角度からスポットライトを当てたりするものだろう。それは当然のことである。細かい差異はともかくとして、ここで提示されている大きなテーマは、ほかの人たちも語ってきたことと共通する。すなわち、長い間「福音派(evangelical)」と呼ばれてきた運動は、実は「救い派(soterian)」と呼ぶほうがふさわしいものであったということだ。つまり、これまでずっと「福音」について語ってきたつもりだったが、実際は「救い」にのみ集中していたのである。(推薦のことば N.T.ライト より引用)
スコット・マクナイト、中村佐知訳『福音の再発見』(キリスト新聞社、2013年)、12-13頁
こうして、少なくともライトたちの提唱するNPPについての関心が、日本のキリスト教界でも高まったのではないでしょうか。あるいは、学者たちの間で、これは広く知らせないとという熱量があったのか、詳しい経緯はわかりませんが、その後、ライトの書籍が毎年のように邦訳出版されるようになっていきます。、その際、興味深いのは、様々な出版社から出版されている点です。教文館、新教出版社、いのちのことば社、あめんどう、といった、必ずしも神学的バックボーンが同じとは言えない出版社から、同一の人物の書籍が出版されていることは、あまり例を見ないことであるように思います。それだけ、NPP(または、N.T.ライト)には、教団・教派を超えた影響力があると言えるのかもしれません。個人的に思うことは、昨今の特に新約学においては、いわゆる保守とリベラルの間の断絶が以前よりは狭まってきているようにも感じます。
こうして、ライトの書籍を中心にして、日本の教会でもNPPが浸透しつつあるわけですが、もちろん、NPPというのはライトの個人的な見解ではありません。あくまでも、ライトはNPPの提唱者の一人です。NPPの発展の歴史については、『ユダヤ人も異邦人もなく〜パウロ研究の新潮流〜』から詳しく学ぶことができます。これからNPPを学ぶなら、この本を読まないわけにはいかないほど重要な本だと言っても過言ではありません。何しろ、本書の著者の山口氏は、N.T.ライトのもとで学ばれているので、説得力が段違いです。また、わかりやすく、同時に信仰的にも励まされ、恵まれます。NPPにそこまで関心のない方でも、ぜひ一読をお勧めします。
また、ライトの出版が相次ぐ中で、NPPを理解する上で重要な本が邦訳出版されたことも大きな出来事だったと言えます。特に重要な神学者が、E.P.サンダースとJ.D.G.ダンです。こちらも、NPPを学ぶなら、どうしても避けては通ることのできない研究ではないかと思います。私が神学生の時には、もちろん邦訳はなかったので、読むのに大変苦労しました。今では、日本語で読めることに感謝です。特にこの二つの大著は、浅野先生によって訳されていることに驚きを禁じ得ません。なんという労力が必要だったことでしょうか。本当にありがとうございます。

ここまでご紹介してきましたように、邦訳本では、N.T.ライトの書籍が多いので、NPPと言えばライトという印象が強いのですが、サンダースやダンなど、NPPには様々な神学者による研究の積み重ねであることは誇張してもし過ぎることはありません。それほどに、NPPの研究の発展、プロセスは重要です。ちなみに、日本の書籍で、NPPについて最初に紹介されたのは、おそらく1986年に出版されたJ.D.G.ダンによる『新約学の新しい視点』(すぐ書房)だと思われます。残念ながら、こちらは古本となっていて入手困難です(「日本の古本屋」ホームページ参照)。私も神学生の頃に学校の図書館で読んだことがあるだけですが、とても薄い冊子のような本でした。
このようにNPPの発展に大きな貢献をした学者の筆頭が、サンダース、ダン、ライトなのですが、残念ながらサンダースとダンはすでに召されています。そういう意味では、これから新しく本が出版されることがないので、二人がライトにどのように応答したのだろうかと考えると、その答えが聞けないのがとても残念です。そのような点からも、ライトの邦訳本が続いているのかもしれません。ライトの著作に触れるとしたら、読み応えのあるのは、「新約聖書と神の民」です。これは、原著ではシリーズものとなっています(Christian Origins and the Question of God series)。
このような学術書は、なかなか日本のキリスト教界の規模では翻訳出版されることはありませんが、ぜひ邦訳が出たらいいなと思うのが、Vol.3です。これは主にキリストの復活について扱っているのですが、説得力があります。復活については『驚くべき希望』がダイジェスト版のような位置付けで、邦訳出版されています。こちらは専門的すぎないので、誰でも読みやすいものとなっています。
ここまで見てきましたように、この10年ほどで、NPPに関する書籍が多数邦訳されてきましたが、この流れはこれからも続くものと思います。もちろん、ただそのまま広がるのではなく、批判的検証を踏まえて、より洗練されたものとなるのではないかと思います。特に、前述の『ユダヤ人も異邦人もなく』において、山口氏は「ポストNPPの旗手たち」として、ダグラス・キャンベル(Douglas A. Campbell)とジョン・バークレー(John Barclay)を挙げています。今後は、彼らの邦訳も出版されることになることは間違いないでしょう。また、ゆくゆくは日本の神学者もその名を連ねる日が近いかもしれませんね。
確かに、NPPに関する邦訳本が多く出版されたからといって、まだまだ日本の教会で浸透しているとは言えない現実もあります。それでも、聖書を学び続けるという姿勢は、すべての信仰者に期待されていることでもあると思います。もちろん、誰もが研究者のように学ぶことはできませんが、そのような研究に触れる機会があると恵まれることもたくさんあるように思います。今もなお世界中で続けられている研究に触れる機会が、日本でもますます増えていくことを期待しています。私自身もそのような研究の恩恵にあずかり、聖書の理解が深められていることを感謝しています。
しかし同時に、ただ最先端の研究を鵜呑みにすればよいかと言えば、そういうわけでもありません。そのような発見に至った経緯、プロセスを知ることも重要だと思います。なぜなら、神学というのは、これまで続けられてきたように、これからも続けられていくものからです。神学の発展してきた経緯を知ることで理解も深まります。研究と聞くと、少し身構えてしまうということもあるかもしれませんが、そのような学びにますますアクセスできるようになり、また、関心が持たれていく中で、日本のキリスト教界はますます成熟していけるのではないかと思っています。