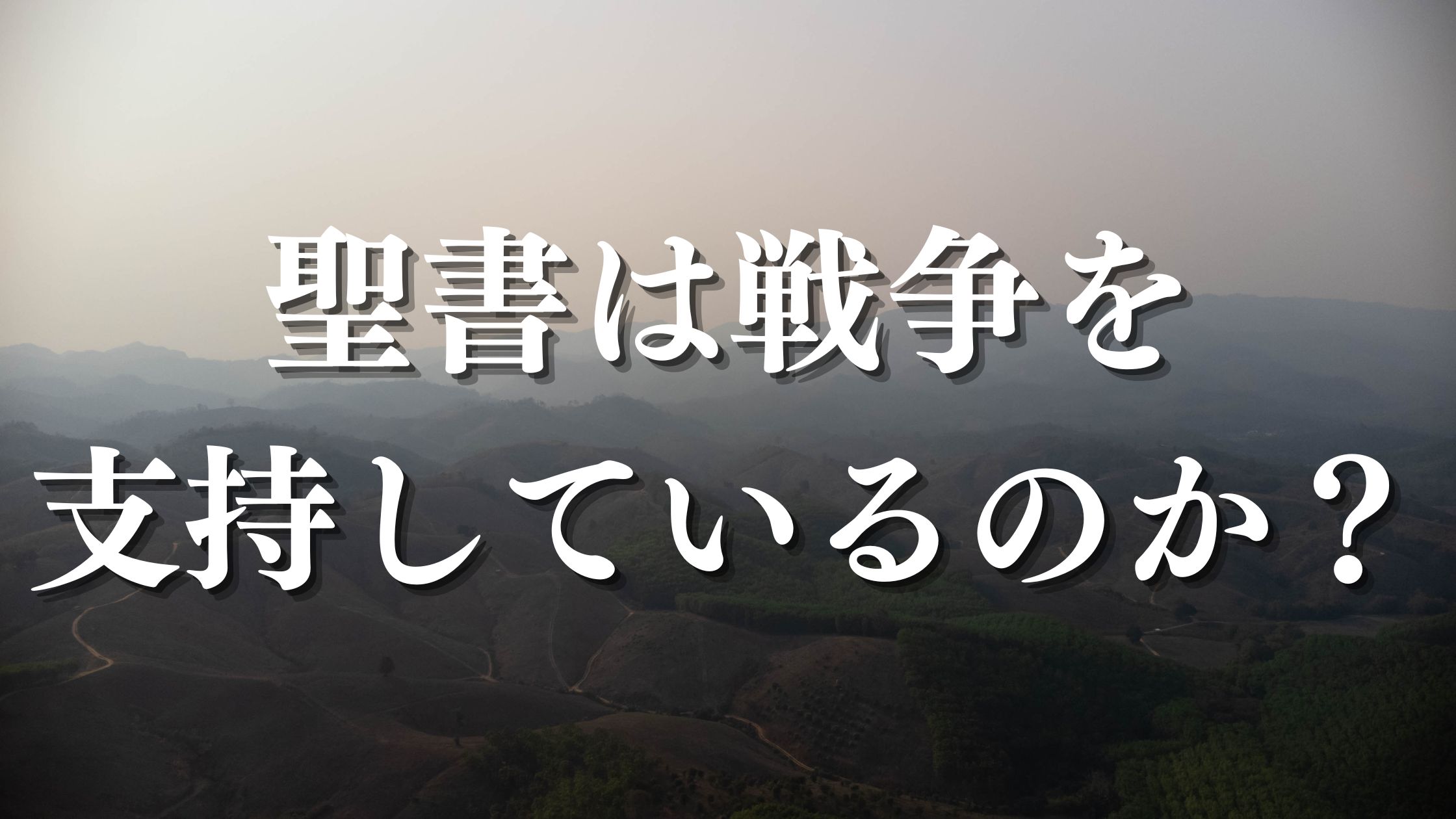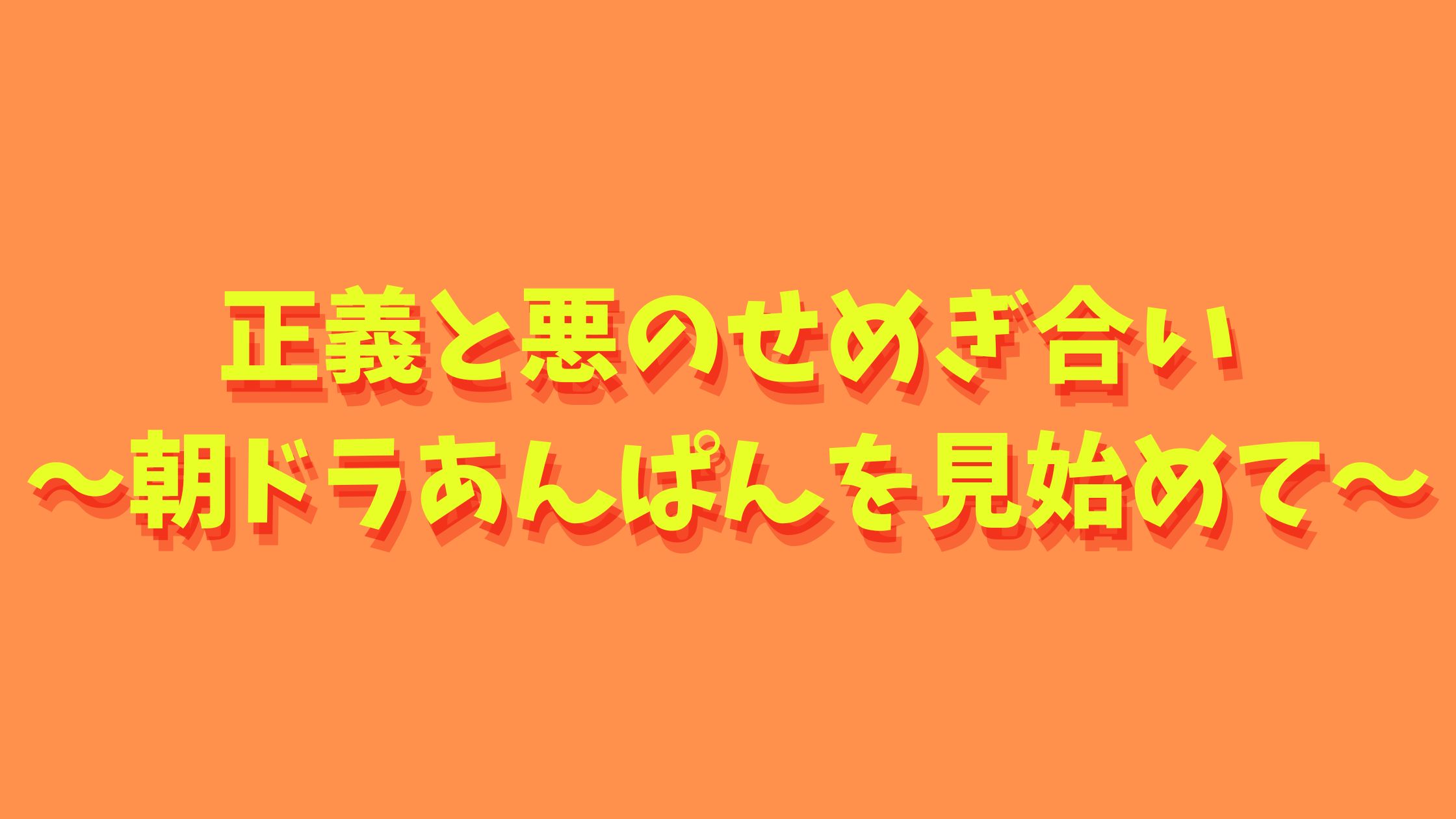最近、牧会の現場で思わされることがあります。
インターネットの普及に伴い、自分で調べ、探究することが一昔前よりはるかに容易になりました。それは、聖書の学びにも当てはまります。調べようと思えば、色々な情報にアクセスできますし、なかには動画による分かりやすい解説もあります。もちろん、そのことは喜ばしいことなのですが、同時に注意しておかなければならないこともあるように思います。
学びをする中で、考えや意見はどんどん先鋭化されていきます。今まで漠然としていた理解が、次第に固まっていくのです。もちろんそれは「理解の深まり」とも言えるわけですが、その一方で方向性が定まれば定まるほど、「論敵」の存在も如実に現れます。
どのような論文であれ、執筆者は論敵との対話を想定し、またそれを通して、結論を導き、提示します。それが学問であり、研究です。論文などでは、「〇〇の意見・主張には反対」というような表現は日常茶飯事です。しかし、そのことを通して、議論がより深まっていくのです。
なぜここで論文の話をしたのかを言いますと、「学ぶ」ということは少なからずそのような学問の領域に足を踏み込むことを意味するからです。つまり、自分で学び始めるということは、そのような世界に片足を突っ込むことになるようなものだということです。たしかに「論文」は極端な例かもしれませんが、独学であれなんであれ、「学ぶ」ということはそこに通じるものです。そして、学ぶうちに自分の見解が定まっていくと、当然のことながら、それとは異なる見解にも直面することになります。学者であれば、そのようなことには慣れていますので、批判的な意見に対しても、どうしたら説得的に答えられるかと、研究の糧にします。しかし、そのような「論争」に耐性がないと、ショックを受けてしまうことがあるわけです。そして、実際そのような状況に直面している方々が多いように思います。
自分で学ぶことはとても大切なことです。ですが同時に、学ぶということは、自分とは異なる意見にも直面することを予期していなければなりません。時には、そのような意見を見聞きして怒ったり、落ち込んだり、これまでの自分の学びが全否定されたような気持ちになることもあるかもしれません。ですが、「学ぶ」ということは、そういうことです。この世界には、自分の意見だけが存在しているわけではないのです。様々な意見との対話や時には論争を通して、理解が深まっていくのです。
しかし、そのことに対する「耐性」があまり備わっていない現状があるように思われます。聖書の解釈の違い一つで、人間関係まで壊れてしまうということもあるかもしれません。これは、あらゆる情報に容易にアクセスできるようになった弊害と言えるのかは分かりませんが、いずれにしても、学ぶための心備えをしておくことは必要だと思います。
特に、初学者にとって注意すべきは、意見の偏りです。「この意見こそ正しい!」と思ってしまうと、それ以外の意見に直面した時に、極端な反応をしてしまうことになります。つまり、相手の否定か自分の否定です。そのような状況に陥りやすくさせている要因は様々あるのかもしれませんが、身近なところで考えれば、例えば、「おすすめの動画」に似たようなものばかりが関連動画として勧められるということも挙げられるかもしれません。似たような主義・主張のものだけに触れていくと、あたかもそれが完全な答えであるかのように錯覚してしまいかねません。
自分の目で見て、自分で探求することは大事な姿勢です。しかし、その道を進むということは、その先には「必ず」異なる意見がある、論敵がいることも念頭においておかなければなりません。もちろん、そこで論文のように相手の主張を論駁することを勧めているわけではありません。ただ、覚えておいていただきたいのは、その時に極端に落ち込んだり、あるいは相手を頭ごなしに否定していては、理解の深まりはないということです。
誰もが独自に学ぶことができる時代にあって、そのようなことを頭の片隅にでも入れておくことが必要ではないかと思わされる昨今です。
過去の記事もご参照ください。