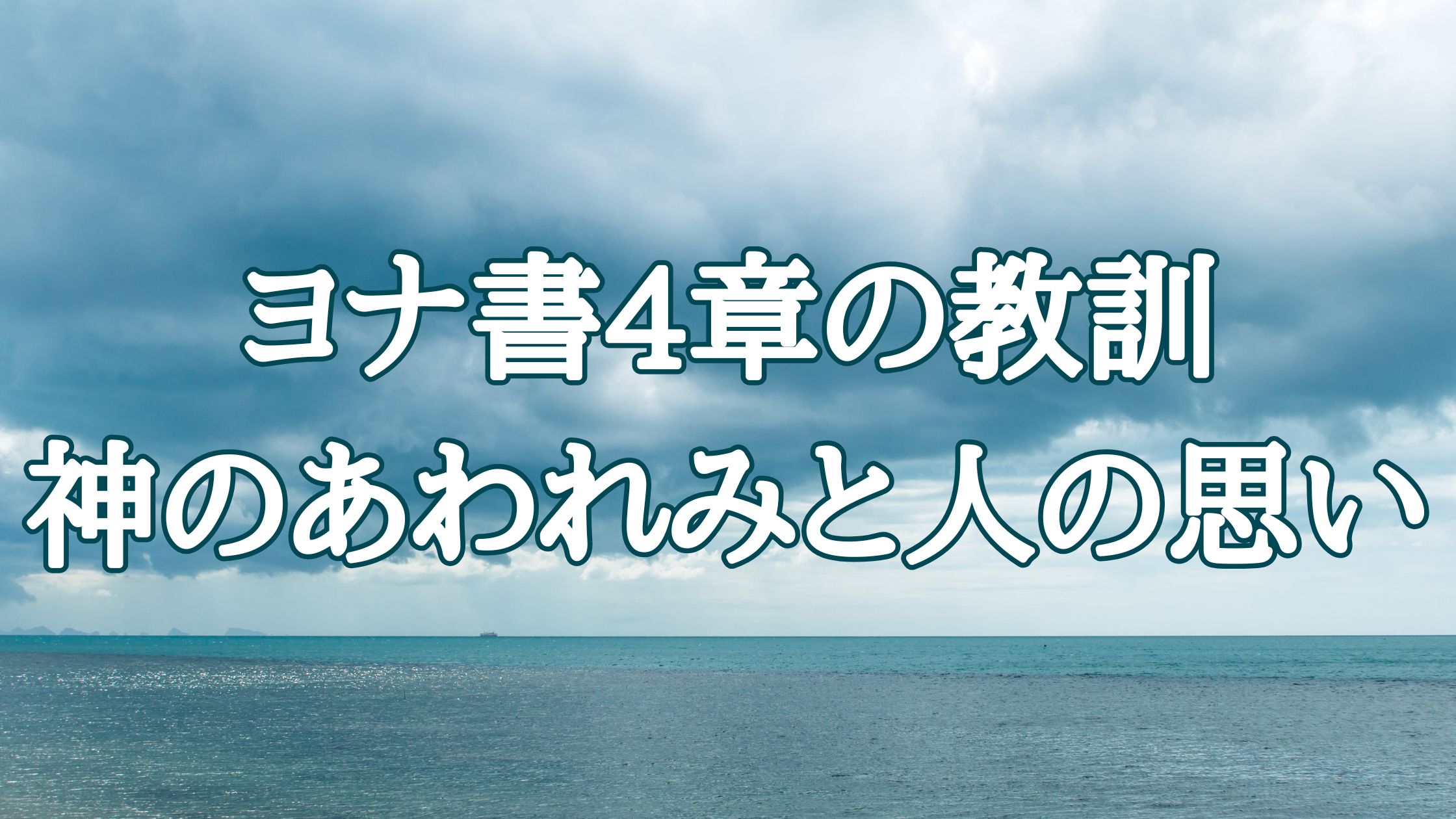魚に飲み込まれることで有名な『ヨナ書』ですが、中でも最も重要なのは4章だと言えるかと思います。むしろ、4章に至るまでの過程はすべて4章を際立たせるためでもあります。
ヨナは預言者としてニネベの町に遣わされます。
主の言葉がアミッタイの子ヨナに臨んで言った、 「立って、あの大きな町ニネベに行き、これに向かって呼ばわれ。彼らの悪がわたしの前に上ってきたからである」。
ヨナ書1:1-2(口語訳聖書)
しかし、ヨナはどうにもそのことが受け入れられませんでした。と言うのも、ヘブル人にとって、アッシリアの都、ニネベは宿敵です。そんなヨナは、神の召しにどう応えたのかと言えば、全く反対のタルシシュへと向かったのです。
ヨナ書は、全体を通して、終始「コントラスト」が見られます。それは、神に不誠実なヨナ(ヘブル人)と誠実な異邦人(異教徒)です。ヨナが乗り込んだタルシシュ行きの船は、嵐に見舞われますが、ここで誠実な信仰を見せたのは、むしろ、異教徒の水夫たちでした。また、ニネベの人たちも、ヨナの呼びかけに素直に応答し、神の前に悔い改めたのです。
その一方で、ヘブル人であるヨナは神に不服を申し立てます。そもそも、ヨナがニネベに行って、神のことばを語ることを拒んだのは、神がニネベの人たちを救うことをヨナは知っていたからです。神のあわれみ深さをヨナは知っていたので、ニネベの人たちが救われては困ると思い、神のことばに聞き従わずに、タルシシュへ向かったのです。
神は彼らのなすところ、その悪い道を離れたのを見られ、彼らの上に下そうと言われた災を思いかえして、これをおやめになった。ところがヨナはこれを非常に不快として、激しく怒り、 主に祈って言った、「主よ、わたしがなお国におりました時、この事を申したではありませんか。それでこそわたしは、急いでタルシシにのがれようとしたのです。なぜなら、わたしはあなたが恵み深い神、あわれみあり、怒ることおそく、いつくしみ豊かで、災を思いかえされることを、知っていたからです。
ヨナ書3:10-4:2(口語訳聖書)
詰まるところ、ヨナは「確信犯」と言っても良いでしょう。神はニネベの人たちをあわれみ、赦されるので、ニネベには行きたくないということは、要するに、ヨナはニネベの人たちに滅んで欲しいと思っているということに他なりません。なので、ヨナは神がニネベの人たちにあわれみを示したことが面白くないのです。
そして、4章では、神はヨナにあることを教えるために、二つのものを備えます。それは「とうごま」と「虫」です。
ヨナ書4章6-7節(口語訳聖書)時に主なる神は、ヨナを暑さの苦痛から救うために、とうごまを備えて、それを育て、ヨナの頭の上に日陰を設けた。ヨナはこのとうごまを非常に喜んだ。 ところが神は翌日の夜明けに虫を備えて、そのとうごまをかませられたので、それは枯れた。
ヨナは日照りの暑さに苦しみましたが、備えられたとうごまによる日陰で苦しみが和らぎます。しかし、それも束の間、備えられた虫のせいで、日陰を作っていたとうごまは枯れてしまいます。ヨナは、そのことで一喜一憂どころか、怒ります。
しかし神はヨナに言われた、「とうごまのためにあなたの怒るのはよくない」。ヨナは言った、「わたしは怒りのあまり狂い死にそうです」。 主は言われた、「あなたは労せず、育てず、一夜に生じて、一夜に滅びたこのとうごまをさえ、惜しんでいる。
ヨナ書4章9-10節(口語訳聖書)
ヨナは、神によって備えられたとうごまであるにも関わらず、それが枯れると、怒ります。ここでヨナはそれが与えられて当然だと思っています。「備えられた」で思い出されるのは、2章の「大きな魚」です。実は、この魚もヨナを助けるために神によって備えられたものでした。
主は大いなる魚を備えて、ヨナをのませられた。ヨナは三日三夜その魚の腹の中にいた。
ヨナ書1書17節(口語訳聖書)
ヨナは全てが神によって備えられたものだったのに、そのことをさも当たり前かのように考えていたのです。実は、これこそ、『ヨナ書』に込められた最大のメッセージだと言えます。ヨナ書の最後は、このような神からの問いかけで終わります。
ましてわたしは十二万あまりの、右左をわきまえない人々と、あまたの家畜とのいるこの大きな町ニネベを、惜しまないでいられようか」。
ヨナ書4章11節(口語訳聖書)
ヨナにとって、神が自分に備えてくださるものは当たり前のものだと思われました。神は自分によくしてくれて当たり前。しかしその一方で、ニネベの人たちに対する神のあわれみは、当たり前だとは考えませんでした。ここに、イスラエル人が陥っていた過ちがあります。つまり、自分たちは神に選ばれた民であり、特別だという「選民思想」が巣食っていたのです。神は自分たちだけをあわれみ、異邦人はそのあわれみを受けるに値しないと考えていたのです。おそらく、ヨナ書が書かれた時代も、そのような背景があったのものと考えられます。だからこそ、ヨナ書の最後が、問いかけてで終わることで、当時の人々に訴えかけているのです。神はイスラエル人だけではなく異邦人にもあわれみを示すお方ではないのか、と。
このことは現代に生きる者、特にクリスチャンにも大事な問いを投げかけているように思われます。つまり、クリスチャンであることが、ある種の「特権」になっていないだろうか、ということです。もちろん、クリスチャンであることは、神と共に歩む幸いな人生という特権が与えられているということです。しかし、その特権は、クリスチャンだけが独占できるものではありません。このような言い方は多少語弊があるかもしれませんが、少なくともその祝福はすべての人に開かれたものです。まだ神を知らないニネベの人たちにも神のあわれみが示されていたように、まだ信仰を持っていない人々に対しても、神はあわれみ深くあられるのです。そのことを忘れてしまうと、いつの間にか、自分たち「だけ」は特別なんだという選民思想を抱いてしまうのです。
ヨナは自分だけが神のあわれみを受けて当たり前だと考えていました。その一方で、ニネベの人たちが神のあわれみを受けることは当たり前ではないと考えました。しかし、神はそのような方ではなく、すべての人にあわれみを示すお方なのではないかということを、ヨナ書は読者に問いかけています。

ぼくどく
ヨナ書と言えば、この本は面白かったですね!おすすめです。