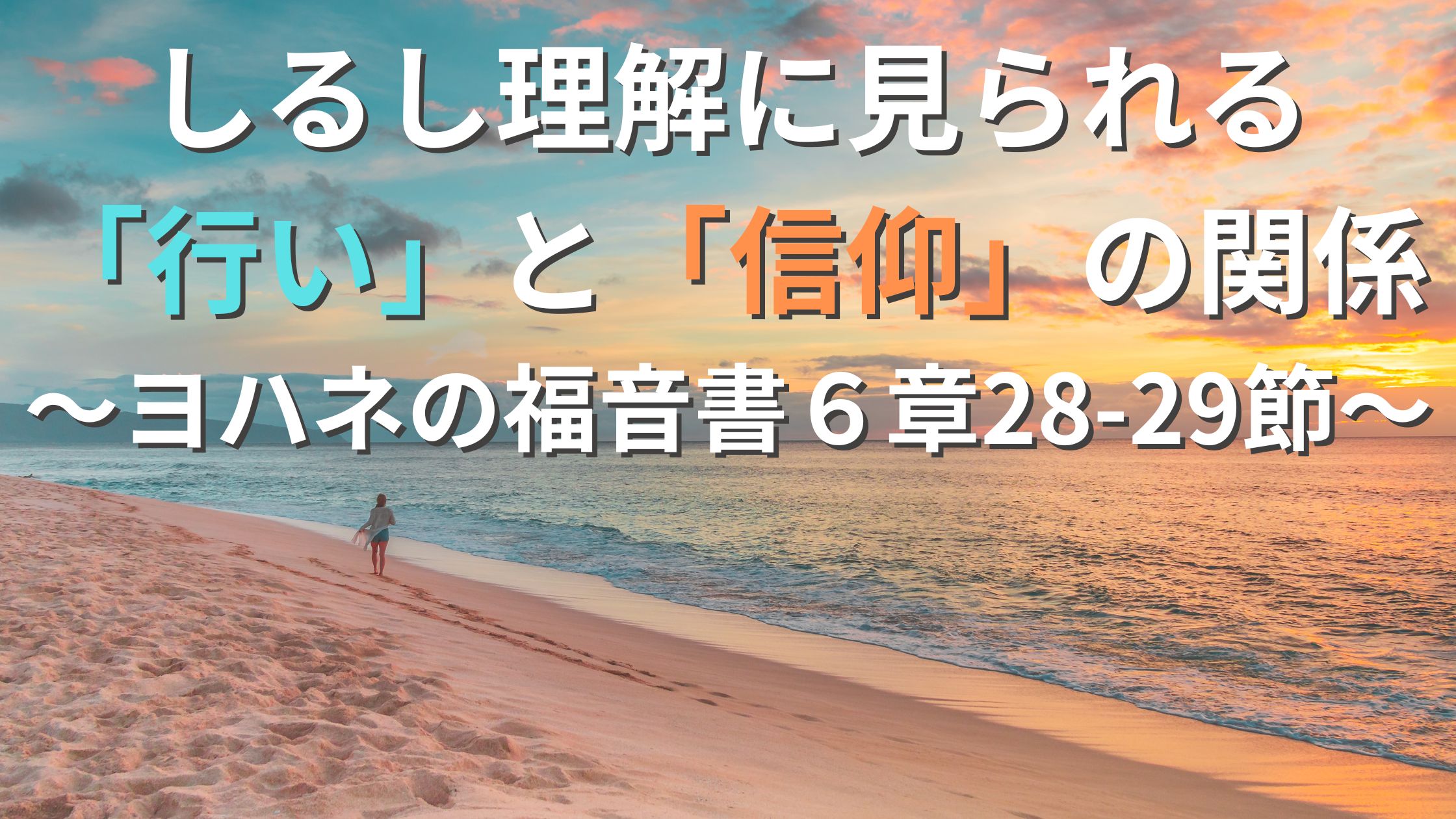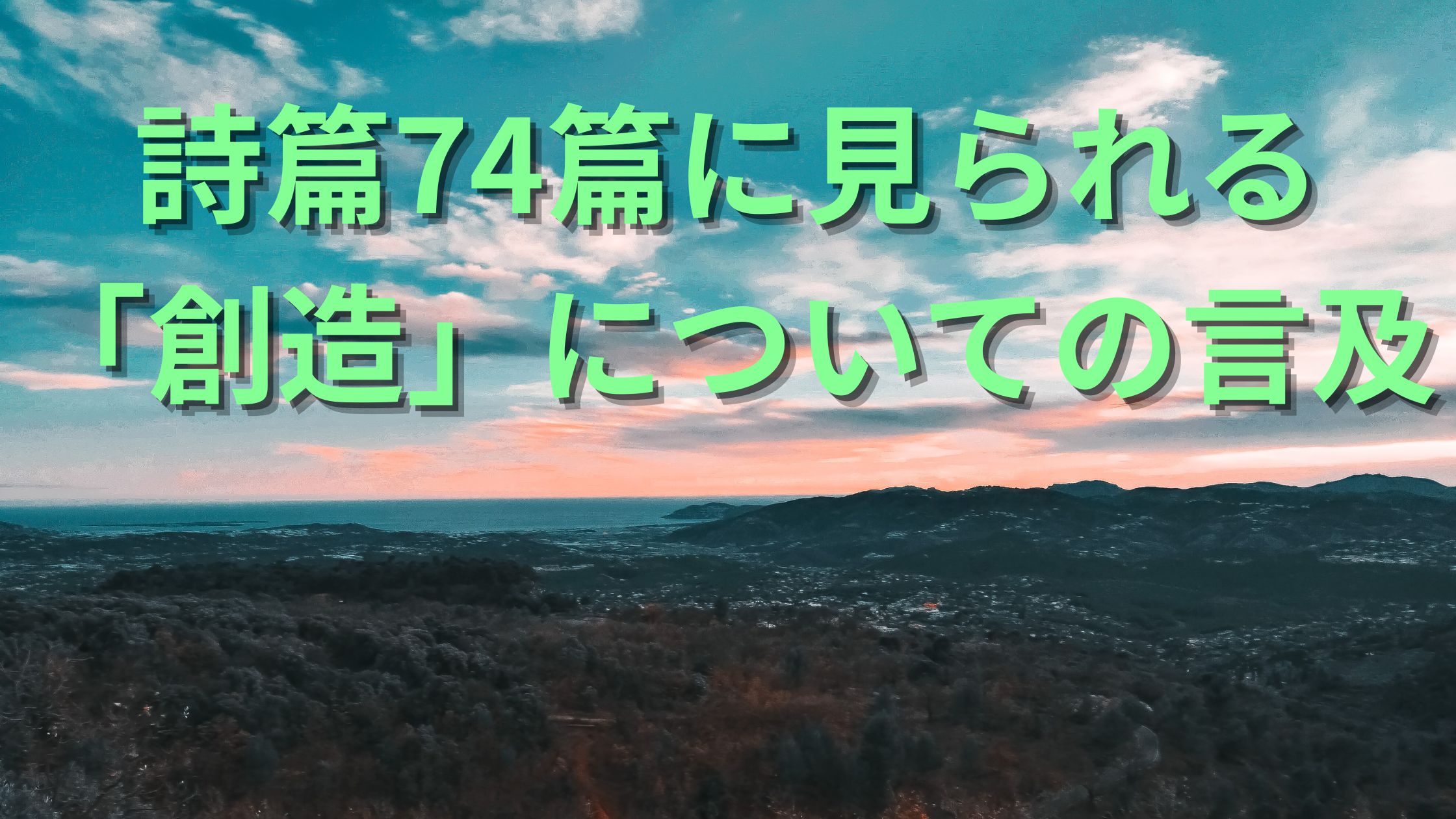これまで「行い」と「信仰」が対立するものとして考えられる傾向にありました。しかし、昨今の潮流は(あくまでも個人的な体感ですが)、そのような誤解も薄れつつあるように感じます。「信仰義認」についての説明も、信仰心さえあれば、何をしてもよいという極端な解釈が語られることも減っているのではないでしょうか。やはり、信仰というのは、生き方に現れるものであって、無関係なものではありません。
今回はこの点について、ヨハネの福音書6章から考察します。
まず、ここでの背景として、イエスとユダヤ人とのやり取りがあります。5章後半から、イエスはご自身が御父から遣わされた神の御子であることを証ししておられます。しかし、人々は一向にそのことを信じません。
そこで、次にイエスがなさったことは、ユダヤ人にとっての最も偉大な人物、モーセにご自身を重ねるということでした。それが、顕著に表されたのが、五つのパンと二匹の魚で、五千人以上の人々を養われた出来事です(「五千人の給食」と言われたりします)。
5イエスは目をあげ、大ぜいの群衆が自分の方に集まって来るのを見て、ピリポに言われた、「どこからパンを買ってきて、この人々に食べさせようか」。
6これはピリポをためそうとして言われたのであって、ご自分ではしようとすることを、よくご承知であった。
7すると、ピリポはイエスに答えた、「二百デナリのパンがあっても、めいめいが少しずついただくにも足りますまい」。
8弟子のひとり、シモン・ペテロの兄弟アンデレがイエスに言った、
9「ここに、大麦のパン五つと、さかな二ひきとを持っている子供がいます。しかし、こんなに大ぜいの人では、それが何になりましょう」。
10イエスは「人々をすわらせなさい」と言われた。その場所には草が多かった。そこにすわった男の数は五千人ほどであった。
11そこで、イエスはパンを取り、感謝してから、すわっている人々に分け与え、また、さかなをも同様にして、彼らの望むだけ分け与えられた。
12人々がじゅうぶんに食べたのち、イエスは弟子たちに言われた、「少しでもむだにならないように、パンくずのあまりを集めなさい」。
13そこで彼らが集めると、五つの大麦のパンを食べて残ったパンくずは、十二のかごにいっぱいになった。
14人々はイエスのなさったこのしるしを見て、「ほんとうに、この人こそ世にきたるべき預言者である」と言った。
15イエスは人々がきて、自分をとらえて王にしようとしていると知って、ただひとり、また山に退かれた。
ヨハネの福音書6章5-15節(口語訳聖書)
この出来事は、モーセが荒野を旅するイスラエルの民に天からマナを降らせることで養った出来事を想起させるものでした。それゆえに、人々はイエスをモーセの再来と捉え、「ほんとうに、この人こそ世にきたるべき預言者である」と言ったのです。しかし、その理解は極めて表面的なものであったと言わざるを得ません。なぜなら、結局ユダヤ人たちは、イエスを自分たちの理解に押し込めて、担ぎ上げようとしていたからです。それはすなわち、軍事的・政治的なリーダーとしての王です。だからこそ、そのような人々から、イエスは距離を取られたのです(15節)。
ここまでが、大まかな流れです。これを踏まえつつ、群衆が再びイエスを探し当てる場面を見ていきます。
25そして、海の向こう岸でイエスに出会ったので言った、「先生、いつ、ここにおいでになったのですか」。
26イエスは答えて言われた、「よくよくあなたがたに言っておく。あなたがたがわたしを尋ねてきているのは、しるしを見たためではなく、パンを食べて満腹したからである。
27朽ちる食物のためではなく、永遠の命に至る朽ちない食物のために働くがよい。これは人の子があなたがたに与えるものである。父なる神は、人の子にそれをゆだねられたのである」。
28そこで、彼らはイエスに言った、「神のわざを行うために、わたしたちは何をしたらよいでしょうか」。
29イエスは彼らに答えて言われた、「神がつかわされた者を信じることが、神のわざである」。
ヨハネの福音書6章25-29節(口語訳聖書)
まず人々がイエスを探した理由について、イエスは「あなたがたがわたしを尋ねてきているのは、しるしを見たためではなく、パンを食べて満腹したからである」ことを指摘しています。つまり、ユダヤ人たちは「五千人の給食」を目の当たりにしながらも、ただでパンを食べられるというレベルでしか理解していなかったということです。しかし、イエスの意図するところはもっと高いレベルにあります。つまり、そのパンを降らせたのは「誰」かということ、さらにはイエスご自身がそのパンであるということです。
食べたらなくなるパンを求める人々に対して、イエスは「永遠の命に至る朽ちない食物のために働くがよい」と言います。ここで「働くがよい」と訳されているギリシア語は「ἐργάζομαι(エルガーゾメー)」という言葉で、「行う(work)」とも訳すことができます。そこでユダヤ人たちは、「神のわざを行うために、わたしたちは何をしたらよいでしょうか」と聞き返します。ここで「行う」と訳されているのは、先ほどと同じ「ἐργάζομαι」です。このように考えますと、イエスがここで言われていることは、永遠の命に至る朽ちない食物のために「行いなさい」となります。
ユダヤ人というのは「行い」を重んじていました。行いというのは、信仰と不可分の関係にあり、どちらかが欠けていても不十分です。そのような人たちに、イエスは欠けているものを示されました。それが、イエスを御父から遣わされた御子であることを信じるという「行い」だったのです。「神がつかわされた者を信じることが、神のわざである。」ちなみに、ここで「わざ」と訳されているギリシア語は「ἔργον(エルゴン)」で、「行い」を意味する名詞です。
さて、ここまで見てきたように、行いを重んじるユダヤ人たちが指摘されたことは、イエスを御子と信じる「行い」でした。その一方で、人々がイエスのなさる「しるし」を見ても、一向にその意味を悟らないという現実があります。実は、そのことが、「行い」と「信仰」のような相互に補完し合う関係に似た「しるし」理解にも通じているように思われます。
信仰はその人の生き方によって表されるように、行いと不可分の関係にあります。同じように、イエスの「しるし」を本当の意味で理解するためには、イエスを御子と認める信仰が不可欠です。それがなければ、群衆のように、単にイエスは偉大な預言者だというレベルでしか理解できないのです。
ここでイエスが対峙しているユダヤ人は、少なくとも「しるし」が証ししていること、すなわち、イエスが御父によって遣わされた御子であることを理解してはいませんでした。また、イエスの指摘によれば、彼らはモーセが天からパンを降らせたと解釈しています。彼らに足りなかったのは、信仰です。イエスを御子と信じる信仰、また、天からパンを降らせたのはモーセではなく、神であるという信仰です。
このことを踏まえるなら、イエスが問題視するユダヤ人の問題が浮かび上がってきます。どれだけしるしを見ても、表面的にしか解釈することができないのは、そこに信仰がなかったからです。ですので、行いに熱心であったユダヤ人たちに、「神がつかわされた者を信じることが、神のわざ(ἔργον:行い)である」とイエスが言われたのには、ある種の皮肉が効いていると言えるかもしれません。そのような意味では、彼らに欠けていたのは、信じるという「行い」だったからです。
しるしを見ても、その指し示すものを理解できないことと、行いが立派でもそれが形骸化してしまうことには、どちらも「信仰」という共通点があります。すなわち、イエスを御子と信じることです。その信仰があって初めて、しるしの意味を理解することができ、行いも意味のあるものとなるのです。そのようなことが、この箇所から言えるのではないでしょうか。