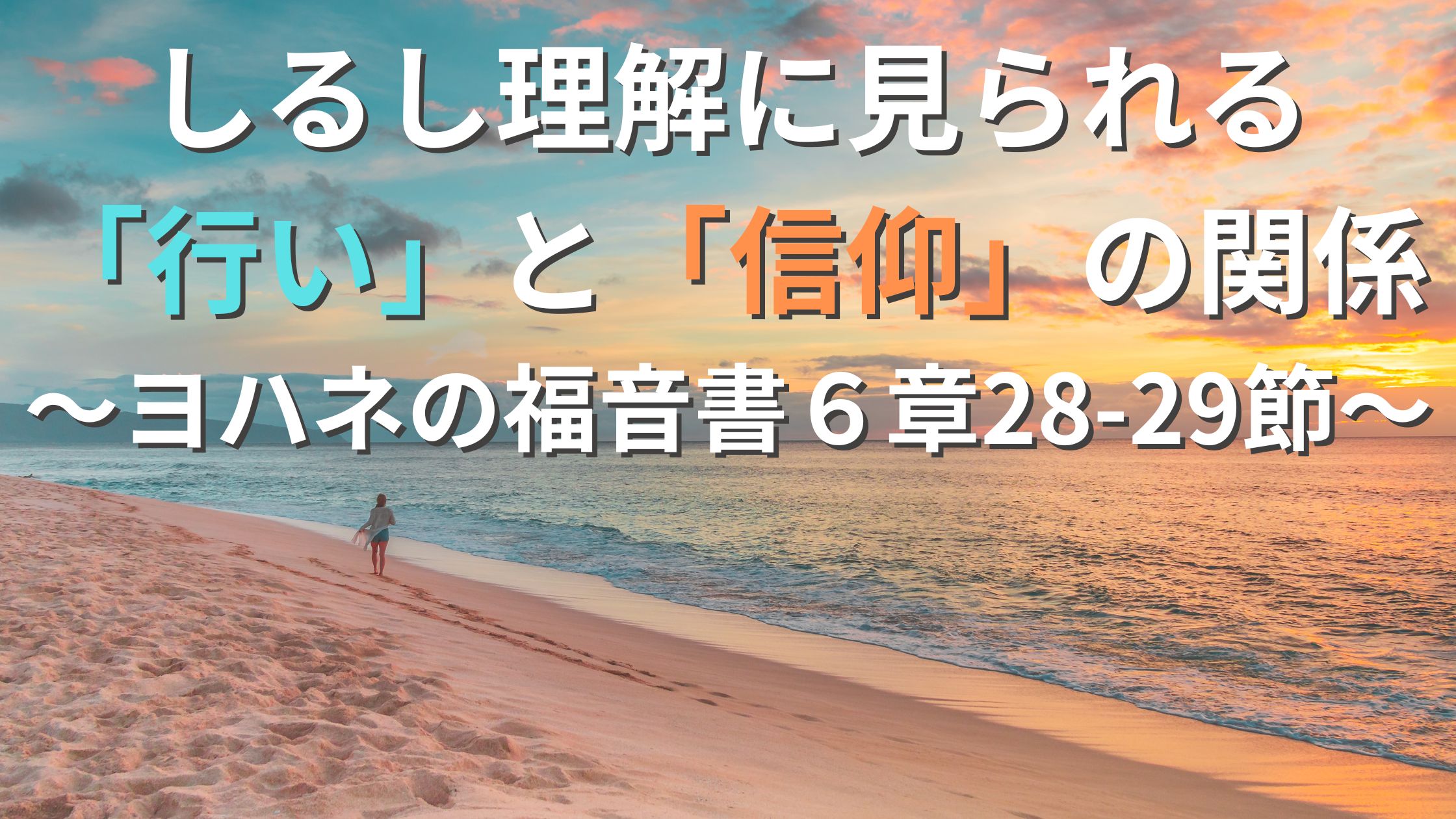キリストの「死」は、キリスト教神学において重要な意味を持っています。しかし、聖書は単に死んだとは言わず、その死は「十字架」によるものであったと語ります。一見すると、キリストの死だけを語っても良さそうなものですが、十字架による死であることに意味があると言えます。
たとえば、多くの人に親しまれている箇所の一つに「キリスト賛歌」として知られるピリピ2章6-11節があります。その一節でこのように言われています。
おのれを低くして、死に至るまで、しかも十字架の死に至るまで従順であられた。
ピリピ人への手紙 2:8(口語訳聖書)
ここでは、キリストの死が、ただの死ではなく、十字架による死であったことが、「しかも(δὲ:even)」という語に表されているように思われます。
それでは、なぜ十字架による死は何を意味しているのでしょうか。歴史的な視点から考えてみましょう。
当時、十字架刑がどのようなものであったのか、ヘンゲルはこう指摘しています。
磔刑は、裸にされて苦しめられている人を特に人目につきやすい場所――人々の集まる場所、劇場、高台、犯罪の行なわれた場所――にさらしものにすることによって、その犠牲者を最大限にはずかしめるものであるが、そのことは、一種の宗教的な次元とつながるものであり、ユダヤ人は特に申命記二一23にもとづいてその点を特に意識していた。
M.ヘンゲル、土岐正策訳『十字架―その歴史的探究』(ヨルダン社、1983年)、109頁
十字架刑が残酷なものであることはよく知られていることですが、十字架の目的は残酷さだけではありません。ここで指摘されているように、十字架刑の目的の一つには「恥」を与えるものであったということがあります。残酷さだけで言ったら、残酷な処刑法は他にもありました。十字架の最大の特徴は、まさに恥を与えることにあったと言ってもよい思われます。それゆえに、十字架刑に処されるということは恥の極みであり、人々からは到底受け入れられるものではなかったのです。
では、なぜ十字架がそれほどまでに忌み嫌われたのでしょうか。
そもそも十字架刑というのは、ローマ社会で行われた処刑方法です。ユダヤ社会のものではありません。ローマ社会において浸透していた価値観というのは、「名誉」と「恥」です。誰もが名誉を求める一方で、恥は忌み嫌われました。その具体的な例としては、『第一コリント』が分かりやすいと思われます。そこには、この世の価値観が教会に入り込み、誰もが人よりも上のステータスを求めているという問題が見受けられます。人からの評判を誰もが求めている社会にあって、恥はその対極に位置します。
このように、そのような恥の極みである十字架刑は、ローマ社会の価値観においては、最も忌み嫌われるものだったのです。この恥の極みという視点から、十字架を観る時に、まさにイエスの生涯、その生き様が象徴的に示されているのが、十字架だと言えるのです。(ちなみに、ユダヤ人にとっては、また別の観点から十字架は理解されています。先のヘンゲルの指摘にもあるように、ユダヤ人にとっては、申命記21:23の教えと深い繋がりがあります。この点については、ガラテヤ3:13参照。)
パウロはこのように述べています。
18十字架の言は、滅び行く者には愚かであるが、救にあずかるわたしたちには、神の力である。
19すなわち、聖書に、「わたしは知者の知恵を滅ぼし、賢い者の賢さをむなしいものにする」と書いてある。
20知者はどこにいるか。学者はどこにいるか。この世の論者はどこにいるか。神はこの世の知恵を、愚かにされたではないか。
21この世は、自分の知恵によって神を認めるに至らなかった。それは、神の知恵にかなっている。そこで神は、宣教の愚かさによって、信じる者を救うこととされたのである。
第一コリント1:18-21(口語訳聖書)
ここで列挙されている「知者」「学者」「論者」はまさに当時の社会で、人々が求めていた「知恵」を持つ人たちです。しかし、キリストの十字架によって示されたことは、まさにそれらとは正反対の「恥」です。誰もがステータスを求めていた社会で、人よりも上にのしあがる生き方ではなく、むしろしもべのように仕える生き方をすること、それはある意味「恥」です。しかし、そのような生き方をされたのは、他の誰でもなく、イエス・キリストでした。
したがって、十字架というのは、単なる処刑方法の一つということではなく、イエスの生き方を象徴的に、そして鮮やかに示すものだったのです。その十字架のことばは、この世の価値観を重んじる者にとっては「愚か」です。しかし、そのようなこの世の価値観から脱却して、全く新しい生き方へと招くのが、十字架のことばなのです。そして、それこそが、信仰者の歩むべき方向を指し示し、その歩みを支える「神の力」なのだとパウロは言うのです。
このように考えると、キリストの十字架というのは、「かっこいい」ものではありません。最近では、十字架と言えば、アクセサリーとして一般的になっていますが、十字架とは本来、恥の象徴なのです。それゆえに、この十字架で死なれたイエスを救い主を信じることは、十字架によって示されたイエスの生き方(この世の価値観からしたら恥と思われるような生き方)を受け入れ、それに倣うということなのです。なんとチャレンジングなメッセージでしょうか。しかし、それが「十字架のことば」なのです。