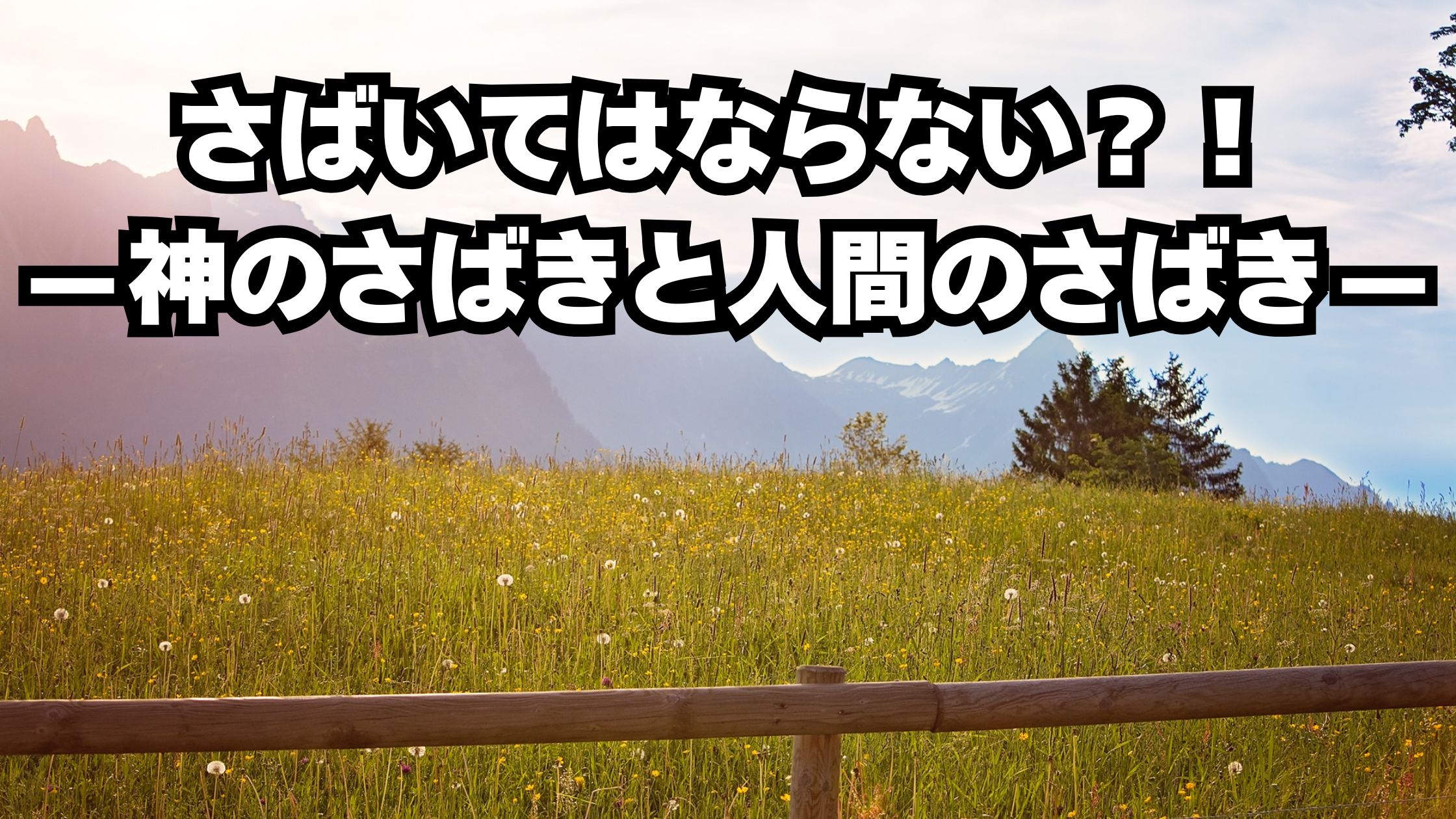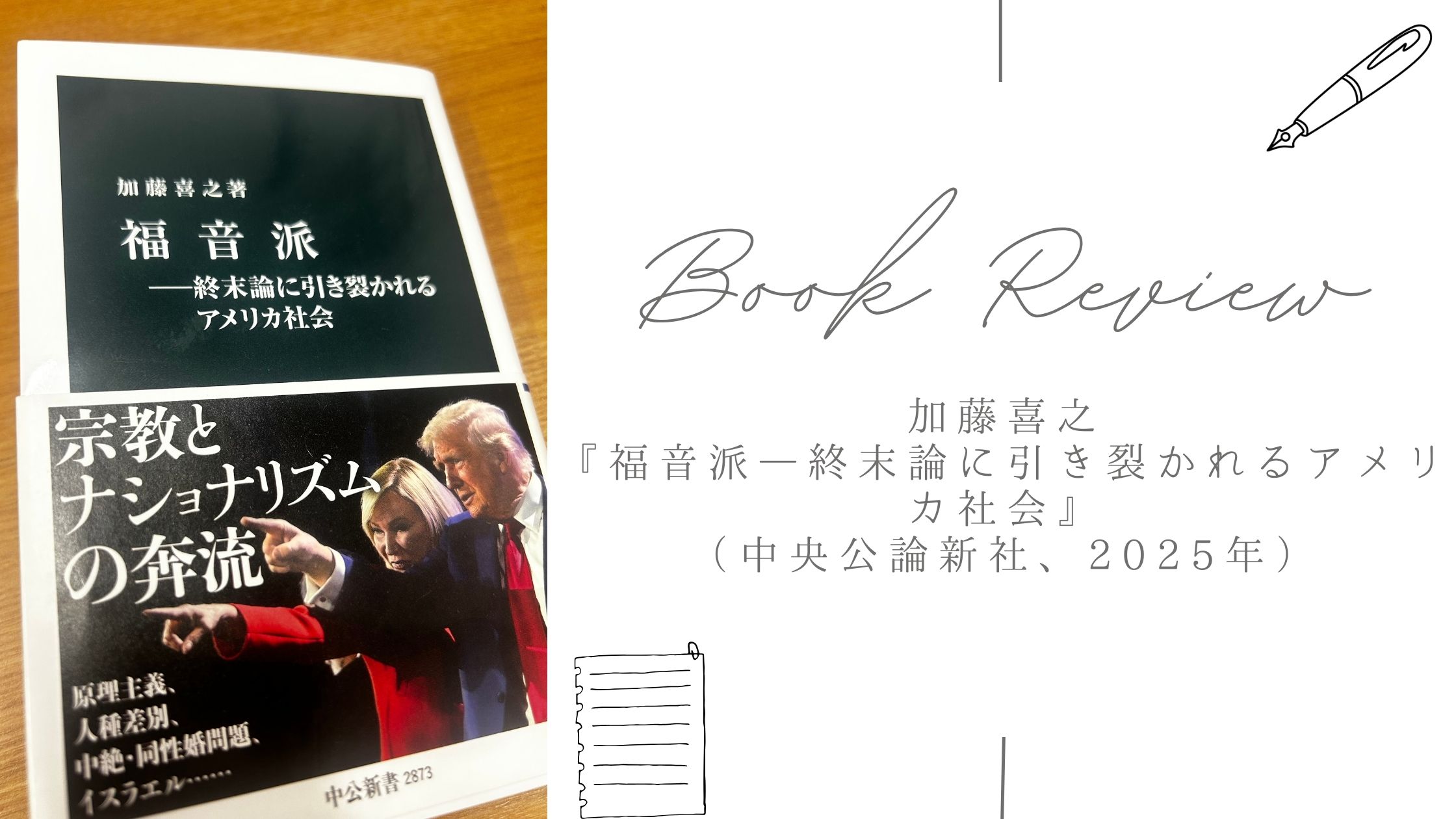高校生の倫理の授業で
私が初めて「哲学」なるものに出会ったのは、高校生の「倫理」の授業でした。
その当時、哲学と聞いても、とっつきにくい印象があったように思います。ですが同時に、哲学の奥深さに漠然とした期待を抱いていました。
そして、その期待は裏切られませんでした。
授業で取り扱われる内容は、決して深くはありません。ですが、教科書や資料集を駆使して、個人的にも調べるようになりました。
その中で、私が最も感銘を受けたのが、キルケゴールです。
高校生の私にとって、キルケゴールを深く理解していたとは到底言えません。ですが、「絶望」の中で神に出会うという考えが、妙に腑に落ちたのです。そして、その時、明確に思ったことは、高校生である私が悩んでいること、考えていること、それでもわからないことは、先人たちも通った道であったのだ、ということです。
そのことを知った時に、とても気が楽になったことを思い出します。
哲学というのは、真剣に人生に向き合って紡ぎ出されてきた先人たちの知恵を言えます。そして、その知恵は、実際、今この世界を生きている私にとって、大きな励まし、助けとなりました。
そのような経験があって、私は学問としての哲学に関心があります。
ですが、一人のいちクリスチャンとして、自分の力で人生を探求するのではなく、神と共に人生の意味を見出す者でありたいと思っています。私の人生と神はどのような関係があるのか。それは、哲学ではなく、神学と言ってもよいのかもしれません。
哲学はむなしい?
キリスト教界では、「哲学」が否定的に考えられることがあります。その際、挙げられるのは以下の箇所でしょう。
あなたがたは、むなしいだましごとの哲学で、人のとりこにされないように、気をつけなさい。それはキリストに従わず、世のもろもろの霊力に従う人間の言伝えに基くものにすぎない。
コロサイ人への手紙2章8節(口語訳聖書)
確かに、キリストによって与えられる神の知恵に比べたら、人間が探求して得られる知恵はむなしいと言えます。ですが、この節だけを切り取って、哲学がむなしく、だましごとであると考えるのは極端でしょう。
詰まるところ、人間の知恵が神の知恵よりも上に来る時に、それはむなしいのであって、大事なことは、その秩序であるように思われます。実際、「哲学」をするということは、自分の人生に真剣に向き合って、考えることですので、それは決して無駄なことではありません。もちろん、コロサイ書で念頭に置かれているのは、そのような人間的な知恵、むなしい哲学であったということはあると思いますが、だからと言って、現代で哲学を勉強する意味が無駄になるということではないと思われます。
それと言うのも、哲学に対する拒否反応を強く感じることが、日本の教会ではあるからです。確かに、哲学者の中には、ニーチェのように、キリスト教に批判的な者もいますし、実際それがキリスト教会に大きな影響を与えたことも事実です。しかし、そのような思想との出会いにも押し流されない信仰に立ち続けることができたら幸いであるように思います。もちろん、無理にそのような荒波に飛び込む必要はありませんが、世の中にはそのような考えを持っている人もいるということを知ることは、大事なことであるように思います。
もっとも、キルケゴールの著書の中でも有名な『死に至る病』は、いわゆる哲学書というよりも、堕落したキリスト教会に対するメッセージであるとも言えるわけですけれども、教えられることはたくさんあります。
最後に
哲学書は膨大です。古典から、最近のものまで、挙げたらキリがありませんが、一冊紹介するとしたら、竹田青嗣『自分を知るための哲学入門』(ちくま学芸文庫)をおすすめします。哲学が自分にとって身近なものに感じられると思います。
また、『月刊いのちのことば』では、「ニャン次郎の哲学的冒険」という連載があります。哲学についてわかりやすく説明されていますので、この機会に哲学に触れてみるのはいかがでしょうか。
ホームページからも連載をお読みいただけます。