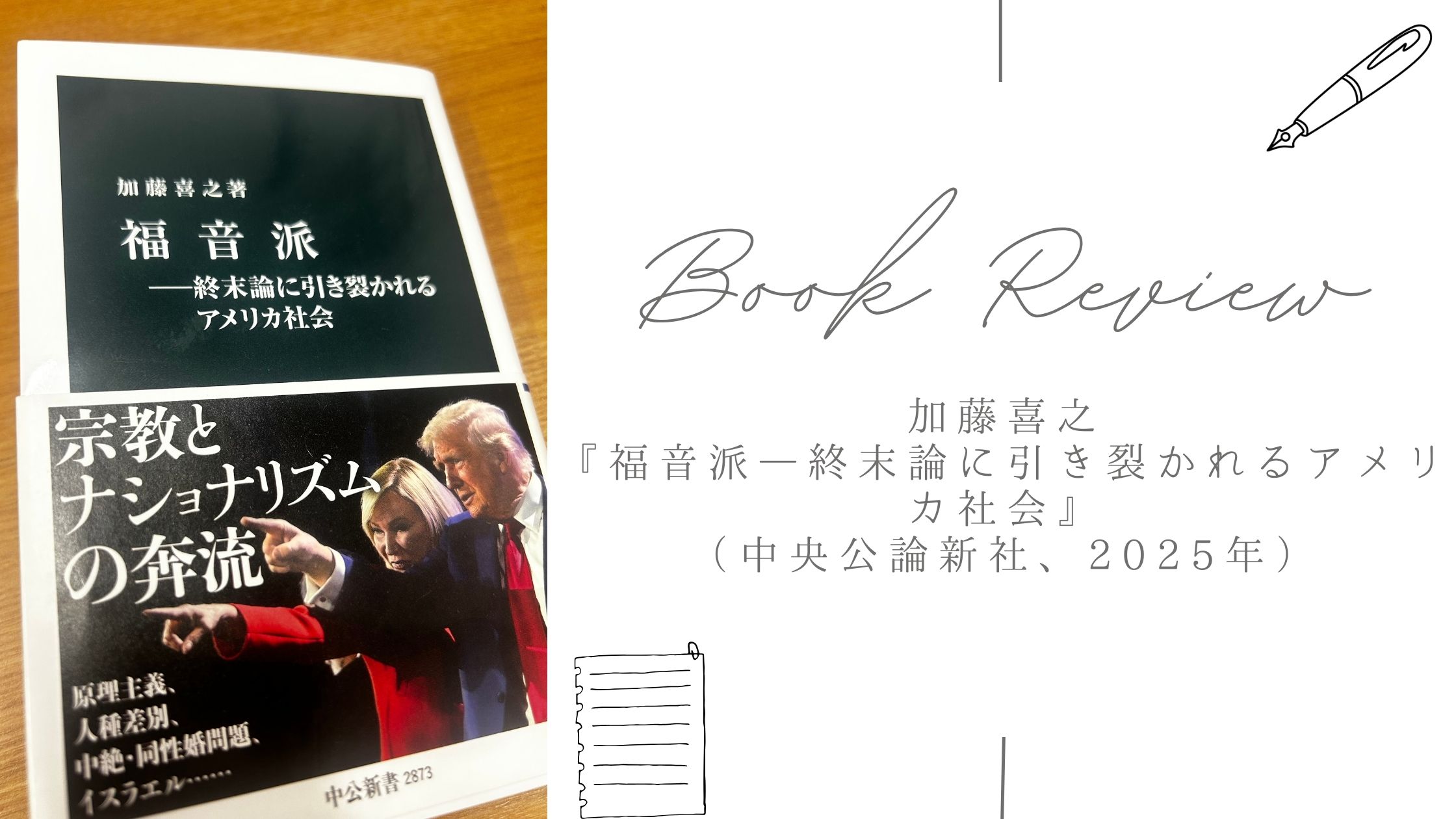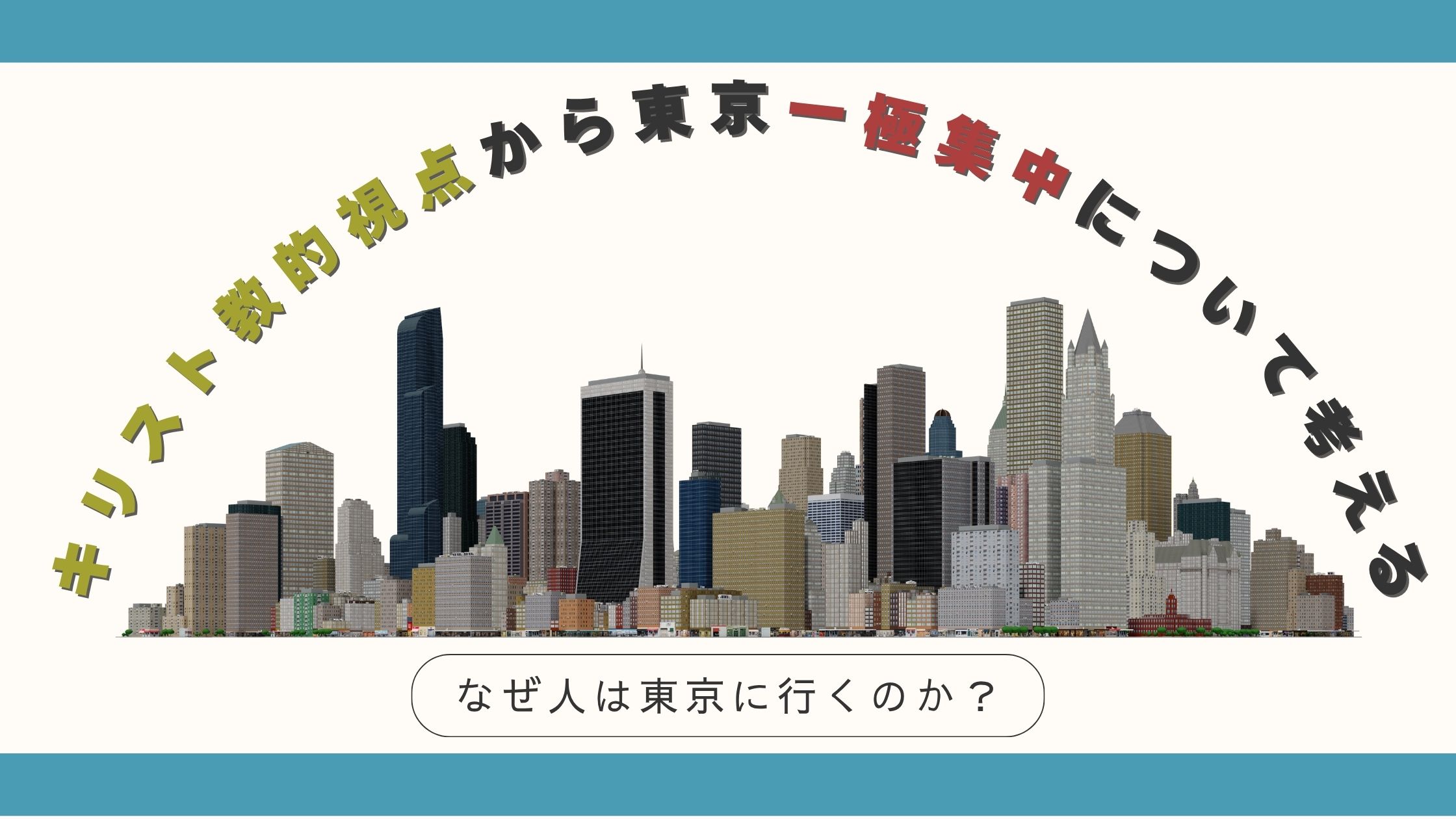アメリカの政治と「福音派」
本書では、アメリカの政治的な背景には古くから「福音派」の影響があったということが、歴史を辿りながら紐解かれていきます。
本書について、一言で言えば、アメリカの近年の歴史の政治的な背景を学ぶなら、必読だと言えるでしょう。確かに、「福音派」を理解すれば、十分であるとは言えません。しかし、福音派を知らなければ、アメリカの政治的な背景を深い次元で理解することはできないことも確かです。
それでは、クリスチャンにとって、本書はどうでしょうか。クリスチャンの読者にもそれぞれの立場があると思いますが、アメリカの「福音派」を知る上で、本書は有益だと思います。なぜなら、アメリカの福音派を知ることは、日本における福音派を理解することにも通じているからです。
アメリカの福音派と日本の福音派
「福音派」という言葉が日本で加速度的に広まったのは、トランプがアメリカ大統領に初当選した2016年頃でしょう。ニュースでは、「福音派」という言葉が飛び交い、日本に住む多くの人が一度は耳にするほどに、知られるようになりました。
しかし、それはあまり良いニュースではなかったかもしれません。というのも、そこで聞く福音派のイメージは決して良いとは言えないものだったからです。多くの福音派クリスチャンは、驚くこともあったのではないでしょうか。というのも、ニュースで聞くアメリカの「福音派」の主張は、どれも「過激」なものに聞こえてきたはずだからです。実際、私も牧師をしながら、アメリカの福音派は、私たちと同じ「福音派」なのかと聞かれることが度々ありました。
それもそのはずで、もはやアメリカにおける「福音派」というのは、純粋な意味での「福音派」ではなくなってしまっていました(もちろん、「それ」が福音派であると言えばそれまでですが)。福音派は、もはや「原理主義」と区別がつけられないほどに近づき、あるいは重なっていたわけです。そのような「福音派」と「原理主義」の関係性について、本書では歴史の変遷の中で詳述されています。もちろん、だからと言ってアメリカにおけるすべての福音派がそのような過激さを持っていたということではありません。本書においても、その点は時折、付言されています。
このように、世間で使われる「福音派」のイメージは、決して良いものとは言えませんでした。ですが、それがそのまま日本でもお茶の間に広がり、「福音派」のイメージが定着した節があります。そのような意味でも、近年ニュースで飛び交っているアメリカの「福音派」と、日本で福音派の立場のクリスチャンは、大なり小なり異なる点があるということも、本書を読めば見出せるのではないかと思います。
しかしながら、日本の福音派の多くは、アメリカにルーツを持っていますので、全く違うとは言えないことも事実です。しかし、アメリカの福音派の歩みと、日本の福音派の歩みは、全く同じではないわけで、その点からも、両者は厳密には同等ではないと考えるのが自然ではないかと思います。皆さんは、その点についてはどう思われるでしょうか。
とはいえ、日本の「福音派」の中にも、極めてアメリカの「福音派」に近い、あるいは同じ考えを持つ立場もあります。そもそも、アメリカの福音派に「倣っている」立場も見受けられます。そのような方にとっては、本書には厳しい言葉が並んでいるように感じられるだろうと思います。それでも、本書の主張に賛同するかはともかく、客観的に「福音派」を見る上では有益なのではないでしょうか。
福音派は批判されて然るべき?
基本的に、著者は「福音派」に批判的な立場にあります。ですが、それは神学的な問題としてではなく、あくまでも実態として浮かび上がってくる現実的な問題に「福音派」が関わっているという点において、批判的であるように思われます。もちろん、そこには福音派の神学理解の影響があることは事実です。しかしそれでも、福音派の中には「右派」も「左派」もいて、一括りに批判しているわけではないことは、本書全体を読めば明らかでしょう。
その一例として、ID理論(インテリジェンス・デザイン)と進化論の衝突で有名な「ドーヴァー裁判」についてのくだりの中でこのように言及されています。
幹細胞研究と進化論教育の二つの事例は、重要な示唆を与える。表面的には、どちらも福音派―社会的な保守派を含む―による科学の進歩への妨害のようにみえる。だが、実はここには目を向けるべき重要な問題がある。たしかに科学は人類の進歩に大きく寄与したが、同時に現代の科学的知識とそれに基づく技術は、環境の大規模な破壊や人間の尊厳を奪う可能性を常に孕んでおり、無批判に科学的な営みを推進する危うさがある。そもそも「環境」や「尊厳」といった概念にまつわる問題は、自然科学を超えたものであり、そうした問題を考えるには自然科学の方法論だけでは解決できない。したがって、科学の定義やその営みは―むしろその発展を望めばより一層―倫理学や社会学や哲学など他の学問領域からの批判にさらされるべきなのだ。
福音派は、直感的にこうした点に気づいていたのかもしれない。もちろん、彼らの主張は荒唐無稽で時として強い調子を帯び、社会的な議論を分断しがちなため、批判されてしかるべきだ。[…]しかしながら、福音派の立場を戯画化するだけでは、現代社会が向き合うべき問題を覆い隠してしまう恐れもある。そうした点からすると、間接的ではあるが、福音派の批判も、とりわけ科学と宗教の関係に関していえば示唆を与えうるものなのかもしれない。(173頁)
これはほんの一例ですが、「福音派」がもたらす益、果たした役割もなかったわけではないことが示唆されています。しかし、それらを鑑みても、アメリカの歴史において、過度に暴走した「福音派」は、分断をもたらす要因となったことは事実です。そして、そのようなことなどを通して、アメリカ国内でも、福音派の印象が悪くなってきたということが、世論調査によって明らかにされています(264頁)。
もちろん、意見の違いというのは、認められるべきであり、仮に「過激」な主張だとしても、それも一意見として尊重されるべきでしょう。しかし、本書で指摘されていることは、それさえも叶わないという現実です。著者はまとめの中でこのように述べています。
あらゆる社会には対立が存在し、対立を通して社会は発展する。これは近代の自由民主主義、すなわち多様な意見を認める政治的なリベラリズムの健全なあり方の一例と言える。しかし、福音派がもたらした終末論的な対立は、リベラリズムの根幹を破壊する可能性を持つ。なぜなら、リベラリズムが機能するためには、言論活動を通して合意や妥協点が見出せるという前提が必要だが、基本的に現在の福音派はこの前提を共有していないからだ。
むしろ福音派は、終末論的な世界観のなかで、対立する相手をサタンや悪魔の支配下にあるものとみなす傾向があり、妥協が困難になる。さらに、サタンや悪魔との霊的な戦いを想定していない福音派でも、なんらかの善悪二元論に立っており、自陣営の世界観と他の世界観とのあいだに共通項を見出すことは少ない。結果、政治的なリベラリズムに不可欠な対話は、機能不全に陥る。むしろ言論活動は、相手の言説を打ち負かすための戦いとなり、真理探究や相互理解、ひいては合意形成に至ることはない。このように、公共圏における福音派の活動は、公共圏が前提とする公共善という考えを破壊してしまう。(284-285頁)
まさにこの点が、著者が言わんとしている「福音派」の問題点であるように思われます。そこに見られるのは、自分(自陣)を絶対とし、相手を間違っていると決めつける態度です。それが、福音派特有の終末論理解から来ているというわけですが、その点は指摘の通りだと、私は思いました。聖書を掲げ、それが神のことばであるとする中で、自分もまた、神の側に立ち、自分を正当化しているということがあります。確かに、聖書を神のことばとして重んじる姿勢は、重要です。しかし、往々にして気をつけなければならないのは、あたかも自分の主義主張を、神のことばとして掲げていないだろうか、ということです。この点については、過去の記事もご参照ください。聖書は戦争を支持しているのか?
神の前に立つ人間は、自分を絶対化するのではなく、絶えず神の前に自分のあり方を問う、謙虚な姿勢が重要になってくるように思います。だからこそ、聖書を学ぶ神学的な営みは、終わることなく、生涯続くのだと言えます。
まとめ
改めて、本書は、特にアメリカの政治的背景を理解するためには、今後必読の書になってくるのではないかと思います。私も、後半からよく知っている人物が登場してくるたびに、キリスト教との関連が浮かび上がり、大変興味深く読みました。最近では、トランプ大統領に関するニュースを見聞きする中で、彼の周辺にいる人物がどのような立場で、どのような影響を与えているのかも見えてくるのは、大変面白いです。
また、クリスチャンの方にとっても、「福音派」を「正しく」理解する上で、本書は有益だと思います。本書でも繰り返し言われているように、確かに福音派の中には、原理主義的な過激さを伴う人たちがいた一方で、「福音派左派」と呼ばれるような人たちもいたことが記されています。ですので、「福音派」だからと言って、全て過激な人たちと批判するのは早計でしょう。そういう意味でも、福音派を深く学べるのではないかと思います。
アメリカにおいて、「福音派」は多数派であり、政治を利用し、また利用されてきた面があります。他方、日本において、福音派、ひいてはキリスト教は、少数派です。ですので、状況は全く違いますが、いつでも「多数派」になることの誘惑には、気をつけなければならないと思いました。
例えば、国のリーダーをクリスチャンにして、国を変えようなどということは、健全な宣教とは言えないでしょう。なぜなら、主イエスご自身は、決して上に立つリーダーにはなられなかったからです。むしろ、上ではなく下に、しもべのように人々の間に住んでくださり、そこで愛を示されました。そのような草の根的な生き方を通して、宣教することがクリスチャン一人一人には求められているように思います。ですので、このような政治的な大きな力を利用しようなどという誘惑にはいつも敏感になっている必要があると思います。
また、トランプ陣営が福音派の影響を受けているということの中には、良い面もあると言えるかどうかの検証も進むことで、より健全な見方ができるような気がします。それはもちろん、「福音派」にとって良いだけではなく、アメリカにとって良い、あるいは世界にとって良いという意味です。例えば、最近ではトランプ関税が話題になりました。それは世界的に見れば批判の的となりましたが、長期的に見た場合、アメリカ国内での生産性を高めるというビジョンが見えます。この動きは、仕事がない人にも仕事を与えることで、アメリカで広がり続ける格差を是正しようとしているようにも思われます。確かに、しばらくの間は、自らの首を絞めることにもなるかもしれません。富める者にとっては犠牲を払うことになるかもしれませんが、それがいつの日か実を結ぶことになるかもしれません。このような犠牲を払う行為は、どこかキリストの教えと共鳴するような気がします。もちろん、トランプ関税がどのような経緯で生まれたのかは、私にはわかりませんが、「福音派」ひいてはキリスト教がアメリカの政治の背景にあることを考えるならば、どこかに繋がりを見出すことも、ひょっとしたらできるのかもしれません。
本書はまさにこのような激動の時代、分断の時代に、読むのにふさわしい本であるように思います。