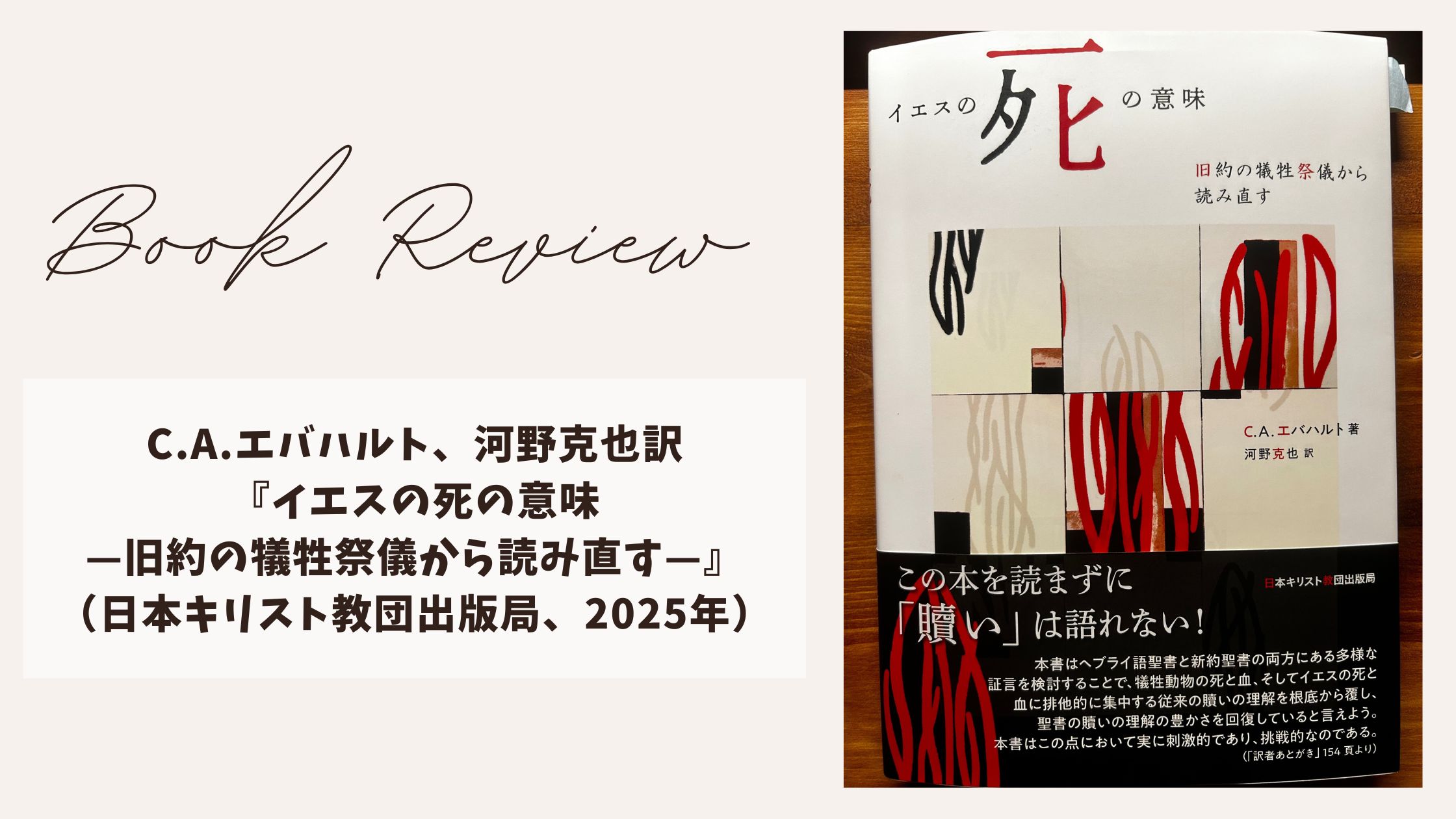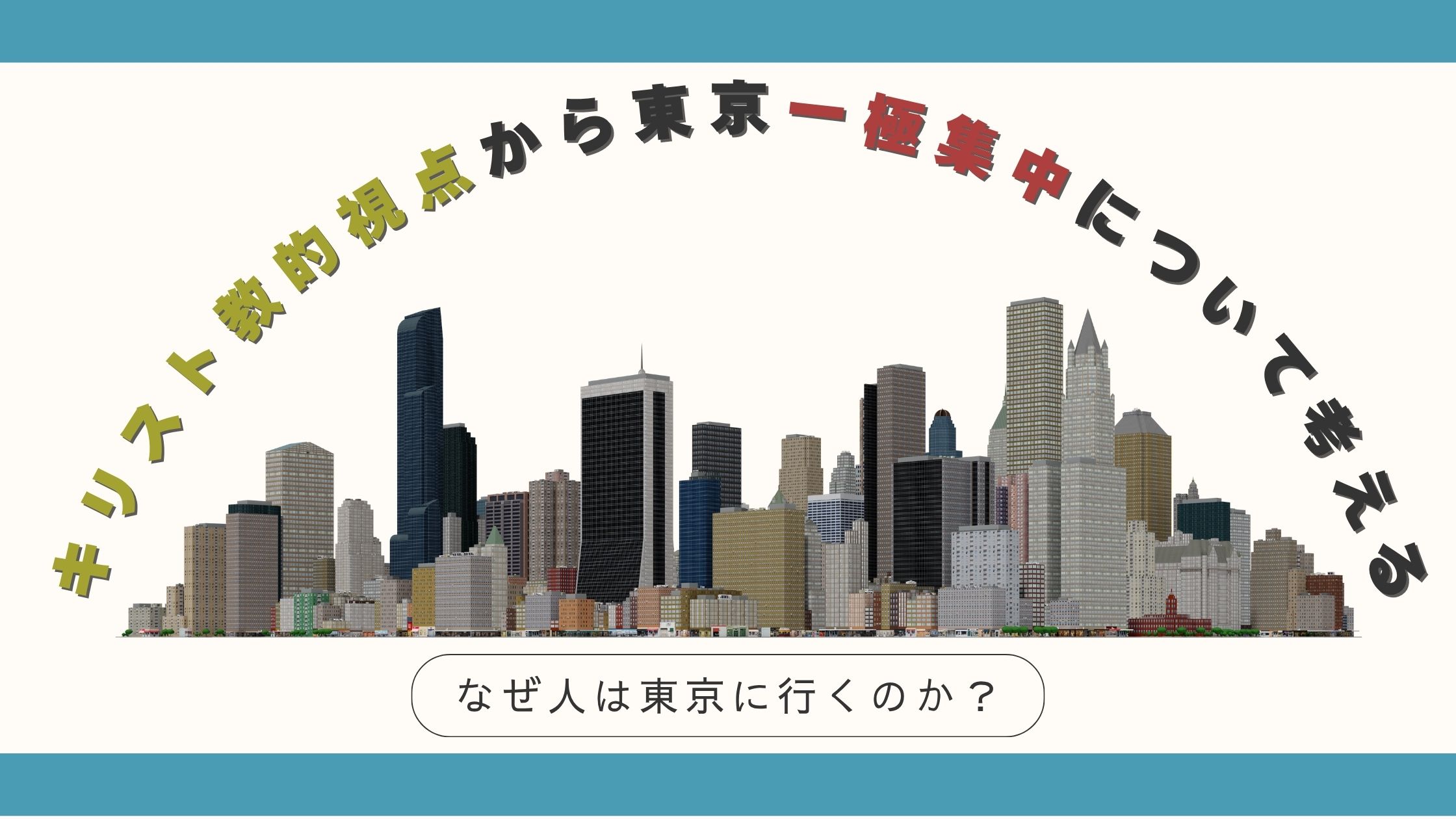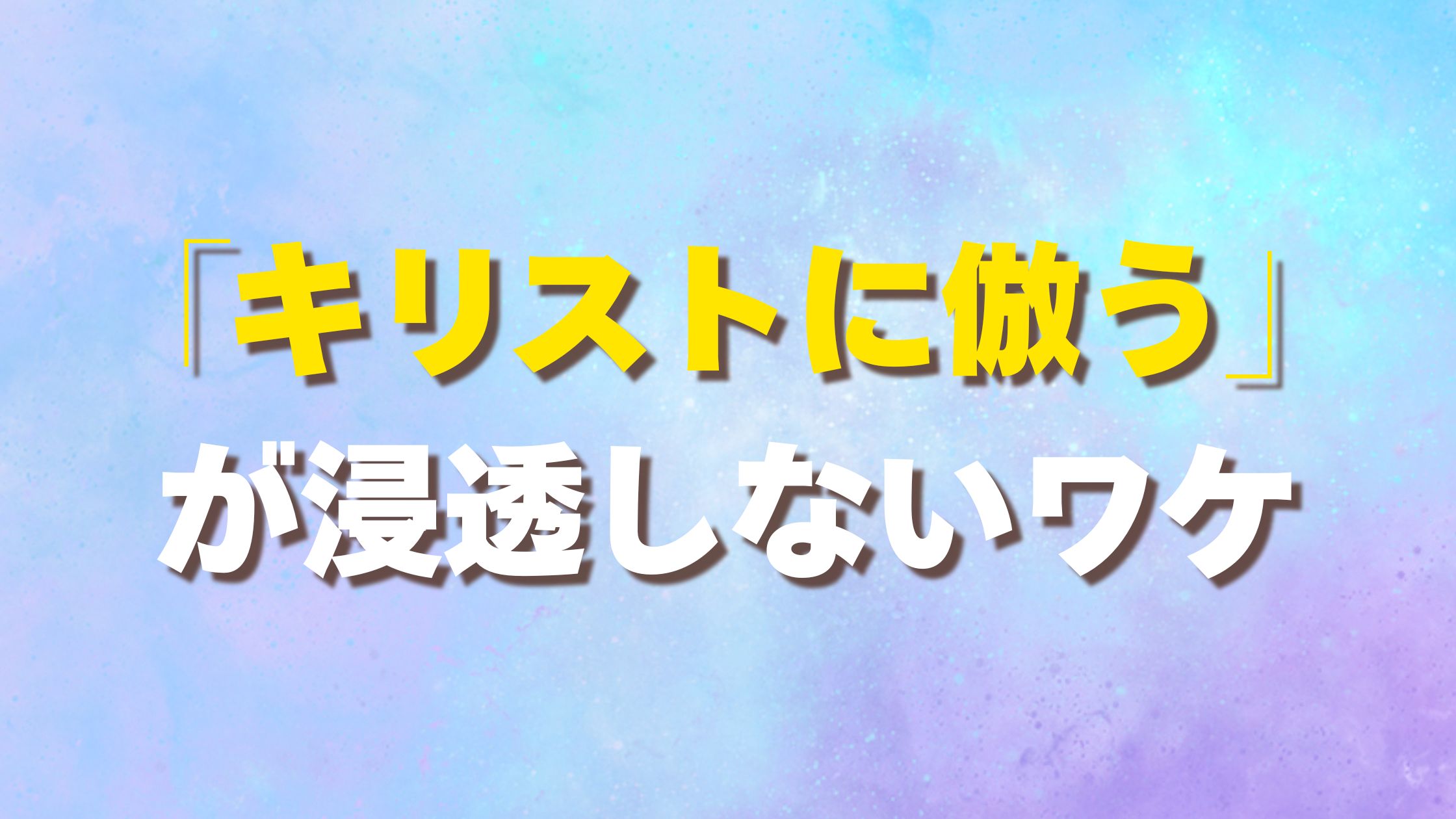本書では、イエスの死の意味について、主に旧約の犠牲祭儀の考察を通して、再解釈されています。そして、それは訳者あとがきにもあるように「刺激的」「挑戦的」なものとなっています。
その理由は明快です。なぜなら、イエスの十字架による贖いは、「身代わり」の死ではないからです。
キリスト教会では、伝統的にキリストの死は「身代わり」だと考えられてきました。しかし、そこには問題もあります。たとえば、キリスト教の神は、子を十字架にかけるような暴虐非道な神なのかという批判です。あるいは、キリストが身代わりに死んでくださったのなら、もはや自分は何もしなくてもよいという他責に陥る危険性です。そのような問題に対して、エバハルトは、あくまでも旧約聖書を緻密に読み込む中で、キリストの贖いの意味を再考しています。
本書は全部で100ページちょっとと、決して長い部類には入りません。また、構成もシンプルです。
- 序論 現代キリスト教徒「イエスの犠牲」
- 第1章 ヘブライ語聖書を読み直す—犠牲祭儀を発見する
- 第2章 イエスの犠牲—キリスト論的贖いのメタファーを理解する
- 第3章 結論—「イエスの犠牲」の再考
中でも、第1章では本書の約70ページにわたって、ヘブライ語聖書(旧約聖書)に登場する犠牲祭儀について、緻密に検討されています。特に重要と思われるのは、これまでは、特定の祭儀に重きが置かれるあまり、他の祭儀が軽視されていたという指摘でしょう。旧約で規定されているささげ物の規定はいくつかありますが、例えば「穀物の献げ物」に関しては、「伝統的また現代の研究の多くは、ほとんど穀物の献げ物に注目してこなかった」(P.66)と指摘されています。一部の犠牲祭儀を強調することで、イエスの贖い理解も偏ってしまっているというのが、旧約の祭儀を再検討する中で浮かび上がってきます。
したがって、イエスの贖いを理解する上でその背景となる旧約聖書で規定されている犠牲祭儀は、必ずしも動物を屠るといった殺す行為を指すものではないと結論づけられます。それゆえに「犠牲」(sacrifice)という用語についても、規定し直す必要があると言います(P.85)。
このように、旧約聖書の犠牲祭儀を読み直すことによって、それらの犠牲は必ずしも「屠殺」を伴うものではないことが明らかにされます。「犠牲は、殺すこと抜きに、また犠牲となる動物なしに可能なのであり、また贖いは部分的には命の効力に基づく」(P.87)。
さらには、「罪のない者が罪責のある者の代わりに苦しむことを想定する『代償』(substitution)という概念は、ヘブライ語聖書の犠牲祭儀からは生じない」(P.87)と結論づけています。
第1章を踏まえた上で、第2章では、実際のイエスの贖いについて、考察されていきます。ここでは、犠牲にまつわる用語(「血」「贖いの場(ヒラステーリオン)」「小羊」など)の検討を通して、イエスの十字架の死が、いかに「身代わり」の死ではなかったということが論証されています。
詳細な議論は、ぜひ本書を読んでほしいと思いますが、ポイントは明快です。冒頭でも述べましたように、イエスの死は「身代わり」の死ではないということです。この点について、訳者はあとがきにて「本書において提示される新たな理解は、特に刑罰代償説に対して挑戦的である。刑罰代償説は、イエスが十字架上で罪に対する刑罰としての死を身代わりとして引き受けたことで、罪人がその死を免れたとする」(P.154)と述べています。
※刑罰代償説についてさらに学びたい方は、J.I.パッカーの著書をご参照ください。
『十字架は何を実現したのか—懲罰的代理の論理』(いのちのことば社)は入手が困難かもしれません。
キリストの死は「身代わり」ではないと聞くと、伝統的な立場にとっては、衝撃的な印象を受けるだろうと思います。ですが、本書の副題には「Understanding Atonement Biblically」とあり、まさに「聖書的」に理解しようとしている著者の姿勢が、本書からは伝わってきます。決して、荒唐無稽なことを論じているのではなく、その根拠はあくまでも、聖書にあるというのです。その姿勢は、まさに伝統的な立場にいるクリスチャンが持つべき姿勢であるとも言えます。もし、エバハルトの主張に異議があるなら、同じやり方で、すなわち、Biblicalな方法で、対抗しなければならないでしょう。
このようにエバハルトの結論は、伝統的な立場のクリスチャンにとっては、衝撃的かつ挑戦的なものと思われると思いますが、しかし、そのような立場の人にこそ、読んでいただきたい一冊だと、個人的には思います。
本書を通して、考えさせられることは、やはり一部分を強調しすぎると、全体の理解が歪んでしまうということがあるということです。特にそのことは、冒頭のところから、私自身もハッとさせられました。
そして、レビ記は多くのユダヤ人にとって最も大切な書の一つである一方で、キリスト者にとっては最も軽視され最も不案内な書の一つになりがちである。
C.A.エバハルト、河野克也訳『イエスの死の意味—旧約の犠牲祭儀から読み直す—』(日本キリスト教団出版局、2025年)、14頁
レビ記は聖書の中でも1、2を争うほどに敬遠されがちな書であり、じっくり読む機会はほとんどありません。ですが、まさにレビ記にこそ、キリストの贖いを理解する鍵があるということは否めません。そのような箇所にも、根気よく向き合っていく必要性を教えられました。
まとめとしましては、本書では、キリストの死の意味について、聖書を元に、説得的に再考されています。そしてその結論は、キリストの死は身代わりではなく、旧約の犠牲祭儀に見られるように、複合的なものであるということです。要するに、これまでは十字架の死が犠牲の死として、いわば否定的に理解されてきたものを、より肯定的な意味として解釈されるということです。死だけを強調するのではなく、他の意味にも注目することが適切な理解ではないかという示唆が本書からは与えられます。
原著の出版は2011年ですが、こうして15年を経て、日本にも出版されることで、キリストの十字架の死の意味について、改めて聖書をもとに、Biblicalに考える機運が高まることを期待します。
ちなみに、キリストの贖罪については、浅野先生による『死と命のメタファ』(新教出版社)もおすすめです。こちらも、出発点は似ていると思います。つまり、キリスト教が教える「犠牲(のシステム)」は、現代社会では到底受け入れられるものではないという批判から始まっています。こちらは、主にパウロの手紙を中心に論考されていますので、エバハルトとはアプローチが異なります。ですが、結論としては、似ていると思います。要は、キリストの死は、単なる身代わりではなく、そこにはキリスト者が歩むべき模範が示されているというようなことが言われています。どちらも、暴虐さが現れているような身代わりの死ではないという点では一致している印象を受けました。ですので、合わせて読むと、補完的に理解できるのではないかと思います。