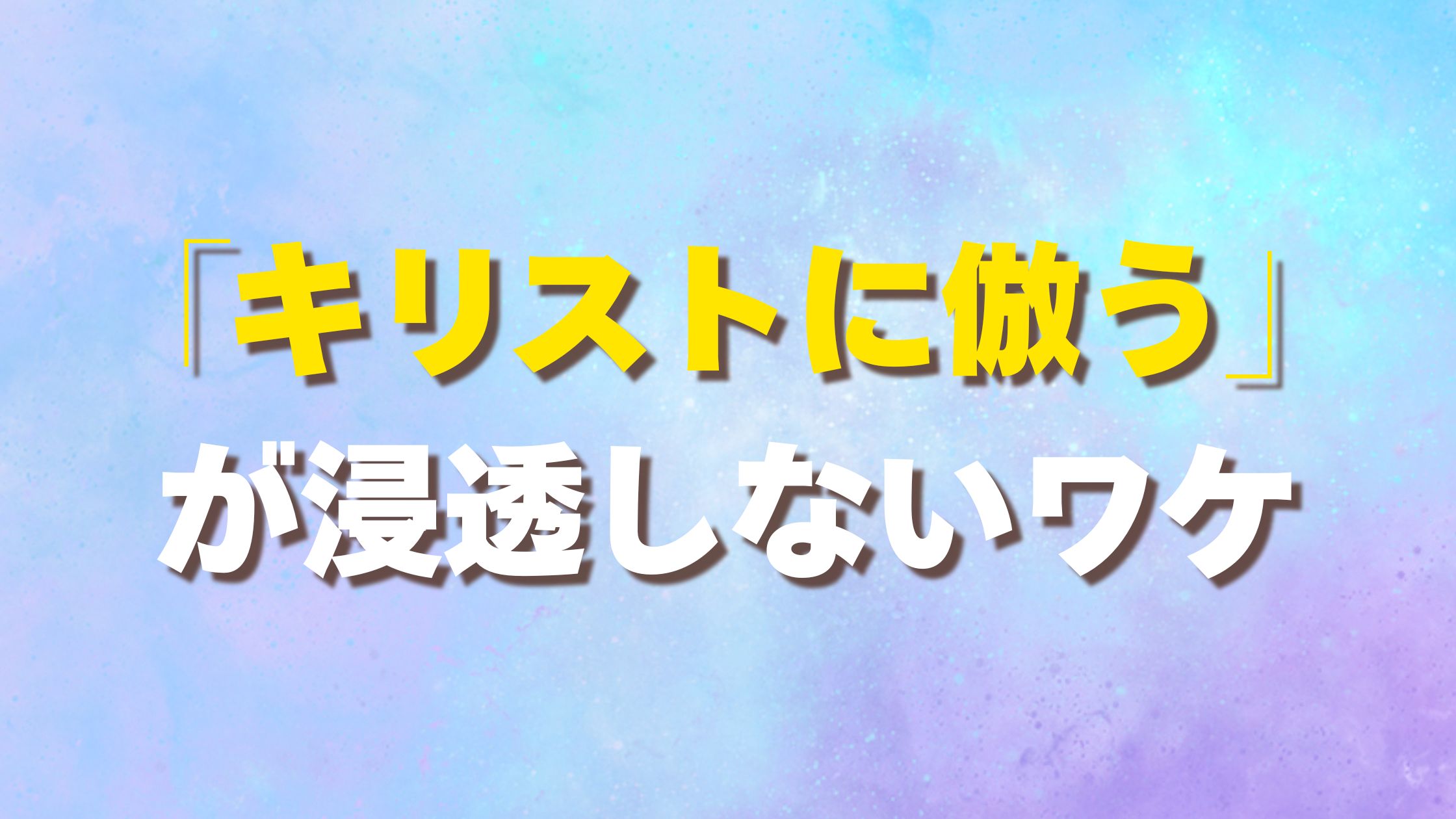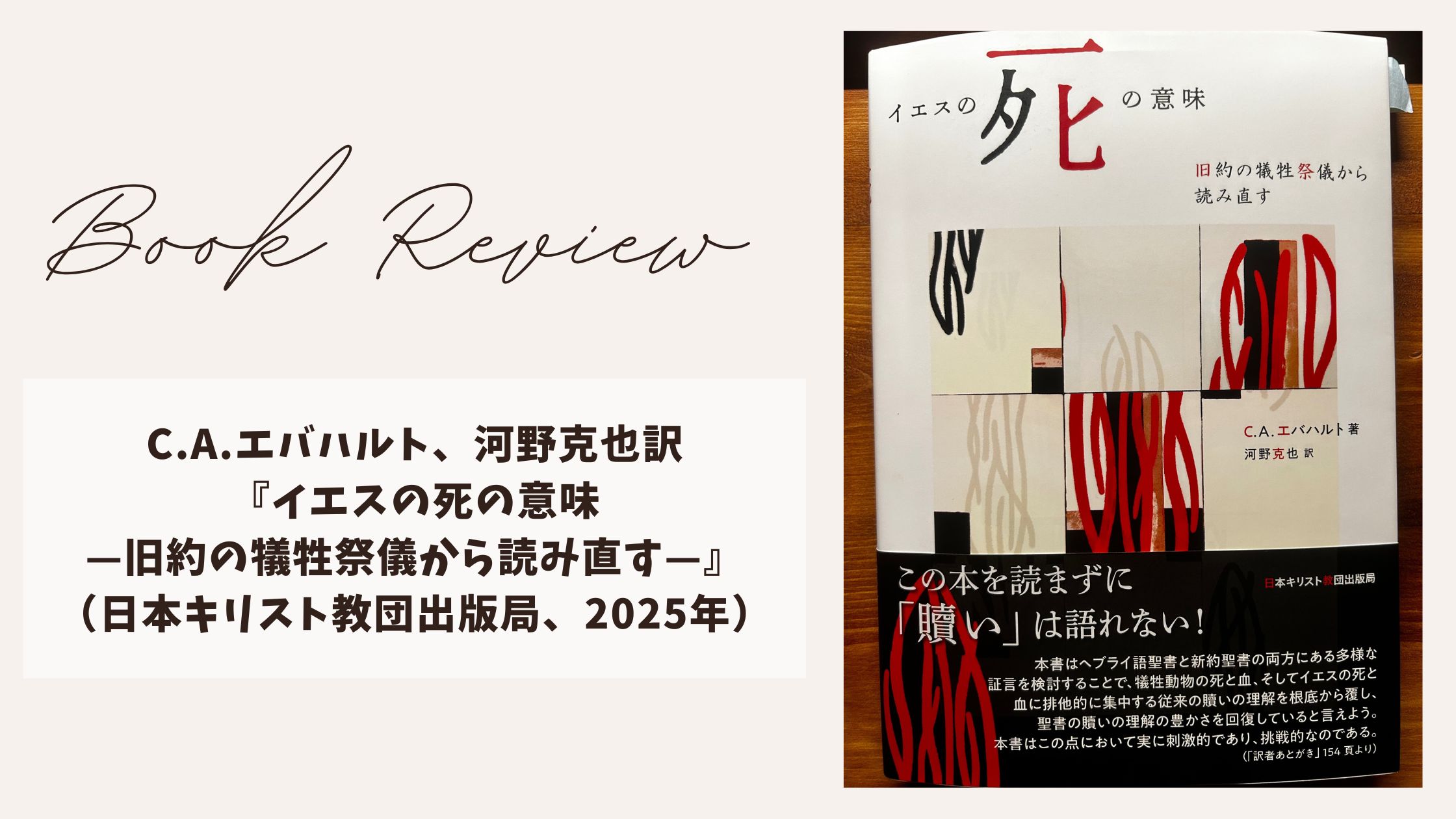「キリストに倣う」ということは、クリスチャンにとっての真髄ではないかと思います。
ただ、牧師をしながら、何となく感じることは、意外と(?)このことは浸透していないように感じます。
そのことの理由を考えてみると、浮かび上がってくるのは、キリストの身代わりの死の解釈です。
よく耳にすることは、キリストに倣うということは、究極的にはそのような死にあずかることである。ゆえにキリストに倣うということが、あまりしっくりこない、というよりも、ある種の拒絶反応を起こしている、ということです。
これは近年、日本のキリスト教会でも改めて問題提起されていることでもあります。つまり、聖書が教える「犠牲」の理解です。『死と命のメタファ』(浅野淳博、新教出版社、2022年)が執筆された動機の一つにも、そのようなキリスト教の犠牲システムに対する批判があったことが冒頭で語られています。最新の邦訳出版では、「犠牲」理解が全くひっくり返るような見解もあります(C.A.エバハルト『イエスの死の意味: 旧約の犠牲祭儀から読み直す』日本キリスト教団出版局、2025年)。
従来、キリスト教の中心は「十字架」であると考えられてきましたが、そのような極端な見方が修正され始めてきていると言えるのかもしれません。
確かに、「キリストに倣う」と言われても、誰一人としてキリストと同じように十字架の道を歩むことはできません。しかしそれでも、自分の十字架を負って、キリストに従うということが求められていることは確かです。もちろんそれは、一般的に批判されているような、犠牲のシステム、つまり一部の人に皺寄せがいくようなものではなく、共に重荷を担い合う生き方であるように思います。
この点において、「身代わり」という認識は、極端な解釈を生みかねないため、個人的には、そのような理解から脱却する時期に来ているのではないかと考えます。
新約聖書で一般的に「代わり」と訳されてきたギリシア語は「ὑπὲρ」と言います。
その一例として、ヨハネの福音書11章50節を比較してみましょう。
「 一人の人が民に代わって死んで、国民全体が滅びないですむほうが、自分たちにとって得策だということを、考えてもいない。」(新改訳2017)
「一人の人間が民の代わりに死に、国民全体が滅びないで済む方が、あなたがたに好都合だとは考えないのか。」(新共同訳)
ここで「代わり」と訳されているのが、先のギリシア語「ὑπὲρ」なのですが、これは単に「ために(for)」という意味ですので、「代わり」というのは意訳し過ぎではないかと、個人的には思います。なぜなら、「代わり」を強調し過ぎると、冒頭でも触れたように、キリストが代わりに死んだゆえに、自分はすることがない、という思考になりやすいのではないかと思うからです。
この点、ESVの訳はシンプルです。
Nor do you understand that it is better for you that one man should die for the people, not that the whole nation should perish. (ESV)
邦訳聖書に戻りますが、ここで不思議なのは、この直後の51節では同じ言葉を「ため」と訳していることです。50節では「ὑπὲρ τοῦ λαοῦ」が「民の代わりに」、しかし51節では「ὑπὲρ τοῦ ἔθνους」が「国民のために」。どちらも「ὑπὲρ」であり、「ために(for)」で訳した方が、原文のニュアンスも汲み取れると思うのですが、なぜこのように訳し分けられているのでしょうか。
おそらく、これはあくまでも想像に過ぎませんが、「代わり」というイメージが、日本のキリスト教会では先行しているのではないかと思われます。もちろん、聖書の他の書との接続なども考慮してこう訳出されたということは言えるわけですが、それでも近年の犠牲理解再考の研究を踏まえるならば、身代わりを想起させる「代わり」ではなく、単に「ために」とした方が、よいのではないかと思います。
キリストが私たちの「ために」死んでくださったということは、十字架が単なる身代わりの死ではなく、信仰者がキリストを模範として、その(十字架に至る)生き様に参与していくものとして理解される必要があります。
確かに、キリストが身代わりに死んでくださったという理解は、ある意味単純で、わかりやすいのですが、それではどうしても信仰者の生き方への関心、視点が欠落してしまいかねません。
キリストの十字架は、信仰者と無関係なものではなく、今もなお、その十字架によって象徴的に表されたイエス・キリストの生涯へと参与することを信仰者に期待するものなのです。