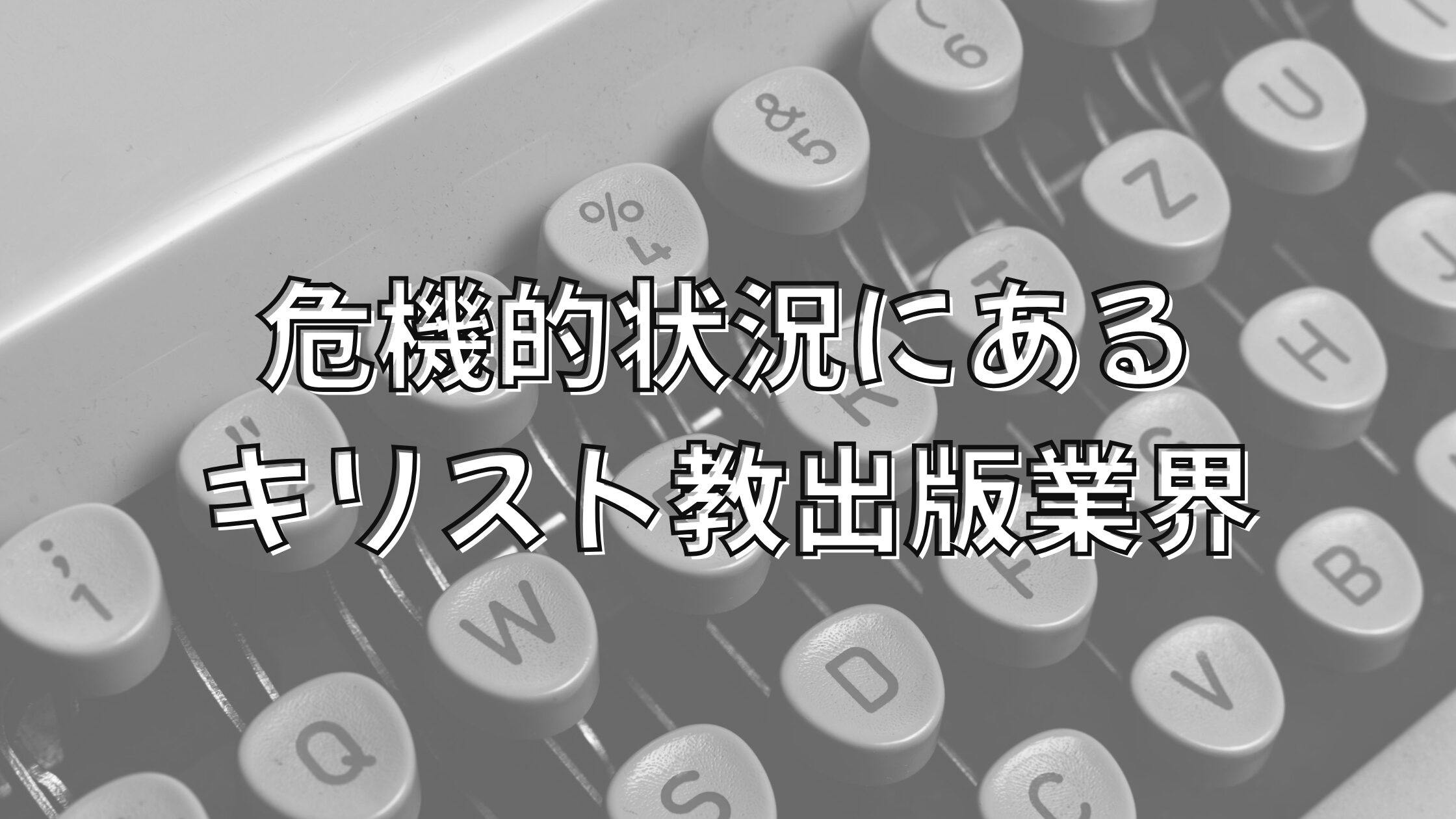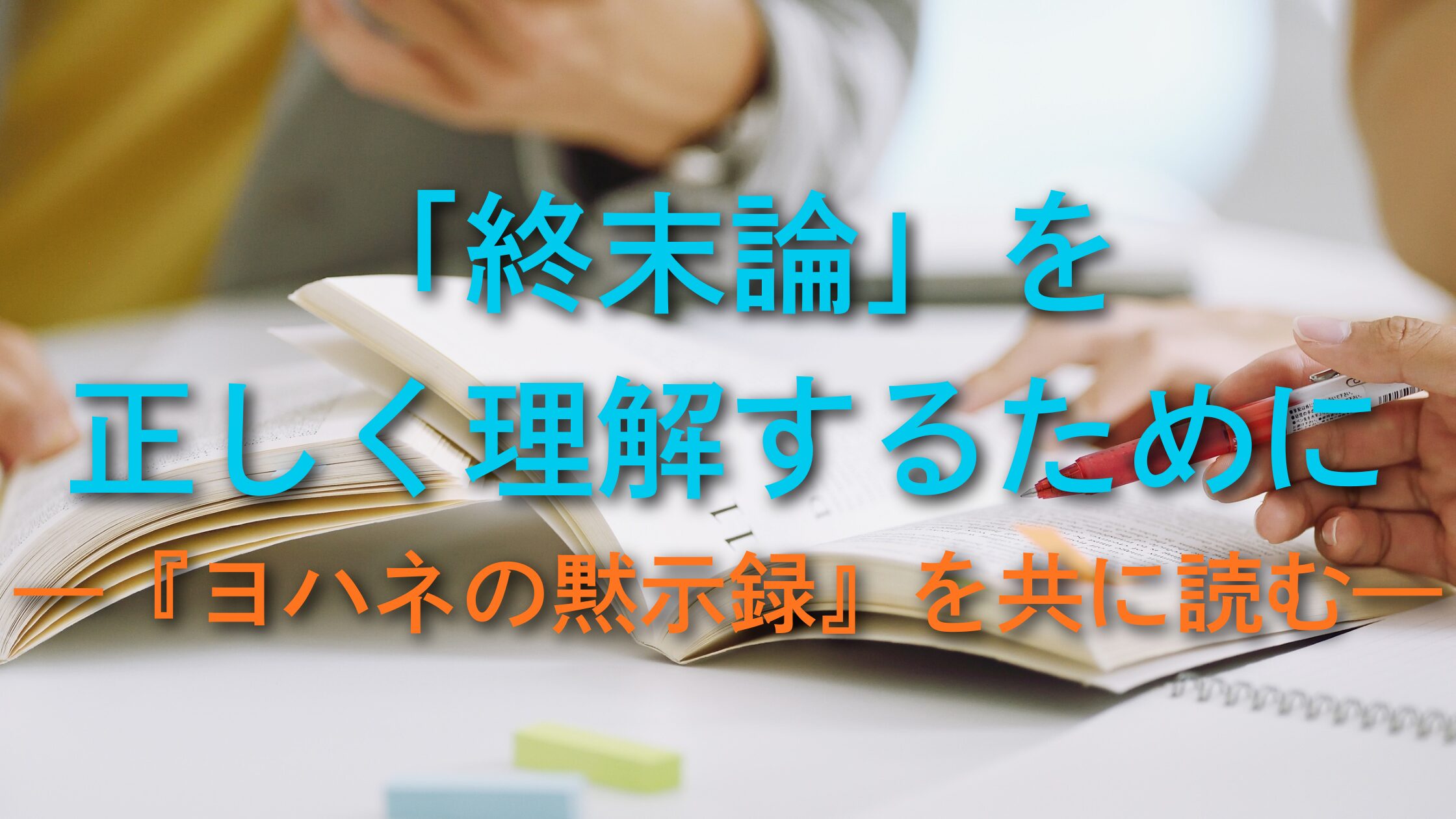先日、キリスト教系出版社が業務を縮小するとの噂を聴きました。これは正式な発表ではありませんので、真偽は不明ですが、もしそうであるとすれば、俄かに信じがたいことでもあります。それというのも、期待されている注解書などの出版も続くと思われていたからです。
しかし、出版業界が大変な状況というのは、これまでも再三指摘されてきたことです。今まさに、そのような危機的状況にある会社はたくさんあるのだろうと推測されます。
私自身、本を読むのが好きで、キリスト教関係の本、特に聖書学の分野は購入するようにしています。それでも、個人的な購買活動では、会社にとってはほとんど収益にならないことは火を見るより明らかです。
そのような理由もあって、本サイトでは、おすすめの本を紹介し、少しでも多くの方に関心を持っていただけたらと願っています。基本的に私が購入した書籍の中からおすすめしています。やはり、読んでみないと、本当におすすめできるかは分かりませんもんね。
話を出版業界の危機に戻しますと、特に「日本におけるキリスト教」×「出版業界」は、はっきり言って、非常に相性がよくないのかもしれません。それというのも、日本のキリスト教人口の少なさと活字離れがダブルパンチなわけですから、当たり前でしょう。
しかし、だからと言って、キリスト教系の出版業界が不要だと言いたいわけではありません。むしろ、必要であると思っています。
こんな時こそ、ピンチはチャンスだと、新しい取り組みが生まれたりするのが、色々な業界に言えること、つまりイノベーションなわけですが、果たして、キリスト教系出版業界に、そのような革命は起きるのでしょうか。
誤解を恐れずに言えば、日本のキリスト教界でも、もっとそのような、なんというか、「野心的(?)」な経営者が出てきてもよいのではないかと思っています。確かに、それはある意味では諸刃の剣とも言えるのかもしれません。実際、利益追求型のビジネスにおいては、自分の利益、私利私欲のためになされていると批判されることもあるような気がします。特にキリスト教界においては。しかし、そもそもビジネスは利益を上げなければ成り立ちませんから、そのような姿勢が全て否定されるべきではありません。ですので、単なる利益を求めるのではなく、そこに誰もが共感するような動機が伴っていれば、なお素晴らしいのではないかと思います。自分の利益のためだけではなく、キリスト教界全体、さらには日本や世界全体を、社会をよくしていこうという思いで生み出されるイノベーションが日本のキリスト教界でも起こることを期待しています。
そのような経営のプロが、すでに日本のキリスト教出版業界にもきっとおられるのではないかと思います。ただ、肌感覚としては、特に日本のキリスト教界では、敏腕ビジネスマンとクリスチャン(のイメージ)が相反するものとして解釈されている現実があるようにも思います。たとえば、クリスチャンになるなら出世コースは諦めなければならないとか。ですが、私はむしろそのような社会の中に、信仰者が出ていくことにも大きな意味があると思います。そのような社会の中で、クリスチャンならではの「違い」を生み出すことができたら、それは周りにもよい影響を与えていくことができるのではないでしょうか。
それでは、日本のキリスト教出版社業界はどうなっていくのでしょうか。そもそも、最近は活字離れが進み、出版社業界も危機的状況の中で、キリスト教出版社業界はどのような打開策を打ち出せるでしょうか。
最近、興味深い取り組みを聞きました。それは「ぶんでんリレー」と呼ばれるもので、いのちのことば社が新潟県の教会を中心に行なっている取り組みだそうです。詳細は、こちらの記事をご覧ください。(種まき「『ぶんでんリレー』in新潟がスタート)
新潟県は縦に長い県ですから、新潟市にあるライフセンター新潟書店だけでは、なかなか遠方から来るということは難しいです。ですが、この取り組みでは、書店から教会に本が委託され、その箱を広げれば、そのまま本を販売できる仕組みになっているそうです。日曜日に販売し、終わったら次の教会へ、教会から教会へとその書籍を渡していき、新潟県の諸教会を繋ぐということで、リレーと称されています。
なかなか画期的なアイディアがあるものですね。それがどれくらい機能しているのかは、私もわかりませんが、このような取り組みが生まれるのは素晴らしいことではないでしょうか。やはり、実物を見て購入する体験は、他には変えがたいものがあります。
こういった取り組みがこれからも生まれてくることを期待しています。
話は変わって、全くの個人的な推測なのですが、日本のキリスト教関係の書籍、特に学術書(に近いものも含む)の多くは「ハードカバー」が多い印象を受けます。一方で、洋書では「ペーパーバック」をよく見かけます。もちろん、ハードカバーもあるにはあるんですが、日本以上にペーパーバックが広まっている印象です。最近のところで言えば、『パウロとパレスチナ・ユダヤ教』もハードカバーもありますが、ペーパーバックもあります。邦訳は、立派なハードカバーのみです。
Amazonなどを見ますと、洋書は選択できるものもよくありますね。
もちろん、コレクション(蔵書)として手元に置いておくなら、リッチなハードカバーの方が好まれるのはよく理解できますが、ペーパーバックという選択肢もあってよいのではないかと思いました。最近では、オンデマンド版として、各出版社からリパブリッシュされていますけれども、それは全てペーパーバックですね。例えば、日本キリスト教団出版局ではこんな外観です。

それでも、ペーパーバックが日本ではあまり普及しないのは、そのような学術書を購入する層が、「値段」を気にしていないという可能性もあります。蔵書として手元に置いておきたい本であるなら、値段は気にしないで買う方が多いということでしょうか。反対に、学術書ではないものは、ソフトカバーが目立ちます。例えば、信仰書の類や説教集など。これはハードカバーで出せば、逆に売れないということなのだと思います。
結局のところ、ペーパーバックを導入したとしても、あまり大きな変化は生まれないという判断がすでに下されているのかもしれません。
また、振り出しに戻ってしまいました。どうすれば、日本のキリスト教出版社はやっていくことができるのか。このことは、これからも本サイトにて、継続して考えていけたらと思います。
そのためにも、まずは多くの方が読書をする喜びを再発見していただけるような情報を発信していけたらと思います。