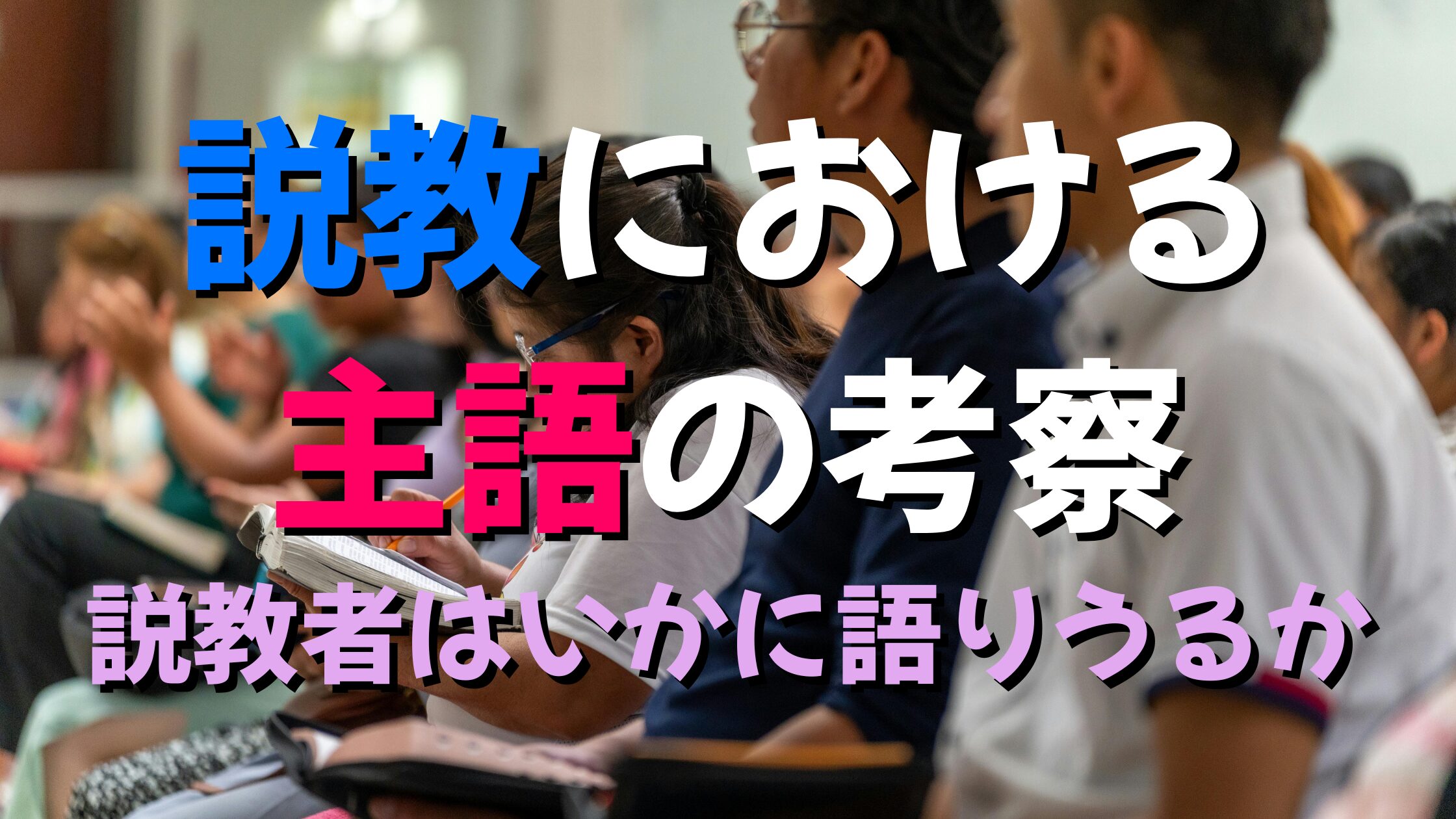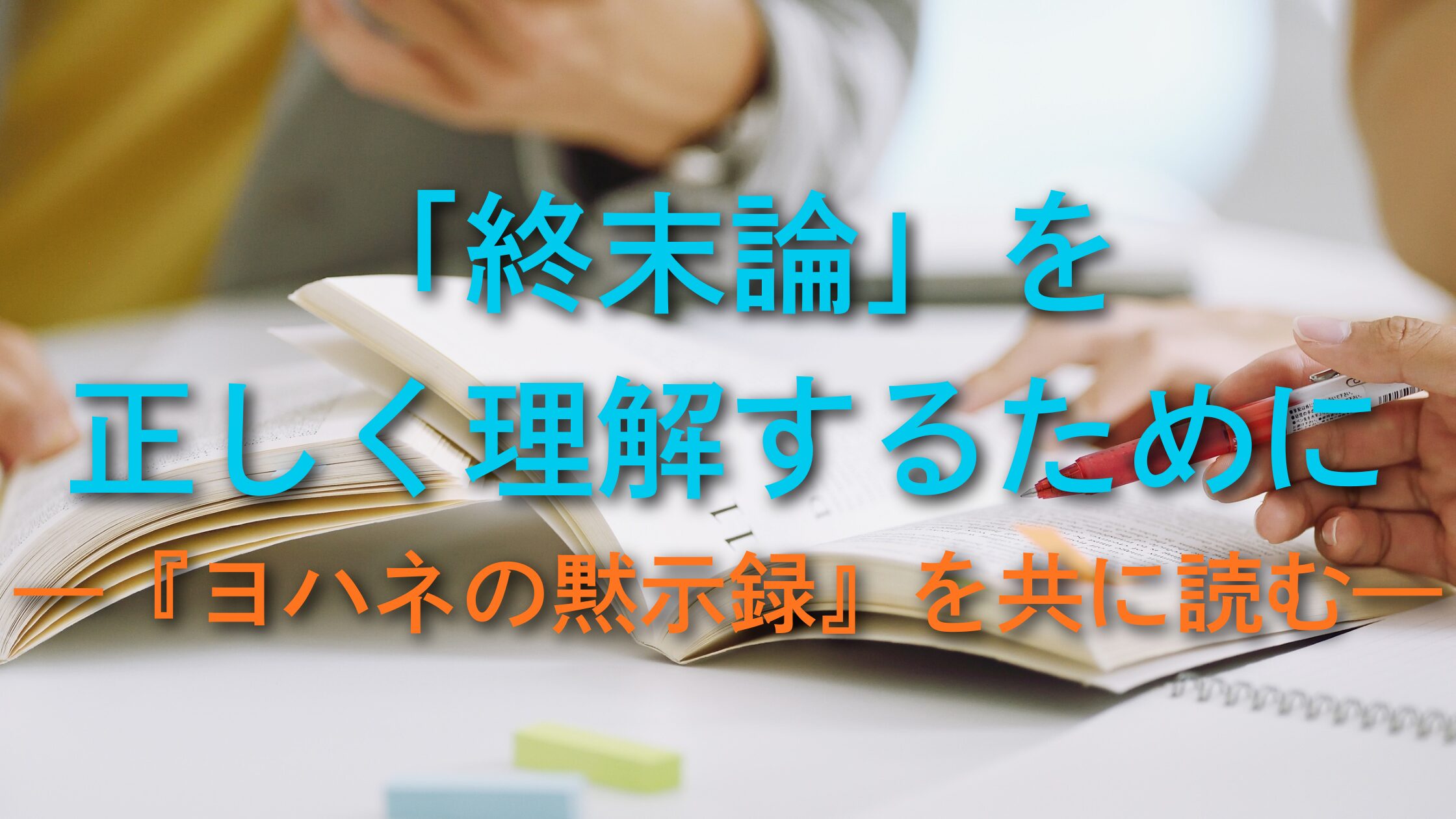日本語では「主語」があまり意識されることはない、と言うのは言い過ぎでしょうか。
日本語の文法では、無意識のうちに主語が省かれがちであることはよく知られていることです。それが日本語のよさでもあり、また曖昧さでもあると言えます。
私は礼拝で語られる説教における主語について、意識していることがあります。それは、基本的に「私たち」を使うということです。
もちろん、このような考え方には、多様な意見があることだと思います。事実、そのようなフィードバックを受けることもあります。ですので、あくまで、現段階における個人的な考えということで、ご理解いただければと思います。
まず、説教における「主語」を考えるということは、説教を語る者の立ち位置をどのように解釈するかに通じるものであると言えるかと思います。たとえば、説教者が神のことばを語る「代理」としての立場であるならば、それは神からのことばを会衆に語ることになるわけであり、それは基本的に「二人称」になる傾向があります。そのことは、主イエスが人々に話しかける言葉遣いにも見られるものです。
しかし、このような解釈には、批判的な意見もあるでしょう。つまり、説教者の「権限」の問題です。説教者は、あくまでも人であり、神ではありません。それゆえに、説教者が神の代理として語ることなどできないという批判です。これは、ある面においては正しいですが、ある面においては正しくありません。
説教者が神のことばを語る場合、会衆は説教者自身の聖書の感想を聞いているわけではありません。そこには、神ご自身が語りかけているメッセージがあることを信じて、聞いているわけです。その点において、説教者自身もまた、ただ自分の思ったこと、感じたことを、適当に語るだけでは、その務めを十分に果たしたとは言えないでしょう。祈りと信頼を持って、語るべきことばを準備するという姿勢が大切になってきます。しかし、もちろん、説教者が「人間」であることは事実です。ですので、神のことばを語る代理だからと言って、それが極端に「神格化」されるべきではないでしょう。
これはとても興味深いことなのですが、旧約聖書において、イスラエルの王というのは、神の代理であり、イスラエルの民から見たら、神同然の人物として理解されていたようです。それゆえに、たとえば、『詩編』などでは、イスラエルの王を賛美する内容が散見されます。これは、現代的な感覚で読むと、なぜ人間である王が賛美を受けているのか、と感じるわけですけれども、実は古代イスラエルにおいては、王は神と等しい存在であったために、そのような賛美が歌われていたということです。
イスラエルの王は、神の代理として、イスラエルの民を治めることが求められていました。ですが、それは神がいない、ということを意味しません。イスラエルの王は、神に全幅の信頼を置いていることで、換言すれば、常に神と繋がっていることで、民を正しく導くことができました。その点において、まさにイスラエルの王は、神と重なっている、そのような人物であったと言えます。
その一方で、イスラエルの王は民の「代表」でもあります。イスラエルの民が過ちに陥るならば、それに対するさばきから、イスラエルの王も逃れることはできません。とはいえ、イスラエルの民に不信仰は、往々にして、王の影響を受けているということは否めませんが。
いずれにしても、イスラエルの王というのは、ある面においては、神の代理であり、ある面においては、民の代表であったと言えます。
私は、現代における教会の説教者が、イスラエルの王に通じているとは全く思っていませんが、この「代理」と「代表」という概念は、通じているものがあるように思っています。
説教において、神のことばを語るということは、それは説教者の個人的な感想を話すことではなく、今目の前にいる会衆に神が語ろうとしておられることを伝えることであり、そこには非常に重たい使命があると言えるのではないかと思います。だからこそ、聖書をしっかりと学び、語る責任があります。その意味において、そのことばは、人間的な言葉とは一線を画すものだと言えます。
しかし同時に、説教者は人間です。説教を語る時だけ、人間でなくなるということはあり得ません。説教者が語ることが絶対とされ、神格化されることに対して、私は強い懸念を抱いています。
それでは、どのようにこの相反する二つの側面を統合することができるのか、と言えば、冒頭でも触れたように、「私たち」という主語を使うことによって、だと考えます。
説教者が語ることばは、説教者の個人的な感想ではなく、神のことばである。しかし、同時にそれは説教者という人間を通して語られる人のことばでもある。そのことを考えた時に、「私たち」と語ることで、両者が統合できるのではないかと思います。神から会衆に向けて一方的に語られる二人称ではなく、あるいは、説教者自身の自分語り、つまり一人称でもなく、「私たち」です。神が「私たち」に語りかけているメッセージを、説教者が語ると同時に、説教者自身も神の前に立つ一人の人間として受け止める、という姿勢が、両極端な解釈から守ってくれるように思います。
たとえば、「あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい」という教えは、まさにイエスの教えであり、それは当然のことながら、「あなた」、つまり、二人称です。では、一人称で語るとどうなるか。命令形のままだと「私は…愛しなさい」となり、少しいびつですが、「私は…愛します」とすると、それはただ説教者の感想であり、神からのメッセージだとは受け取られません。だからこそ、「私たち」とすることで、それは「私たちは…愛しなさい」「私たちは…愛します」となることによって、そこには神から会衆への語りかけと同時に、説教者自身もその語りかけを受けている会衆の一人として含まれることになるわけです。
ただし、これはあくまでも原則であり、基本的なこととして意識していることですので、全ての場面、文脈で適用できるものではない点には注意する必要があるかもしれません。
このような「説教者」の立場についての解釈は、礼拝の形式にも、象徴的に表されていると言えます。たとえば、説教者が「どこ」に座っているのか。ある教会では、講壇の上に椅子があります。それは、「神学的」には、会衆とは分けられていることを意味する場合が多いです。したがって、この場合は、神の「代理」としての側面が強調されていると言えます。一方で、会衆の席と同じ側にある場合、それは会衆の中から出てくるということであり、民の「代表」という側面が強調されていると言えるでしょう。
しかし、そのような違いが現代の各教会に見られることは、個人的には悪いことであるとは思っていません。事実、どちらの側面もあると思うからです。ですので、そのような、言ってしまえば「形式」で、目に見える教会に批判的になってはほしくないというのが、率直な感想です。
以上見てきましたように、説教者がどのように説教を語るのか。その主語について考察することで、説教者自身の立場や説教の受け止め方、そのようなものを理解する一助となれば幸いです。繰り返しになりますが、説教が、神のことばとして語られながら、同時に人間が語っている言葉であること、どちらの側面もバランスよく理解していることが、説教者にも、また会衆にも求められているように思います。
その上で、私が個人的に大切にしていることがあります。これは、私の恩師から教えられたことなのですが、説教者が神のことばを語るときに、そこには重大な責任が伴います。だからこそ、しっかりと勉強しなければなりません。聖書を適当に読んで、その場の思いつきで語ることほど、不遜なことはないでしょう。しかし、同時に、説教者が語るその言葉が、ことばの剣となって、人を刺してしまうことにも、気をつけなければなりません。正しいことを語ることだけが、「説教」ではないのです。だからこそ、大事なこととして教えられたことは、面と向かって話せないことは、説教では語らないということです。
説教者が陥りやすい過ちは、神が語っているなら、何でも語れるということです。ですが、そこで思い出したいのは、「私たち」です。「説教」は神のことばであり、かつ人間の言葉である。そのバランスを健全に保つために、面と向かって話せないようなことは、説教でも語らないこと。私はこの教えが、本当に説教者には必要なことだと思っています。ともすると、説教が誰も反論できないような神格化されたものとなってしまうことがあります。ですが、説教で語ることは、面と向かってその人にも語ることができる。そこまでして、その言葉に責任を持てる言葉を語ること。そのことを意識することを教えられました。
これらのことについて、説教者の視点から、あるいは会衆の視点から、様々な意見があると思います。いろいろな意見や考えを私も聞いてみたいと思います。そのようなプロセスの中で、説教の健全さが保たれていくのではないでしょうか。