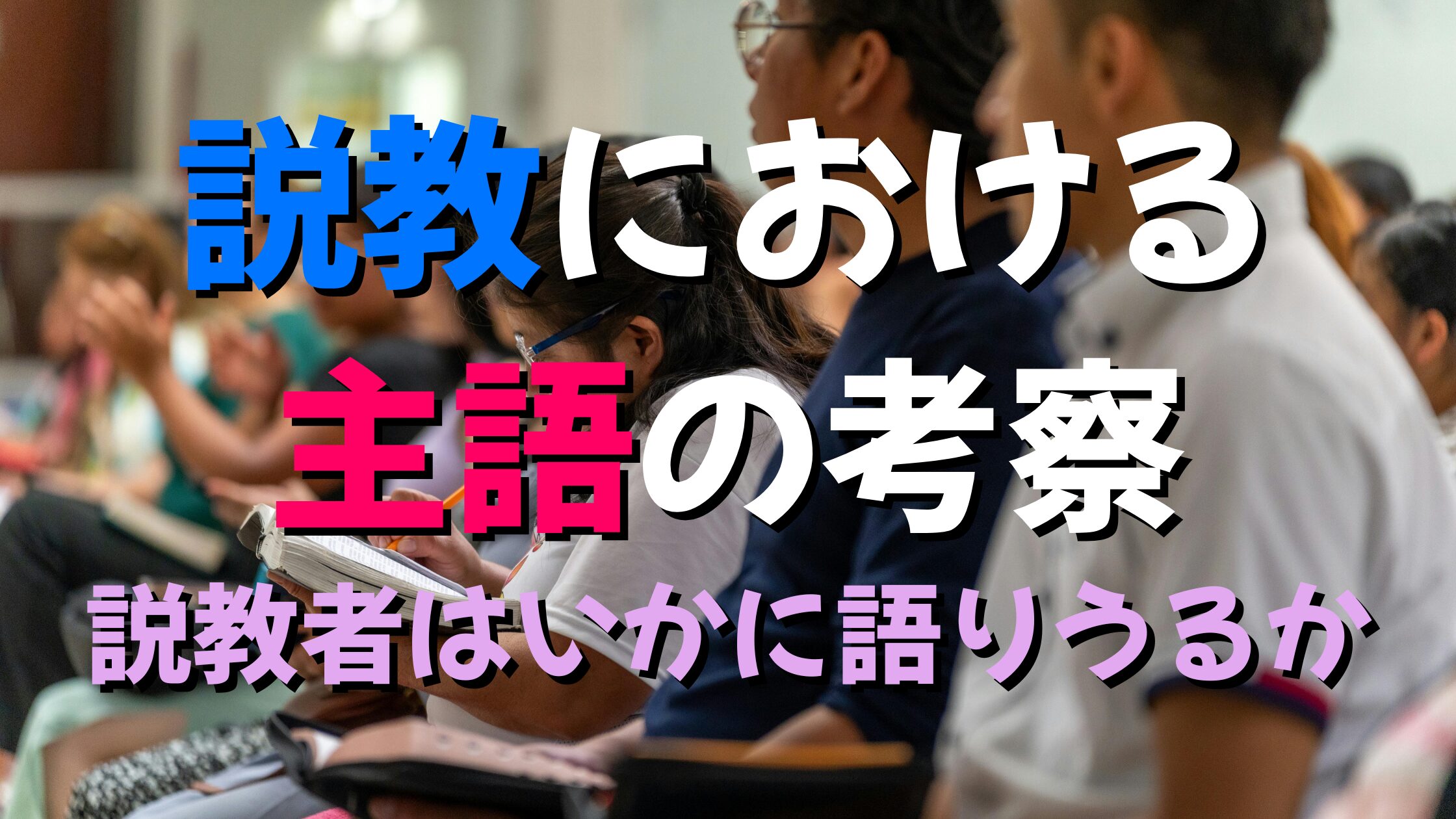【アテンション・エコノミー】
アテンション・エコノミー(英: attention economy)とは、インターネットが発達するなどした情報過多の高度情報化社会においては、情報の優劣よりも「人々の関心・注目」という希少性こそが経済的価値を持つようになり、それ自体が重要視・目的化・資源化・交換財化されるようになるという実態を指摘した概念。
Wikipedia「アテンション・エコノミー」より引用
昨今、「アテンション・エコノミー」と同じ現象があらゆる業界で起こっていて、ますますその影響力が増しているように思われます。ただ、厄介なのは、そのことが必ずしも認知されているわけではないということです。
耳目を集めるもの、衝撃的なものなど、人の関心を集めるものに「自然」と目や耳が向かうことは、ある意味、当然のことではあるのですが、そのような傾向を利用して、あらゆるコンテンツが世の中に生み出され続けているという現状があります。
このことは、当然キリスト教界にも当てはまることで、注目を集めるために極端なことが主張されるということがあります。たしかに、「わかりやすい」「短い」「簡単」といったものは誰であっても惹かれます。そして、それが一概に問題であるとは思っていません。ただ、それには弊害があることも、情報を得る側には知っておく必要があるのではないかと思います。
わかりやすさを追求するということは、要するに、周辺知識を極力カットするということであり、それは言ってしまえば「極論」です。極論というのは、白黒はっきりついていて、賛同する人にとっては、耳に心地よい、聞いていて気持ちが良いものだと言えます。しかし、そのような極論の積み重ねは、非常に偏った解釈に繋がりやすいことは明白でしょう。
あくまで個人的な思い出ではありますが、まさにアテンション・エコノミーの対局にあるのが「教授」であるように思います。当時、学生であった私は、「要するに何が言いたいのか」を聞きたくて、質問をしました。しかし、その問いに対して、「一言」で返ってきたことはありませんでした。たとえ、どれだけシンプルに答えることができたとしても、それを「正しく」受け取れるか、解釈できるのかは、また別の問題だということです。教授がどれだけ簡単に説明したとしても、学生である私が、その考えを全く同じように理解できるわけではありません。
このことは、学術書や論文を読むときにも感じることです。結局、最後のページには「結論」が記されています。そして、それは非常に短い場合が多いです。著者が主張したいことは、明瞭なのです。しかし、そのことのために、膨大なページが割かれます。それは、その文章の目的は、ただ「結論」を教えることではないからです。たとえ、それだけを教えたとしても、そこに意味がないからです。どのような思考、実験、プロセスを経て、その主張にたどり着いたのか、どのようにその主張の意義を伝えるのか。これは序文から結語に至るまでのプロセスにかかっています。
しかし、「忙しい」現代人にとって、そのような長大なプロセスは敬遠されがちです。それゆえに、簡単にまとめられた結論に飛びつくわけですが、その結果、極端な解釈、極論が広まってしまう現象を生み出しているように思われます。
ただここで視点を変えることが大事なのではないかと思います。たしかに、「長い」ということに抵抗を覚えるのは必至です。できれば、「短い」「簡単」な方がよいと誰もが考えます。しかし、視点を変えるとどうなるでしょうか。その「長さ」は、受け手が理解する時間と考えることができるのではないでしょうか。なぜ、くどくど説明するのか。受け手は最も簡単に説明してほしいと思います。しかし、短く説明したところで、その「短さ」が受け手にとって益となるかはわかりません。むしろ、その短さこそが、理解を妨げているということもあるように思います。だからこそ、「長さ」や「複雑さ」など、受け手にとって抵抗を覚えるものは、視点を変えて、理解するために必要な時間、プロセスであると考えることが大事なのではないでしょうか。
かくいう私自身も、「簡潔さ」「短さ」「わかりやすさ」こそ正義だと思ってきた人間です。その結果、極端な解釈に陥ってきたこともあったことが、今更ながら思い出されます。そのようないわゆる「極論」というのは、白黒はっきりしているので、痛快なわけですけれども、世の中にある多くの事象はそれほど単純な話ではありません。その意味において、学問を生業としている「教授」は、そういったことを心得ておられたのだと腑に落ちました。
以上のことから、極端な意見で耳目を集めるスタイルが一概に問題だとは思いませんが、少なくとも、そこには弊害があることも認識されるようになることが望ましいように思います。