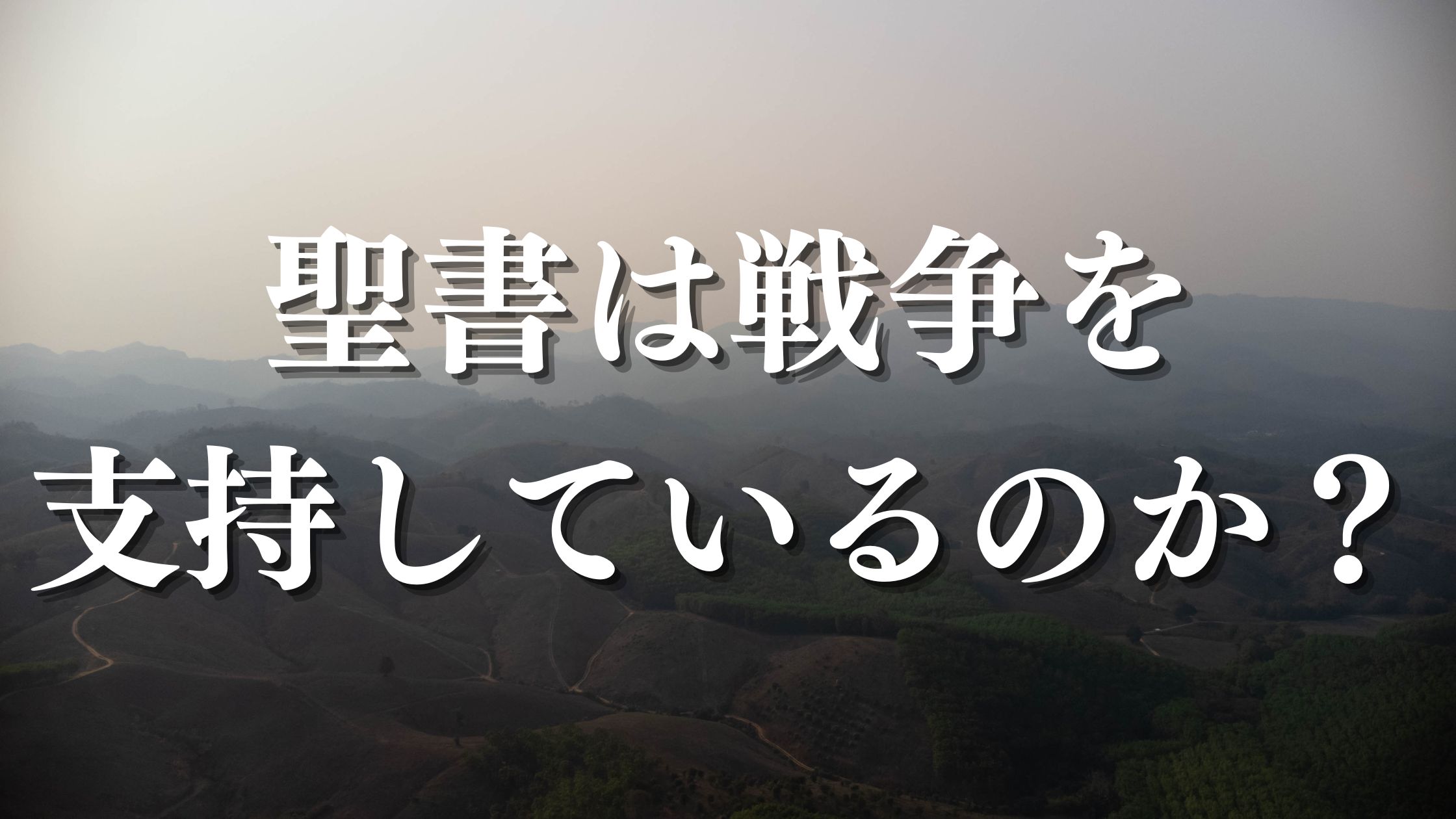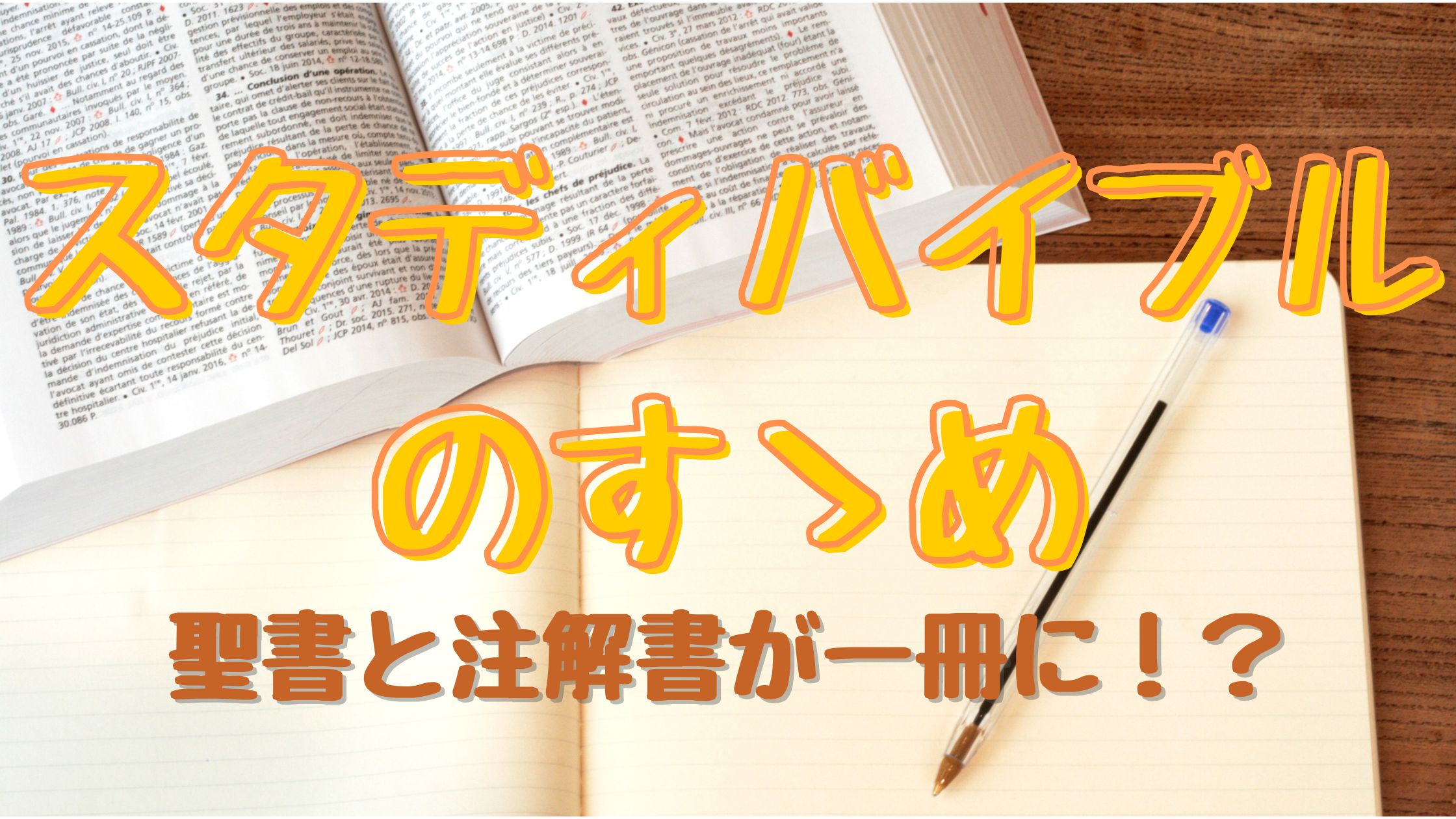ここ数年で、世界的に戦争に対する緊張感が高まっています。もちろん、それは今に始まった話ではなく、人類の歴史を振り返るなら、戦争と無縁な時代など皆無だと言ってもよいでしょう。そのような戦争について目を向ける時、避けて通ることができないことが、キリスト教と戦争の関係です。なぜなら、多くの戦争当事国はキリスト教の影響を色濃く受けている国々だからです。そして時には、聖職者などによって、「聖書」をもとに、その戦争にお墨付きが与えられるということもあったりします。
そのような現実を目の当たりにすると、「聖書」は戦争を支持しているのか、という疑問が生じてきます。実際、聖書と戦争というテーマは古くから議論されてきたものでもあります。クリスチャンではない方にとっては、キリスト教と戦争の関係にうんざりしている方もおられるでしょう。キリスト教が聖書を通してどれだけ素晴らしいことを語っても、キリスト教国と呼ばれる国々が戦争を起こしている現実、それは結局のところ、多くの人の目に「聖書は戦争を支持している」ように映ります。
それでは「聖書」は戦争を支持しているのでしょうか?
この問いは一見するとシンプルなものかもしれませんが、表層的な結論に陥りがちです。つまり、聖書に記されている戦いの記述(主に旧約聖書)を列挙し、聖書は戦争を支持していると言うこともできれば、そのような出来事は史実ではないと切り捨てることもできるということです。
しかし、真剣に聖書に向き合うならば、そのような安直な結論は出ないのではないでしょうか。詰まるところ、「聖書は戦争を支持しているのか」という問いは、聖書の解釈の仕方に大きく左右されてくるということです。
旧約聖書には戦争に関する記述が少なくありませんし、中には神の名の下に残虐な行為がなされている(と読める)箇所もあります。そのような出来事をどのように解釈したらよいのでしょうか。繰り返しになりますが、そのような出来事は史実ではないと無視することもできるでしょう。しかし、それでは聖書のことばに立つ福音主義の立場とは相容れないものとなります。あるいは、旧約時代の神はそうだけど、新約時代の神は違うと答えることもできるでしょうか。しかしそれでは、神の姿が一貫していないことになります。もっと言えば、旧約時代の神よりも新約時代の神の方が優れているという結論にもなりかねません。
それでは、やはり神は戦争を命じ、支持しているという結論になるのでしょうか。神の前に罪深い者たちに対してならば、剣を取ってもよいとなるのでしょうか。聖書にはそのような出来事があるのだから、それが聖書のメッセージだと言えるのでしょうか。
今年刊行された『福音主義神学(54号)』に収録されている「イスラエルによるカナン侵攻物語をどう読むか—カナン人虐殺を命じたのは誰か?」は、福音主義の視点から、そのような問題に切り込んだ論文だと思います。聖書のことばを大切にする福音主義の立場だからこそ、真剣に聖書に記されている出来事と向き合い、そしてそれを現代でどのように生かしていくのか。それは福音主義に立脚する者にとって必要不可欠な姿勢ではないでしょうか。
内容に関しては、ぜひ論文を読んでいただきたいと思います。「論文」と聞くと身構えてしまうかもしれませんが、とても読みやすいというのが率直な感想です。著者の佐藤氏の力量に感服します。
その中で、一箇所だけ引用させていただきたいと思います。
本稿は、古代イスラエルによる残虐行為が存在しなかったということを述べるものでは決してない。むしろ、旧約聖書の言説を、現代の倫理観で評価するのではなく、古代オリエントの文脈の中で再解釈することによって、暴力の性質やその出所について、再定義を試みた。特に、戦争時における神託の出所は、神にあるのではなく、人間側の神学的な意思表明、あるいは信仰告白が反映されている可能性を提示した。つまり、古代イスラエル共同体は、神の名と神託を用いて、自ら戦争を行ったのである。この理解に基づくならば、カナン人虐殺を命じた責任の所在は、人間にあるということになる。
佐藤潤「イスラエルによるカナン侵攻物語をどう読むか—カナン人虐殺を命じたのは誰か?」(福音主義神学54号、2025年)、71-72頁
ここで著者は、古代の文脈に照らし合わせながら、イスラエルの民がしてきたことというのは、まさに神の名によって、神託を用いて、「自ら戦争を行った」ことだと述べています。そのように考えるなら、現代人が聖書を根拠に、戦争を支持することはできないという結論に導かれます。事実、世界の現状を見渡す時に、多くの国々が神の名の下に戦争を行っているのではないでしょうか。それままさに、昔も今も変わらない現実だということです。自分の思いを神の名を用いて正当化している現実は、戦争という大きな問題に限らず、誰であっても身近に潜んでいる問題であるようにも思います。
このような視点で聖書を読むなら、聖書は決して戦争を支持してはいないという結論に至ります。つまり、戦争を引き起こしているのは、昔も今も人間によるものだということです。そして、聖書が記していることは、まさにそのような人間の罪の性質であるということです。
たしかに、このような読み方は、聖書に対する姿勢としてギャップを感じる方もおられるかもしれません。しかし、聖書のことばに立つ福音主義の立場として、決して矛盾するものではないように思われます。聖書のことばと真剣に向き合うからこそ、隠すことのできない人間の残虐性、罪性が示されていることを受け入れることができるのです。そして、そこから、現代に生きる人間は学ぶ必要があると言えるのだと思います。聖書によって戦争を正当化してはならないこと、それは古代から繰り返されてきた人間の過ちであることを学ばなけれならないということです。さもなければ、これから先も、聖書が戦争を支持するものとして、悪用されてしまうことになっていくことは避けられないでしょう。
「聖書と戦争」というテーマは昔から繰り返し議論されてきたテーマです。そして、現代人にとっても決して無視はできないテーマだと言えます。聖書のことばを大切にするクリスチャンであればなおさら、考えなければならないことです。その問題に向き合うことを避けるならば、ますますキリスト教に対する「誤解」が広まっていくことにもなりかねません(それが誤解ではないという人もいるかもしれませんが)。もちろん、先に取り上げた論文の結論を全て受け入れなければならないと言うつもりはありません。しかし、そのような姿勢で、真剣に聖書に向き合う必要があることだけは確かだと思います。
このことを契機に、またとっかかりとして、聖書を通してこの世界の現実、人間の罪性を直視し、聖書から学び、今を生きることができたらと、私は思いました。
おすすめの本