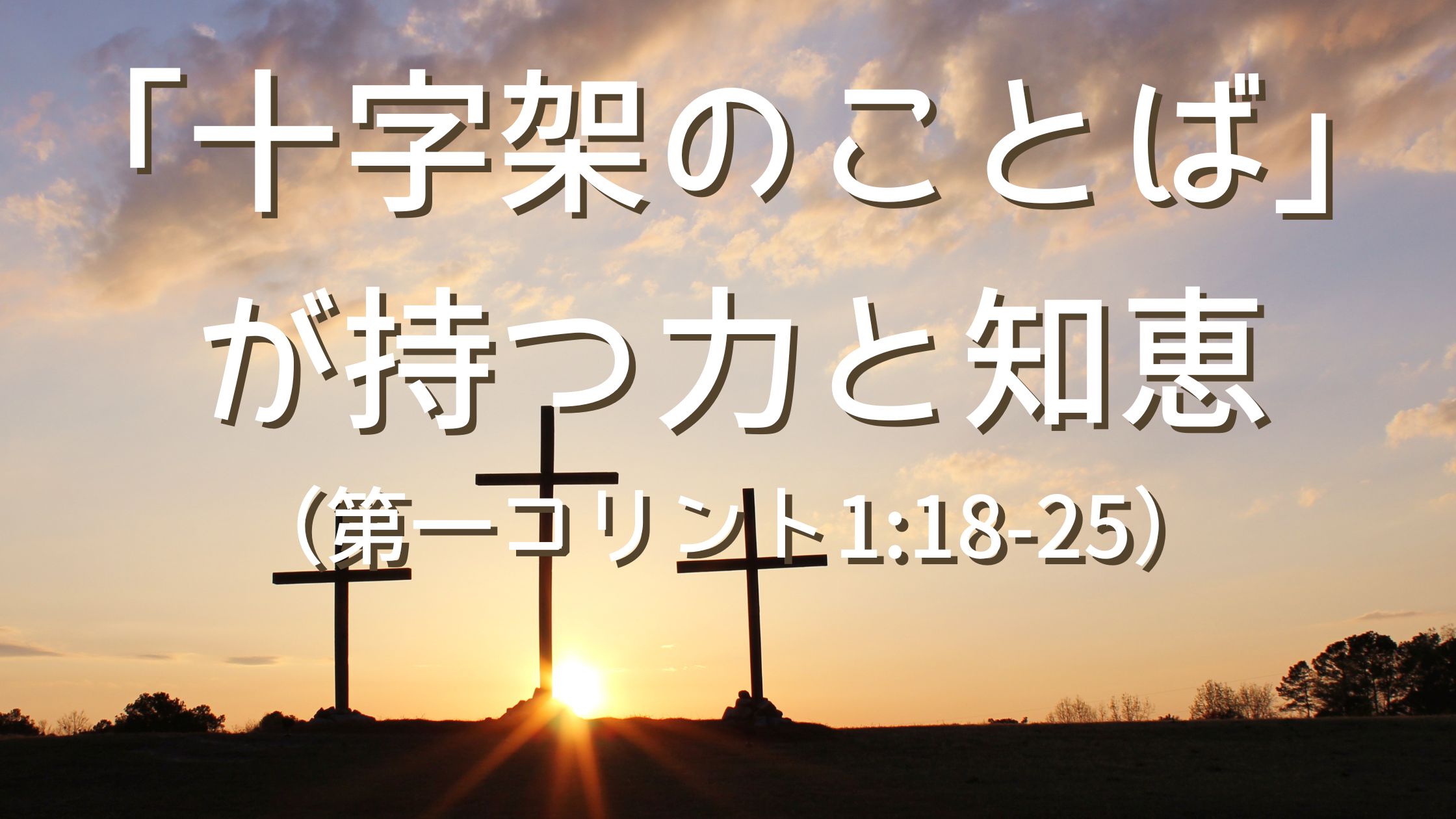聖書における「さばき」とは何を意味しているのでしょうか?一般的にイメージされるものは、死後に受ける裁きであるように思われます。それでは、生きている間は「さばき」とは無縁なのでしょうか。
『ヨハネの福音書』の特徴の一つに、「永遠のいのち」がすでに与えられているものとして語られているという点が挙げられます。たとえば、4章にはサマリア人の女性が登場しますが、彼女はイエスと出会って、渇くことのない水、すなわち永遠のいのちを与えられます。ですがそれは、生きている時点で与えられるという点で、いわゆる死後に与えられる「永遠のいのち」とは異なるものと言えるかもしれません。もちろん、その内実は同じものです。文字通りの永遠のいのちをすでに先取りし、その前味を味わっているということです。
このように「いのち」が生きているうちに与えられているものであるのと同じように、「さばき」も生きているいうちにすでに与えられている、と言うことができます。
16神はそのひとり子を賜わったほどに、この世を愛して下さった。それは御子を信じる者がひとりも滅びないで、永遠の命を得るためである。
17神が御子を世につかわされたのは、世をさばくためではなく、御子によって、この世が救われるためである。
18彼を信じる者は、さばかれない。信じない者は、すでにさばかれている。神のひとり子の名を信じることをしないからである。
19そのさばきというのは、光がこの世にきたのに、人々はそのおこないが悪いために、光よりもやみの方を愛したことである。
20悪を行っている者はみな光を憎む。そして、そのおこないが明るみに出されるのを恐れて、光にこようとはしない。
21しかし、真理を行っている者は光に来る。その人のおこないの、神にあってなされたということが、明らかにされるためである。
ヨハネの福音書3章16-21節(口語訳聖書)
18節に「信じない者は、すでにさばかれている」とありますが、まさにこのことは生きている者でも、すでにさばきを受けていることを示しています。それでは、ここでいうところの「さばき」とは何でしょうか。
まずここには興味深い「逆転」が見られます。それはすなわち、「さばかれない」ということは、光であるイエスの元へ行き、悪事が暴かれるということです。一見すると、さばかれないということは、悪い行いが隠されている状態と思われるかもしれませんが、ここで言われていることは、さばかれない者は、光の元へ来る者であり、その悪が照らされている者です。
その一方で、「さばかれている」者は光であるイエスの方へ来ない者です。19節では端的に「さばき」の定義がなされています。「そのさばきというのは、光がこの世にきたのに、人々はそのおこないが悪いために、光よりもやみの方を愛したことである。 」すなわち、闇の中を歩むこと自体がすでに「さばき」だということです。
このような点を踏まえるなら、さばきが生きているうちに与えられることの意味がわかるのではないでしょうか。すなわち、イエスを信じないということは、光の方へ来ないということであり、罪の中にとどまり、闇の中を歩むということです。それのどこが「さばき」なのかと思われるかもしれませんが、しかし、イエス様という光に照らされることなく闇の中を歩むことは、一言で言えば希望のない人生です。やがては渇き、干からびてしまう人生です。そのことはまさに4章のサマリア人の女性の出来事で表されています。イエスに出会う前の女性は、人間的に渇きを潤すものを求めて、枯渇していたのです。そして、それが生きているうちに受ける「さばき」だということです。
このように考えますと、さばきというのは、神が与えるというものよりも、自分自身で選び取った結果だと言えるのかもしれません。もちろん、さばきが神と無関係であるということではありません。つまり、さばきというのは自分で選び取った結果であると同時に、神がその道を進むことをお認めになったということです。
このことをよく表しているのが、いわゆる「放蕩息子」として知られているたとえ話です(ルカ15:11-32)。弟息子は、父から財産をもらって、遠い地に旅に出ます。その結末は悲惨なものだったわけですが、その道を進むことを認めたのは他ならぬ父親です。息子が一人で生きていくことができるなど、この父親もよくわかっていたのではないでしょうか。たとえ話には記されていませんが、ここで父親が弟息子に考えを改めるように助言したと考えることはおかしなことでしょうか。結局、弟息子は自分で選択した結果のゆえに、自分自身が苦しむことになりました。一方、父親は弟息子が帰ってくるのを今か今かと待ち侘びていました。そして、帰ってきた息子を抱き寄せ、迎え入れたのです。
このたとえ話は、さばきとは何かを示しているように思います。つまり、神から離れて歩むこと自体がさばきであるということです。そしてそれを選択するのは、人間です。また、そのような選択をする人間を神はお認めになるのです。しかし、放蕩息子の父親が息子の帰りをいつも待っているように、神から離れた者が再び帰ることを願っておられます。その上で重要なことは、「さばき」には神に立ち返るための効果があるということです。弟息子が自分で選択した道を歩んだ結果、苦しい思いをしました。しかしそのことがかえって父親の元へ帰る決断へと促しました。同じように、人間が神から離れ、暗闇の中を歩む時、そのことが神へと立ち返るきっかけにもなりうるということです。
このように、生きているうちに与えられる「いのち」と「さばき」は、「永遠のいのち」と「死後のさばき」の前味と言えるかもしれません。人間は今すでに、いのちとさばきを味わうことができ、そしてこれからどうするのか、選択する余地が残されているように思われます。