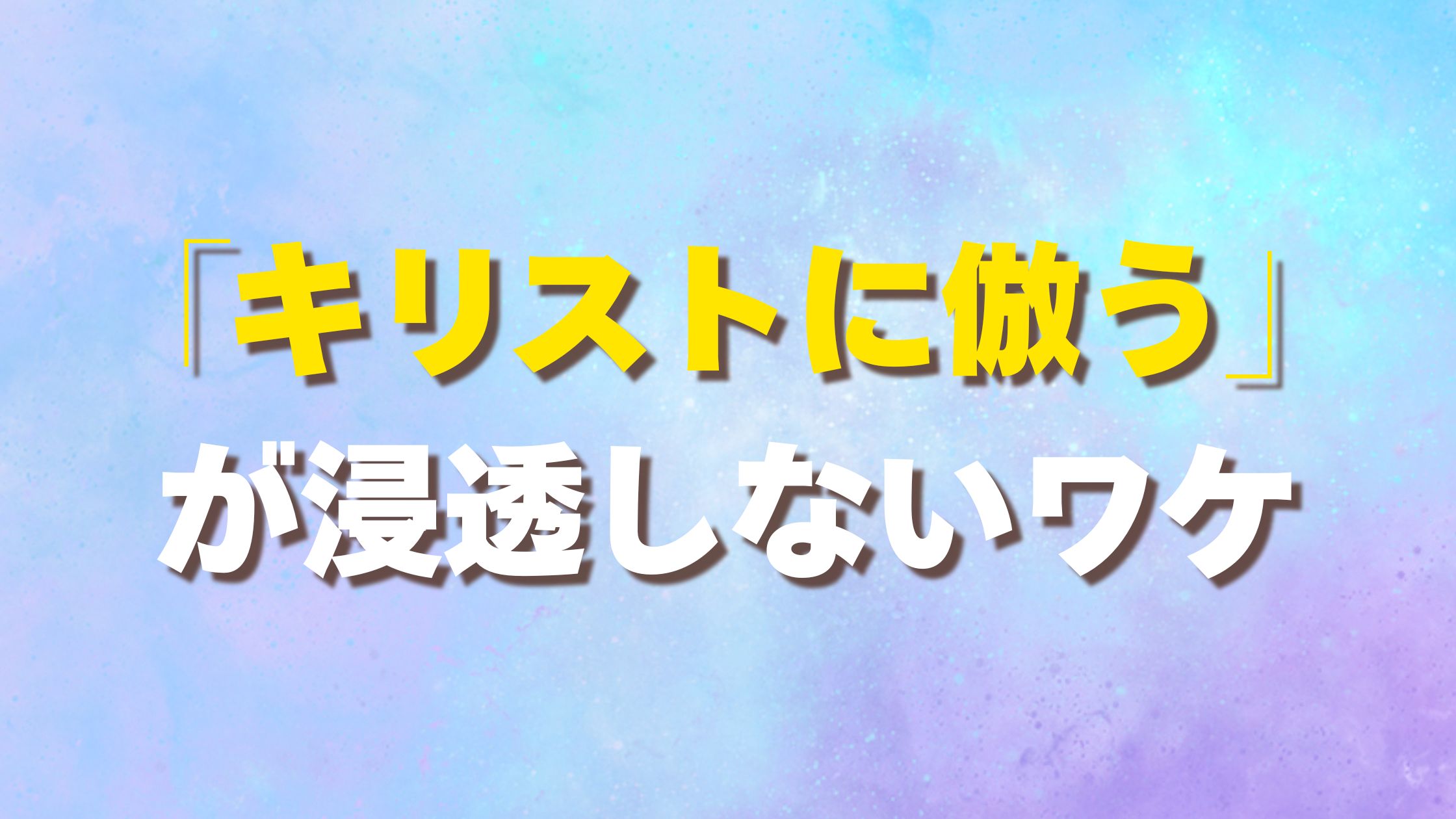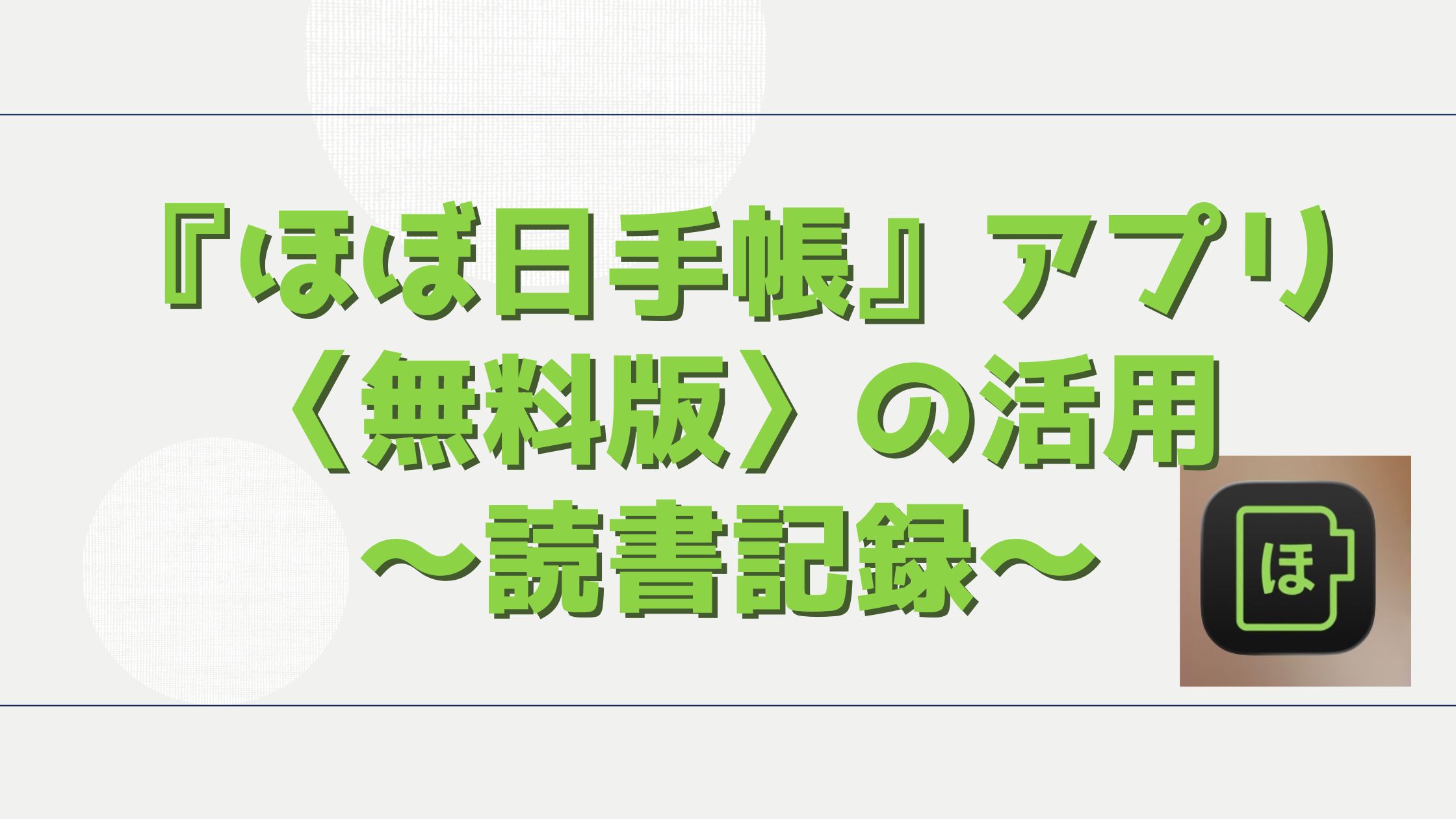ぶどうの木のイメージ
わたしはぶどうの木、あなたがたはその枝である。もし人がわたしにつながっており、またわたしがその人とつながっておれば、その人は実を豊かに結ぶようになる。わたしから離れては、あなたがたは何一つできないからである。
ヨハネの福音書15章5節(口語訳聖書)
上記は広く知られている箇所の一つだと思いますが、キリストとぶどうの木の関係は多くの人にとってお馴染みのものでしょう。クリスチャン一人一人は、キリストというぶどうの木に繋がっている存在として理解することができます。このイメージは、多くの人にとっても親近感が湧くものであるように思われます。
実は、この「ぶどうの木」というイメージは、旧約時代からのものでもあります。旧約聖書において、ぶどうの木として描かれているのはイスラエルの民です。例えば、イザヤ書ではこのように言われています。
1わたしはわが愛する者のために、そのぶどう畑についてのわが愛の歌をうたおう。わが愛する者は土肥えた小山の上に、一つのぶどう畑をもっていた。
2彼はそれを掘りおこし、石を除き、それに良いぶどうを植え、その中に物見やぐらを建て、またその中に酒ぶねを掘り、良いぶどうの結ぶのを待ち望んだ。ところが結んだものは野ぶどうであった。
3それで、エルサレムに住む者とユダの人々よ、どうか、わたしとぶどう畑との間をさばけ。
4わたしが、ぶどう畑になした事のほかに、何かなすべきことがあるか。わたしは良いぶどうの結ぶのを待ち望んだのに、どうして野ぶどうを結んだのか。
5それで、わたしが、ぶどう畑になそうとすることを、あなたがたに告げる。わたしはそのまがきを取り去って、食い荒されるにまかせ、そのかきをとりこわして、踏み荒されるにまかせる。
6わたしはこれを荒して、刈り込むことも、耕すこともせず、おどろと、いばらとを生えさせ、また雲に命じて、その上に雨を降らさない。
7万軍の主のぶどう畑はイスラエルの家であり、主が喜んでそこに植えられた物は、ユダの人々である。主はこれに公平を望まれたのに、見よ、流血。正義を望まれたのに、見よ、叫び。
イザヤ書5章1-7節(口語訳聖書)
神にとって、イスラエルの民はぶどうの木であり、神はその実りを楽しみにしておられました。ぶどうの木が豊かな実を結ぶために、様々な準備をし、良いぶどうが実るのを待ち望んでいました。しかし、実際に実ったのは「野ぶどう」であったと言われています。口語訳では、直訳的に訳されています。ESVでも”wild grapes”となっています。その一方で、共同訳や新改訳では「酸っぱい(酸い)ぶどう」となっています。ヘブライ語では「בָּאֻשׁ」と言いますが、ヘブライ語の辞典HALOTによれば、”sour, unripe berries“とあります。また、この単語が使われている他の箇所を見ると、「悪臭」(ex.詩38:5)となっているものもあります。
これらのことから、この「野ぶどう」が否定的なニュアンスを持っていることは明らかだと思います。それは、本来期待されていたような実りではなかったということです。まさに、イスラエルの民は、神が期待したような歩みをすることができませんでした。神がイスラエルに期待したことは、すなわち「公平」と「正義」です。しかし、現実はと言えば、「流血」と「叫び」であったのです。
このように神が期待した歩み、生き方とは程遠かったイスラエルの民を、旧約聖書記者たちは「酸っぱいぶどう」「野ぶどう」と表現しました。
それでは、その反対に、神によって期待された歩み、生き方である「良いぶどう」とはどのようなものなのでしょうか。ここで注目されるのは、まことのぶどうの木である主イエスです。クリスチャンは、このイエスと繋がっているとき、豊かな実を結ぶぶどうの木(の一部)となれます。
詩篇80篇に見られる「ぶどうの木」
それでは、キリストに繋がる(とどまる)とはどのような意味でしょうか。詩篇80篇との関係から考えてみたいと思います。
なぜ、詩篇80篇なのかと言いますと、ここにも「ぶどうの木」のイメージが見られるからです。
8あなたは、ぶどうの木をエジプトから携え出し、もろもろの国民を追い出して、これを植えられました。
9あなたはこれがために地を開かれたので、深く根ざして、国にはびこりました。
10山々はその影でおおわれ、神の香柏はその枝でおおわれました。
11これはその枝を海にまでのべ、その若枝を大川にまでのべました。
詩篇80篇8-11節(口語訳聖書)
ここでは、イスラエルの民がかつて奴隷とされていたエジプトから、約束の地へ移されたことをぶどうの木の移植になぞらえられています。本来は、その新しい地で、神の祝福を教授し、豊かな生活を送るはずでした。ここで詩人は、実際そのような祝福を受けたと思われるような表現をしていますが、それはあくまでも部分的なものです。イスラエルの歴史において、そのような繁栄は一時的なものであり、そのほとんどは、先のイザヤ書で言われているように、堕落したものだったと言えます。
ではなぜ詩人はこのような繁栄について言及しているのでしょうか。それは12節以降の現実をより鮮やかに描き出すためです。
12あなたは何ゆえ、そのかきをくずして道ゆくすべての人にその実を摘み取らせられるのですか。
13林のいのししはこれを荒し、野のすべての獣はこれを食べます。
14万軍の神よ、再び天から見おろして、このぶどうの木をかえりみてください。
15あなたの右の手の植えられた幹と、みずからのために強くされた枝とをかえりみてください。
16彼らは火をもってこれを焼き、これを切り倒しました。彼らをみ顔のとがめによって滅ぼしてください。
詩篇80篇12-16節(口語訳聖書)
詩人が言い表しているのは、自分たちが今直面している苦難です。それは、本来豊かに実るべきぶどう畑が荒廃しているという現実です。そして、そのような「ぶどうの木」を憐んでくださるようにと、神に嘆願しています。
詩篇80篇で3回繰り返されるフレーズがあります。
「万軍の神、主よ、われらをもとに返し、み顔の光を照してください。そうすればわれらは救をえるでしょう。」(3,7,19節)
詩人は、今陥っている状況が、本来の状況ではないゆえに、「もとに返し(てください)」と訴えます。しかし、よく考えるなら、このような状況を生み出したのは、イスラエルの民自身にあると言えます。神を信頼せずに、人間の力を拠り所とした結果が、このような荒廃でした。
ですが、詩人の姿勢には神を求める真剣さがあります。確かに、その原因は自分たちにありました。しかし、詩人にとって、そのような状況から救い出してくださるのは、神以外にはいないことをわきまえているのです。だからこそ、このような嘆願を3回も繰り返し、神に訴えているのだと言えます。
詩篇80篇には、一貫して苦難の中で神を呼び求める詩人の姿があります。詩人の願いは、「み顔の光を照してください」ということです。詩人にとって、神が共におられることが救いなのです。
キリストにとどまるとは?
そして、このことは、キリストというぶどうの木にとどまるということに通じているように思われます。キリストにとどまるということは、すなわち、苦難がない人生を意味しません。むしろ、キリストにとどまる人生は、キリストに倣う人生であり、それはまさに十字架の道です。命を尽くして、愛を示す生き方です。そして、そのような生き方は決して容易なものではありません。時には、大きな苦難の中を通ることもあるのではないかと思います。しかし、そのような時に、キリストにとどまるということは、苦難の中でさえも、神の拠り頼む生き方です。まさに、詩人がそうであったように、苦難の中で嘆くこともあるでしょう。しかしそれでも、神以外に救いはないということを確信した生き方、それがキリストにとどまるということなのではないでしょうか。
イスラエルはぶどうの木と言われていますが、それが良い実を結ぶことはありませんでした。なぜなら、イスラエルの民の生き方は神の喜ばれるものとはかけ離れていたからです。しかし、そのような中で来られたのが、まことのぶどうの木であるイエス・キリストです。それは言い換えるならば、イスラエルの民には果たすことのできなかった務めを完成しに来られたということでもあります。
イスラエルの民に期待されていたこと、それは「公平」と「正義」です。しかし、現実はと言えば、隣国との戦いでした。まさにイザヤ書で「流血」と「叫び」と言われている通りです。
その一方で、イエス・キリストの歩みは公平と正義に基づくものであったと言えます。社会から除外されている者、虐げられている者たちを顧み、愛を示されたのです。そして、そのようなキリストにとどまるということは、その生き方に倣っていくということでもあります。
そして、現代に生きるクリスチャンにとって、良いぶどうの木となるということは、まことのぶどうの木である、イエス・キリストに繋がるということです。順境の時は賛美し、逆境の時は神に嘆き訴える。そのような、神と共に生きる歩みこそ、イエスの生き方であり、またクリスチャンに期待されている歩みだと言えるのではないでしょうか。