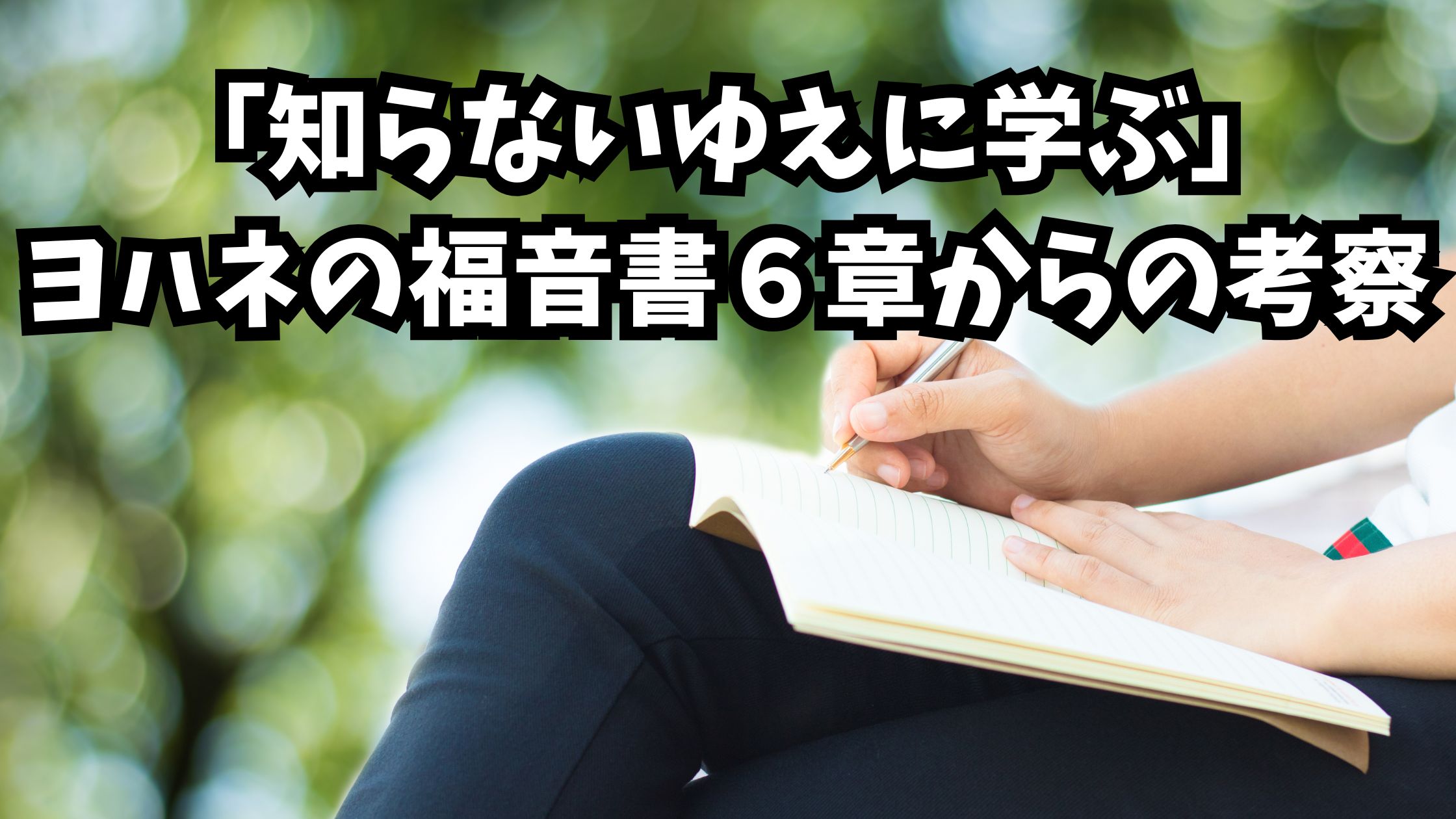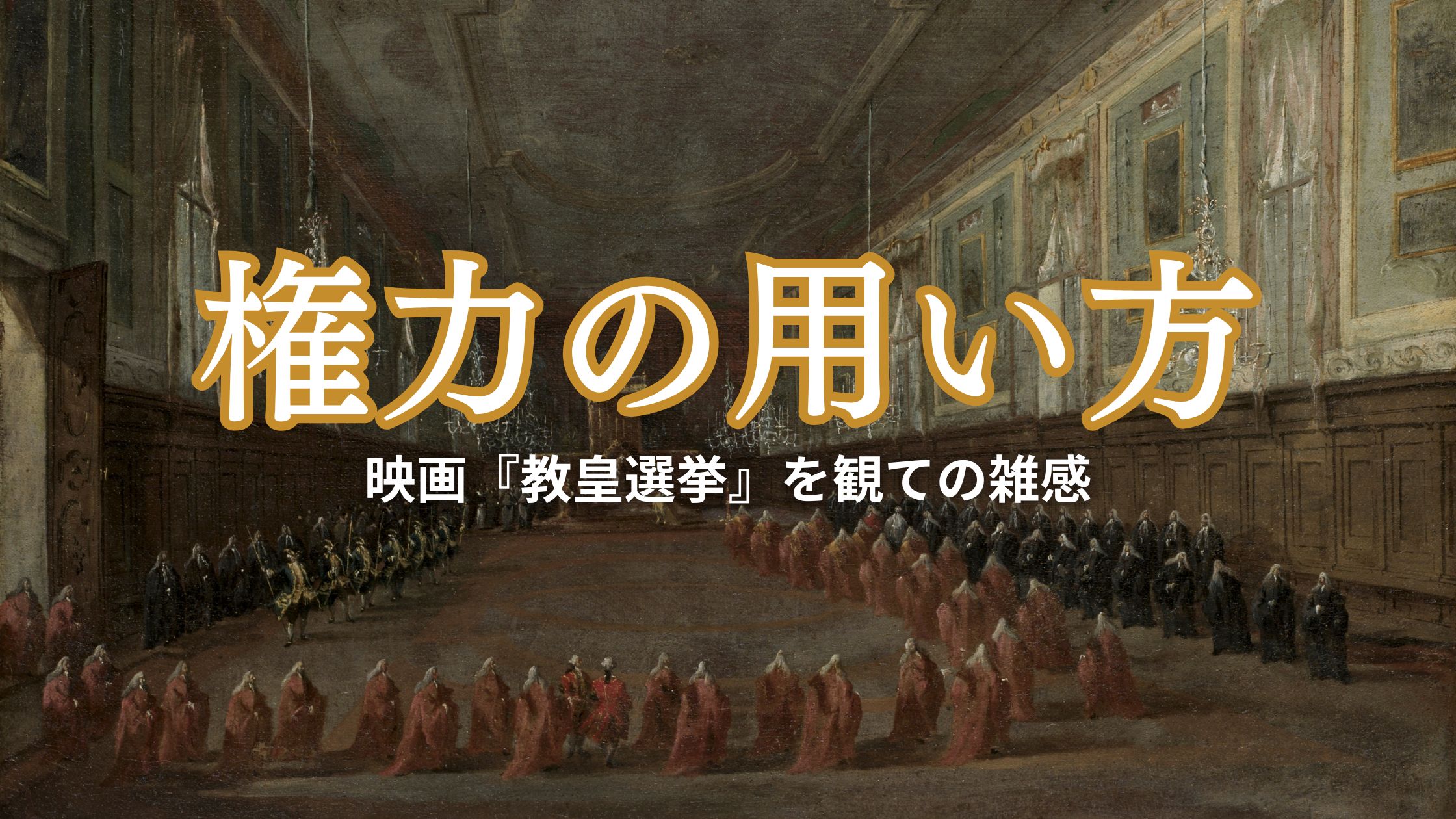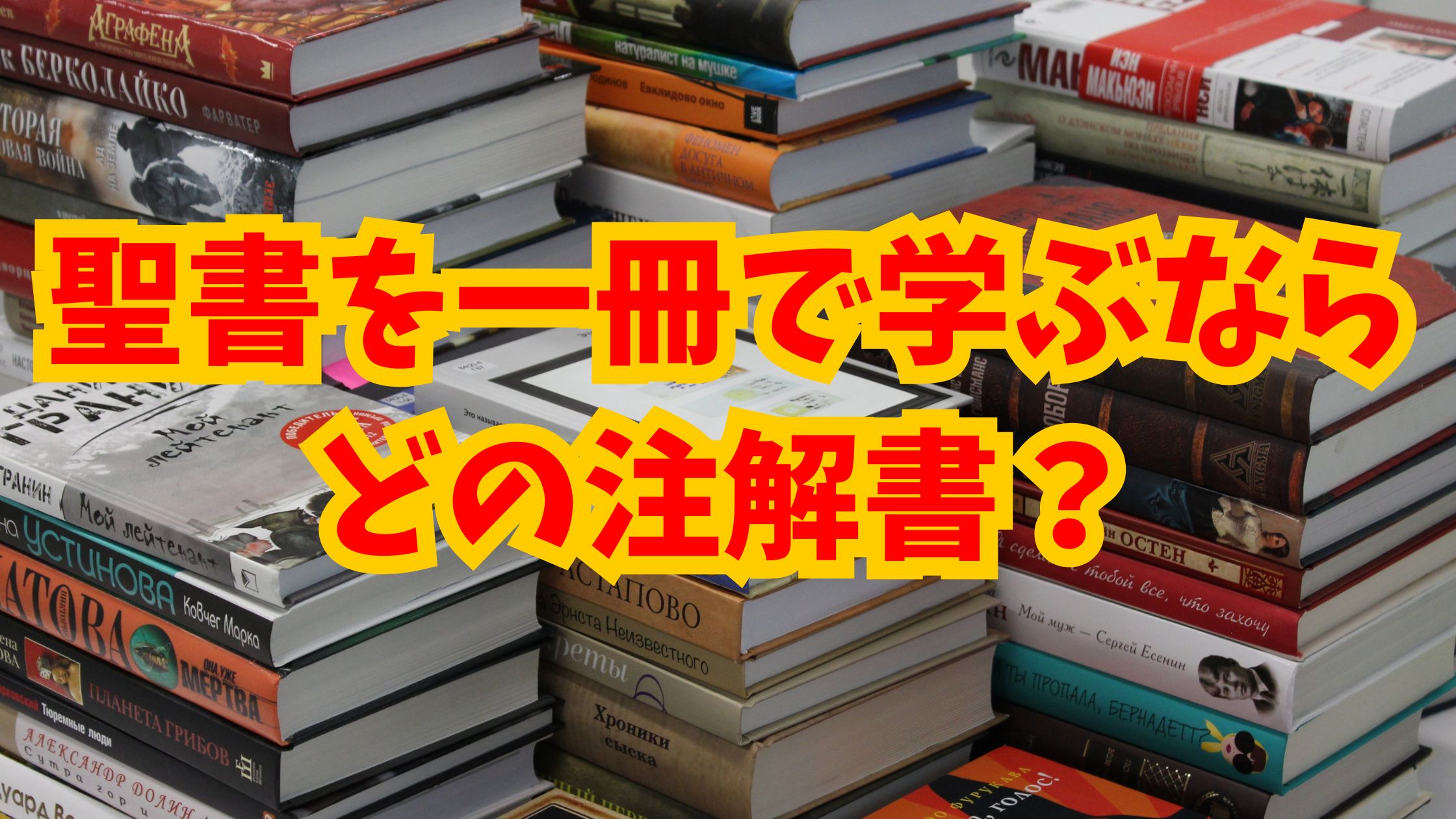ヨハネの福音書6章では、イエス自らご自身のアイデンティティについて証ししています。そのアイデンティティとは、すなわち、イエスが御父から遣わされた神の御子であるということです。しかし、群衆はそのことが理解できませんでした。
この一連のやり取りでは、イエスと群衆(ユダヤ人)との間に、入れ違いがあるように思われます。それは、ユダヤ人たちは神を知っていると思っている一方で、イエスは、御子を通してでなければ神を見ることができないと指摘している点です。
神から出た者のほかに、だれかが父を見たのではない。その者だけが父を見たのである。
ヨハネの福音書6章46節(口語訳聖書)
ここでテーマの一つとなっているのは「知識」です。それは神に関する知識です。
それでは、イエスが天から下ってきた御子であることを理解できない人々は、どのような知識を持っていたのでしょうか。
41ユダヤ人らは、イエスが「わたしは天から下ってきたパンである」と言われたので、イエスについてつぶやき始めた。
42そして言った、「これはヨセフの子イエスではないか。わたしたちはその父母を知っているではないか。わたしは天から下ってきたと、どうして今いうのか」。
ヨハネの福音書6章41-42節(口語訳聖書)
ここには暗黙の対比が見られます。またそれは皮肉であるとも言えるかもしれません。つまり、ユダヤ人たちが知っていることは、イエスの父と母についてであって、父なる神ではなないということです。
自分は知識がある、知っていると思う人は、それ以上学ぶ必要はありません。しかし、知らないと思う人は、さらに学ぼうとします。ここにユダヤ人が陥っていた問題があります。つまり、自分たちはイエスの父と母について知っているので、イエス自身についても知っていると思ってしまっていたのです。それは要するに、ヨセフとマリアの子としてのイエスです。おそらく、幼少期から知っている人も少なくなかったでしょう。そのような人にとっては、いきなりイエスが天から下って来た御子であると言われても、それまでのイメージがあるわけですから、容易に受け入れることはできなかったでしょう。
そのような人々に対して、イエスは旧約聖書から引用してこう言います。
預言者の書に、『彼らはみな神に教えられるであろう』と書いてある。父から聞いて学んだ者は、みなわたしに来るのである。
ヨハネの福音書6章45節(口語訳聖書)
おそらく、これはイザヤ書の一節が念頭に置かれたものだと考えられています(エレミヤ31:33も参照)。
あなたの子らはみな主に教をうけ、あなたの子らは大いに栄える。
イザヤ書54章13節(口語訳聖書)
聖書で一貫して語られることは、神の教えを受けること、神のことばから学ぶことです。しかし、いつの間にかユダヤ人は、神の教えでははなく、自分たちの考えが優先されるようになっていきました。特に、ヨハネ6章では御父の「御心」という言葉が繰り返されますが、人々は神の御心を自分の持っているイメージでしか理解できなかったのです。たとえば、直前ではこのように言われています。
14人々はイエスのなさったこのしるしを見て、「ほんとうに、この人こそ世にきたるべき預言者である」と言った。
15イエスは人々がきて、自分をとらえて王にしようとしていると知って、ただひとり、また山に退かれた。
ヨハネの福音書6章14-15節(口語訳聖書)
自分たちの持っているイメージ、知っていることの範囲、枠内でしか、イエスを理解することができなかったのです。しかし、そのことは要するに「知っていない」ということに他なりません。
知らないことは、一見すると好ましくないことのように思われます。しかし、ここで人々に求められていたことは、知らないことを素直に認めるということだったのではないでしょうか。なぜなら、知らないのであればば、学べばよいからです。そして、事実、イエスから学ぼうとする者をイエスが拒絶することはありません。
父がわたしに与えて下さる者は皆、わたしに来るであろう。そして、わたしに来る者を決して拒みはしない。
ヨハネの福音書6章37節(口語訳聖書)
このような自分が「知らない」ということを認めること、ゆえに「学び」続けることは、信仰者にとって非常に重要な要素であるように思われます。
イザヤ者には「終わりの日」の終末的なビジョンが語られています。
1アモツの子イザヤがユダとエルサレムについて示された言葉。
2終りの日に次のことが起る。主の家の山は、もろもろの山のかしらとして堅く立ち、もろもろの峰よりも高くそびえ、すべて国はこれに流れてき、
3多くの民は来て言う、「さあ、われわれは主の山に登り、ヤコブの神の家へ行こう。彼はその道をわれわれに教えられる、われわれはその道に歩もう」と。律法はシオンから出、主の言葉はエルサレムから出るからである。
4彼はもろもろの国のあいだにさばきを行い、多くの民のために仲裁に立たれる。こうして彼らはそのつるぎを打ちかえて、すきとし、そのやりを打ちかえて、かまとし、国は国にむかって、つるぎをあげず、彼らはもはや戦いのことを学ばない。
イザヤ書2章1-4節(口語訳聖書)
ここで特に注目したいのは、終わりの日に主のもとで、主から教えを受ける、すなわち主から学ぶということです。この「終わりの日」というのは、キリストの再臨によって到来する者であると同時に、キリストの来臨によってすでに開始していると考えることもできるでしょう。ですので、信仰者は部分的には知っていることもありますが、しかし、終わりの日が到来するまでは、完全に知っているわけではありません。このように考えますと、信仰者にとって、学ぶということは、キリストが再び来られる日まで終わることなく続く人生の営みだと言えるのではないでしょうか。
ですので、現代においても、全てを知っていると過信することには、誰もが注意深くある必要があります。教会にしろ、個人にしろ、神から学ぶことは生涯続くのです。特に、昨今、平和が壊れつつある時代にあって、「戦いのことを学ばない」と言われている点は必聴です。人類は、いつの時代も、戦いのことばかり学んでいるからです。
以上のことから、何を知っていて、何を知らないのか、自分自身をよく吟味する姿勢は重要だと言えるのではないでしょうか。最近は、互いの知識を振り翳し、異なる立場の人を否定し、排除しようとする傾向があるように感じられます。しかし、究極的には、誰もが完全な知識には到達していないのであれば、「終わりの日」が来るまでは、吟味し続ける謙虚な姿勢を忘れてはならないのだろうと、思わされています。