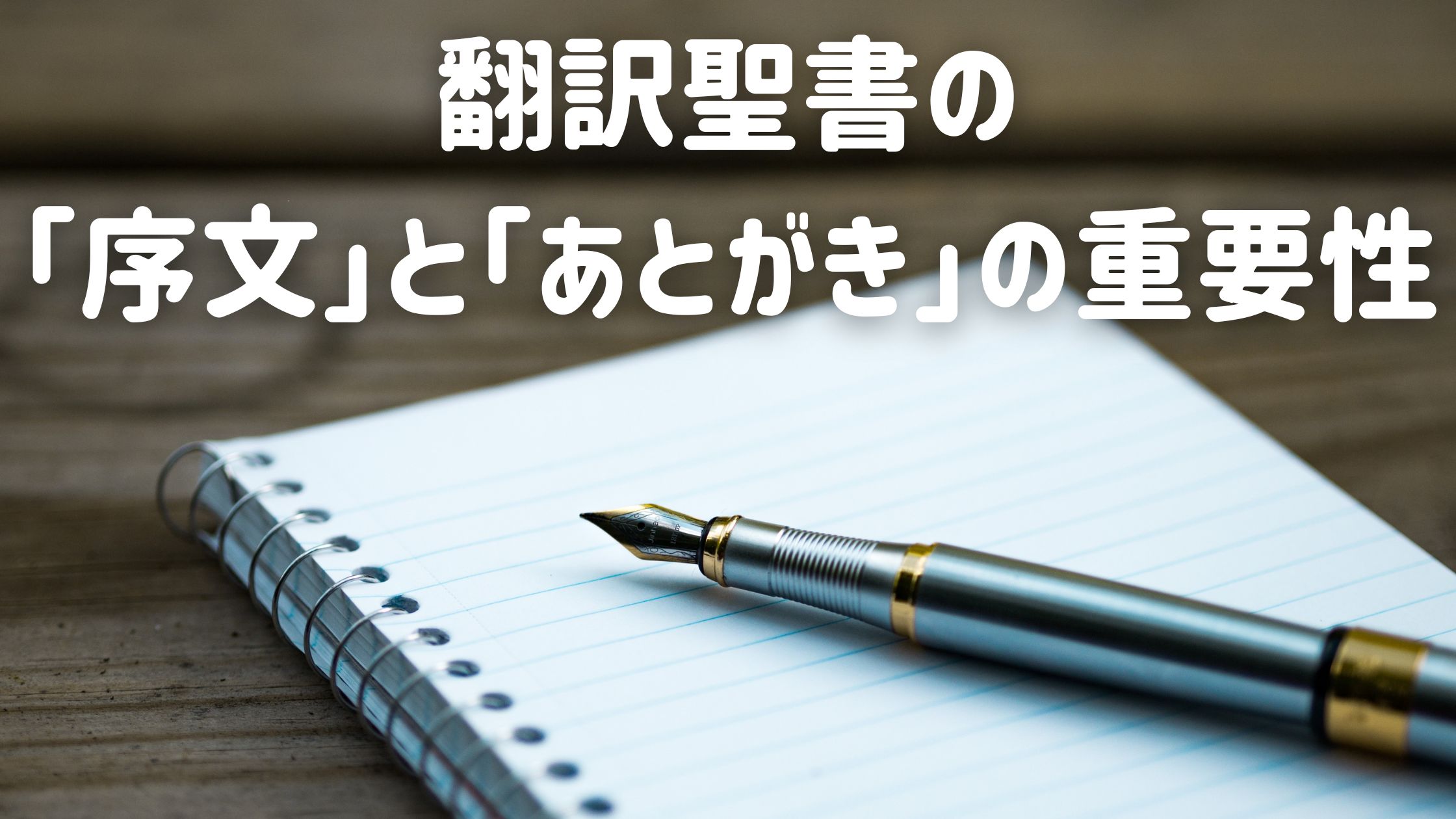意外に思われるかもしれませんが、実は『聖書』には「序文(前書き)」と「あとがき」があります。
「聖書は本文さえ書かれていれば十分ではないか」と言われたらそれまでですが、しかし、翻訳聖書というのは「完璧」なものではありません。翻訳する以上は、翻訳者(あるいは翻訳委員会)の神学が少なからず反映されることになります。したがって、ある程度本文を補う文章が必要になってくるわけです。ですが、これは聖書の読者にとって、非常に有益なものでもあります。なぜかと言いますと、その聖書がどのように翻訳されたのか、その意図やこれまでの翻訳の歴史などを知ることができるからです。
そこで、今現在、最も新しい二つの邦訳聖書を具体例として見てみましょう。
聖書協会共同訳(日本聖書協会、2018年)
これは『新共同訳聖書』の系譜に位置付けられる、最新の邦訳聖書です。『共同訳』はカトリック教会とプロテスタント教会の共同作業によって翻訳されましたが、この『協会共同訳』もそれを基盤にしています。ただし、『聖書 新共同訳』が共同訳聖書実行委員会の責任の下に翻訳されたのに対して、『聖書協会共同訳』は日本聖書協会理事会の決議の下に開始されたと、序文にあります。ですので、同じ系譜ではありますが、その責任者が異なるという点が両者の相違点と言えるでしょう。
そして、この翻訳聖書には、『序文』が収録されています。「あとがき」はありませんが、巻末に収録されている60ページに及ぶ資料が大変役に立ちます(聖書地図や用語解説など)。序文には、これまでの日本聖書協会による翻訳史の概略などが記されているわけですが、中でも注目したいのが「翻訳方針前文」です。
新しい聖書翻訳は、
(1)共同訳事業の延長とし、日本の教会の標準訳聖書となること、またすべてのキリスト教会での使用を目指す。
(2)礼拝で用いることを主要な目的とする。そのため、礼拝での朗読にふさわしい、格調高く美しい日本語訳を目指す。
(3)義務教育を終了した日本語能力を持つ人を対象とする。
(4)言語と文化の変化に対応し、将来にわたって日本語、日本文化の形成に貢献できることを目指す。
(5)この数十年における聖書学、翻訳学などの成果に基づき、原典に忠実な翻訳を目指す。底本として、旧約(BHQ)・新約(UBS第5版)・旧約続編(ゲッティンゲン版)など、最新の校訂本をできる限り使用する。
(6)文学類型の違いを訳出して原点の持つ力強さを伝達する努力はするが、聖書が神の言葉であることをわきまえ、統一性を保つ視点を失わないこととする。固有名詞や重要な神学用語については『新共同訳』のみならず、過去の諸翻訳も参考にして、最も適切な訳語を得るようにつとめる。
(7)その出版に際して、異読、ならびに地理や文化背景などを説明する注、引照聖句、重要語句を解説する巻末解説、小見出し、章節、地図や年表、などの本文以外の部分は、できる限り様々な組み合わせを考え、読者のニーズに応える努力をする。
https://www.bible.or.jp/wp-content/uploads/2021/03/transl_policy.pdf
この「前文」を読むと、『聖書協会共同訳』がどのような方針で翻訳されたのかということがよくわかるのではないでしょうか。またここには、この翻訳聖書の「底本」が示されています。聖書の翻訳と言っても、オリジナルの聖書があるわけではなく、現存するのは写本です。したがって、オリジナルに近い原文の聖書を再現したものを底本として、翻訳はなされます。したがって、翻訳聖書はどの写本を底本とするのかを選択する必要があります。そこで『聖書協会共同訳』が選んだのが『BHQ』と『UBS第5版』等、であるということです。
また、序文において、『聖書協会共同訳』の「最も重要な特徴」は「スコポス理論」であると言われています(P.Ⅳ)。これは翻訳方法を左右するものです。「スコポス」というのは、ギリシア語で「目的」を意味します。つまり、簡単に言えば、翻訳する上で最も大事なことは、その「目的」を果たすということです。その目的とは要するに、著者の意図が読者にとって意味がわかるように翻訳されるということです。たとえば、子ども向けの聖書翻訳を「スコポス理論」で行う場合、対象の子どもにわかりやすいように平易な言葉遣いが採用されるということがあるということです。『聖書協会共同訳」の掲げるスコポスは「礼拝での朗読」と言われていますので、そのことを前提に翻訳がなされていったということでしょう。「スコポス理論」の詳細については、こちらをご参照ください(聖書翻訳における 「スコポス理論」の意義と適用)。
新改訳聖書2017(新日本聖書刊行会、2017年)
『新改訳聖書2017』の翻訳理念については、公式HPにてこのようにあります。
翻訳の理念
https://www.seisho.or.jp/aboutus/philosophy-of-translation/
- 聖書信仰
聖書を誤りなき神のことばと告白する、聖書信仰の立場に立つ。- 委員会訳
特定の神学的立場を反映する訳出を避け、言語的な妥当性を尊重する委員会訳である。- 原典に忠実
ヘブル語及びギリシア語本文への安易な修正を避け、原典に忠実な翻訳をする。- 文学類型
行き過ぎた意訳や敷衍(ふえん)訳ではなく、それぞれの文学類型(歴史、法律、預言、詩歌、ことわざ、書簡等)に相応しいものとする。- 時代に適応
その時代の日本語に相応しい訳出を目指す。- 今後も改訂
聖書研究の進展や日本語の変化に伴う必要な改訂を行う。
新改訳は、いわゆる「福音派」と呼ばれるグループで広く用いられている聖書ですが、この理念に示されているように、「特定の神学的立場を反映する訳出を避け」た翻訳が心掛けられています。現状は、日本では『共同訳聖書』の方が普及率が高いですが、『新改訳』が広まることで、より聖書の「翻訳」に関心が向かうのではないかと思います。『新改訳2017』の詳しい特徴については、公式HPをご覧ください。「新改訳2017特徴」
『新改訳2017』には「序文」がない代わりに「あとがき」があります。翻訳理念にもありますように、これは「委員会訳」であり、個人訳とは異なり、委員会で検討が重ねられた上で訳出されます。ですので、その背景には様々な個人的な理解、翻訳案がありつつも、委員会としての訳を決定していったプロセスが推察されるわけですが、あとがきには「翻訳編集に携わった者の一致した願いは、原語にあくまでも忠実であり、読みやすく、しかも聖書としての品位を失わない訳文を得ることであった」と記されています。
また、新改訳2017も共同訳と同様に、底本として『BHS(ビブリア・ヘブライカ・第4版)』『BHQ(ビブリア・ヘブライカ・第5版)』『ネストレ・アーラントの校訂本第28版』『『聖書協会世界連盟(UBS)第5版』を挙げています。つまり、底本が複数あるということは、それぞれ異なる文章がある際に、どの訳が相応しいかを取捨選択する必要があるということです。その翻訳作業の一端がこの記事にはありますのでご参照ください。「聖書 新改訳2017どう新しくなるのか?<7>校訂本文の変化」
特に『新改訳』の特徴として特筆すべきは、「平仮名」の活用にあると思われます。一見すると、漢字ではなくなぜ平仮名で?と思われる訳出がありますが、実はそこに、日本語では表しきれないものを暗示する意図があるのです。
原語において異なる語は、日本語でできるだけ訳し分けることを原則としているが、最終的には、文脈によって判断をしている。神あるいはキリストが話し手である場合は、平仮名の「わたし」を用いている。また、訳語において、日本語での通常の意味と異なる意味合いを出したいときなどに、あえて平仮名を用いている場合がある。たとえば、「さばき」「いのち」「みこころ」等である。
「あとがき」より 『聖書 新改訳2017(新日本聖書刊行会)』
翻訳聖書をより深く理解するための「序文」と「あとがき」
このように一口に聖書と言っても、それが翻訳されたものである限り、翻訳者の神学や意図が含まれています。また、翻訳にも限界があります。しかし、だからこそ、聖書の読者は、翻訳の理念や経緯を知ることで、より深く聖書を理解することができるようになります。そして、そのヒントや手がかりが記されているのが「序文」と「あとがき」なのです。
母国語で聖書が読めるということは大きな特権です。そしてそこには、翻訳者たちの想像を絶する労力がかけられていることを思わされます。そのような思いを汲み取りながら、翻訳聖書に親しんでいくことができたらよいのではないでしょうか。