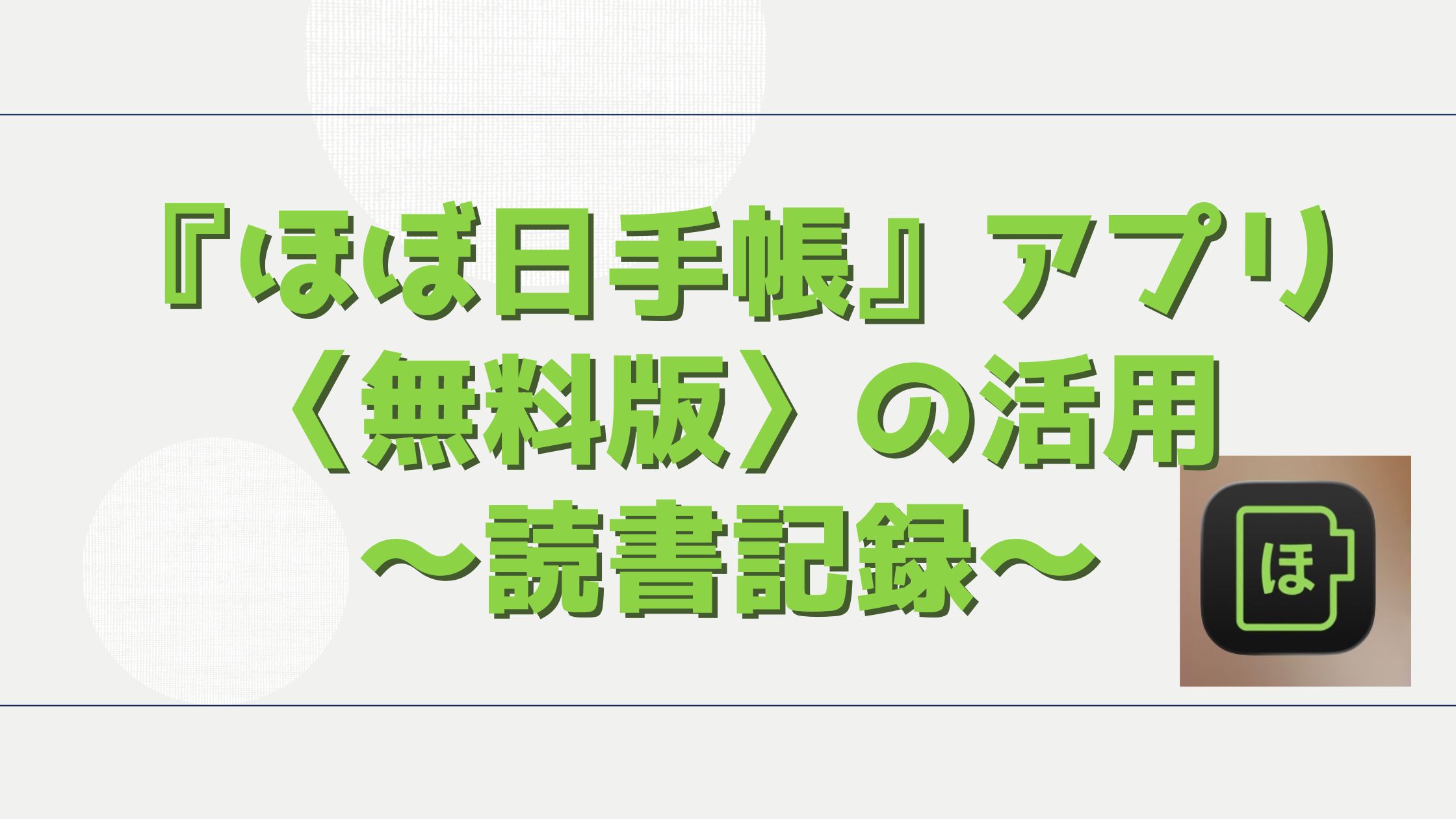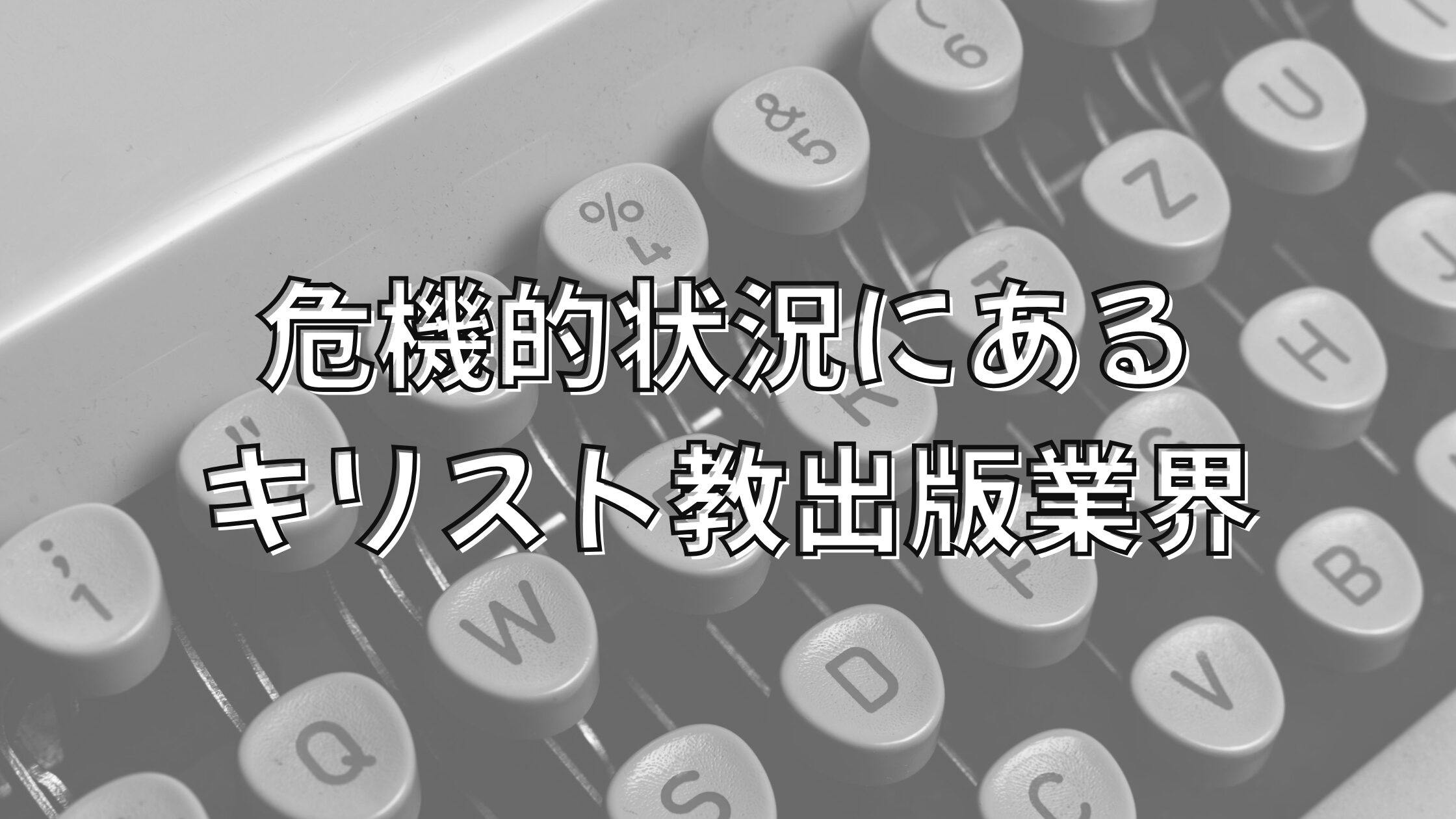教会音楽の父
今年は、「教会音楽の父」と呼ばれる、ジョヴァンニ・ピエルルイジ・ダ・パレストリーナ(Giovanni Pierluigi da Palestrina)の生誕500年です。彼の音楽は、後代の教会音楽に多大な影響を与えました。そのような年であるため、今年の全日本合唱コンクールでも、パレストリーナの楽曲が、混声・男声・女声それぞれにおいて、課題曲として選曲されています(Dies sanctificatus, Ascendens Christus in altum, Sub tuum praesidium)。
今年もクリスマスが近づいてきましたので、今回はクリスマスの讃歌として知られている「Dies sanctificatus」について考察してみました。
Dies sanctificatus(聖なる日)
“Dies sanctificatus”は、ラテン語で「聖なる日」という意味です。世界中の合唱団で広く親しまれているクリスマスの讃歌です。
| Dies sanctificatus illuxit nobis | 聖とされた日がわれわれに光りはじめた |
| Venite gentes et adorate dominum | もろもろの民よ来て、主をほめたたえよ |
| Quia hodie descendit lux magna in terris. | 今日地上に大いなる光がくだったから |
| Haec dies quam fecit dominus | これは主が作りたもうた日 |
| Exultemus et laetemur in ea. | われわれはこの日に、よろこびおどろう |
この歌詞の背景には、いくつかの聖書箇所があると考えられます。
イザヤ9章2節
イザヤ9章2節(口語訳聖書)暗やみの中に歩んでいた民は大いなる光を見た。暗黒の地に住んでいた人々の上に光が照った。
一応、ラテン語訳も。
populus qui ambulabat in tenebris vidit lucem magnam habitantibus in regione umbrae mortis lux orta est eis
Isaias9:2(Vulgate)
ラテン語で「光」は「lux(単数・主格)」と言います。この箇所では「lucem(単数・対格)」となっています。Dies sanctificatusの歌詞と、イザヤ9章2節を読み比べてみても、非常に似ているということは、よく分かると思います。
そして、この続きには、かの有名な、クリスマスによく開かれる箇所があります。
6ひとりのみどりごがわれわれのために生れた、
ひとりの男の子がわれわれに与えられた。
まつりごとはその肩にあり、
その名は、「霊妙なる議士、大能の神、
とこしえの父、平和の君」ととなえられる。
7そのまつりごとと平和とは、増し加わって限りなく、
ダビデの位に座して、その国を治め、
今より後、とこしえに公平と正義とをもって
これを立て、これを保たれる。
万軍の主の熱心がこれをなされるのである。
イザヤ9章6-7節(口語訳聖書)
9章2節は、新約聖書においても、バプテスマのヨハネの父、ザカリヤの預言の中で引用されています。
78 これはわたしたちの神のあわれみ深い
みこころによる。
また、そのあわれみによって、日の光が上から
わたしたちに臨み、
79 暗黒と死の陰とに住む者を照し、
わたしたちの足を平和の道へ導くであろう」。
ルカの福音書1章78-79節(口語訳聖書)
一応、ラテン語訳も。
78 per viscera misericordiae Dei nostri in quibus visitavit nos oriens ex alto
79 inluminare his qui in tenebris et in umbra mortis sedent ad dirigendos pedes nostros in viam pacis
Lucam1:78-79(Vulgate)
ちなみに、ここで「inluminare」とありますが、これはもはやお馴染みの「イルミネーション」を想起させる言葉ですね。
口語訳では、「日の光」(ルカ1:78)と訳されていますが、原語のギリシア語では「ἀνατολή」という言葉が使われています。これは新約聖書の中で10回(マルコ16:8を含めるなら11回)使われていますが、基本的には「東」と訳される名詞です。ですが、BDAGで「3.a change from darkness to light in the early morning, the dawn」とあるように、東から昇る太陽の光と解釈することもできるでしょう。実際、新改訳2017や聖書協会共同訳では「曙の光」と訳されています。
したがって、ここで暗示されているのは、暗闇に覆われたこの世界を東の空から昇る太陽のように照らす存在です。それが、ザカリヤに言わせてみれば、これから生まれようとしている救い主であるということです。
イザヤ60章2-3節
2見よ、暗きは地をおおい、
やみはもろもろの民をおおう。
しかし、あなたの上には主が朝日のごとくのぼられ、
主の栄光があなたの上にあらわれる。
3もろもろの国は、あなたの光に来、
もろもろの王は、のぼるあなたの輝きに来る。
イザヤ60章2-3節(口語訳聖書)
ラテン語訳も。
2 quia ecce tenebrae operient terram et caligo populos super te autem orietur Dominus et gloria eius in te videbitur
3 et ambulabunt gentes in lumine tuo et reges in splendore ortus tui
Isaias60:2-3(Vulgate)
ここでは「もろもろの国」という単語が見られます。ラテン語では「gentes(複数)」です。世界を照らす曙の光の元に、もろもろの国、民が招かれている、そのような情景が連想されます。
詩篇118篇24節
これは少々無理矢理かもしれませんが…
24これは主が設けられた日であって、
われらはこの日に喜び楽しむであろう。
詩篇118篇24節(口語訳聖書)
ラテン語は割愛。
この箇所だけでも、Dies sanctificatusと重なる部分がありますが、この続きにはさらに両者の繋がりを裏付ける言葉が出てきます。
27 主は神であって、われらを照された。
詩篇118篇27節a(口語訳聖書)
口語訳聖書では「照らされた」と訳されている言葉は、原語のヘブライ語では「אור」と言いますが、やはり「光」に通じる言葉だと言えます。なぜ詩人は「この日」を喜ぶのか、といえば、それは主が光によって照らしてくださったからです。
「光」というテーマ
ここまでみてきましたように、上記の箇所に、一貫して「光」というテーマが共通していることは明白です。よりクリスマスの讃歌として解釈するなら、「聖なる日」というのは、まさにイエス・キリストが「光」として来られたことを喜ぶ歌だと言えるでしょう。
その光は、曙の光のように、東の空から昇り、世界を照らします。そして、その光の下に出てくるようにと、諸国の民は招かれています。
それでは、なぜその光が喜びなのか。それは、イザヤ9:6-7やルカ1:79で言われているように、世界に「平和」をもたらす光だからです。人々が長い間待ち望んでいたもの、それは平和をもたらす光です。闇夜を歩いているような絶望の中にある人々を照らす光こそ、この世にくだられたイエス・キリストです。
このような歌詞の意味を考えるなら、Dies sanctificatusが奏でるメロディーから、より鮮やかに「光」のイメージが伝わってくるように思います。朝日が昇るように静かに、そして、ゆっくりと始まります。しかし、次第にその光は空高く昇り、世界全体を照らします。そして、その光の下に来るようにと諸々の民を招きます。曲調もリズミカルになっていきます。最後は、美しい旋律をもって、この曲は終わります。それはまるで、この世界に与えられる平和を象徴しているかのようです。
ジョヴァンニ・ピエルルイジ・ダ・パレストリーナ(1525頃-1594)
最後に、パレストリーナが教会音楽の父と呼ばれる所以について、簡単に触れておきます。
パレストリーナを理解する上で重要なのは、その時代です。彼の年代からも分かるように、当時は「宗教改革」真っ盛りです。1517年にドイツでマルティン・ルターに端を発する改革は、次第にヨーロッパ全土へと広がっていきます。
そして、その頃、カトリック教会内部でも、改革が行われていました。それが俗に「対抗宗教改革」とも呼ばれる「トリエント公会議」(1545-1563)です。この会議の詳細については、今回は触れませんが、簡単に言えば、実際に教会が改革(改善)されなければならない点もあったので、それについての話し合いがなされたということです。
そして、その中で出された議題の一つが、礼拝で歌われる音楽の問題です。当時の音楽には「音楽があまりにも複雑で、信徒が歌詞(テキスト)を理解できない」という問題がありました。これは、他の問題にも通じていると言えるかもしれません。プロテスタント教会が、ステンドグラスなどといった極度に華美なものを廃止していった中で、カトリック教会にはそのような問題がいくつかの分野でみられていたようです。そして、その一つが、音楽です。過度に技巧的な多声音楽(ポリフォニー)によって、歌詞が聞き取れず、理解できない、ゆえに信仰の妨げになっているという現実的な問題を生み出していたのです。
そこで活躍したのがパレストリーナです。彼の音楽の特徴は、まず歌詞が聞き取れること、また、不協和音が少なく、美しい響きであることなどが挙げられます。これにより、彼の音楽は、ポリフォニーは礼拝にふさわしくないという批判を覆し、教会音楽における理想的なモデルとなりました。まさに、信仰と芸術を両立させる音楽だったと言えるでしょう。
そんなパレストリーナについては、次のように評されています。
パレストリーナが残したミサ曲は合わせて百四曲、モテットは賛歌なども含めて三百七十七曲に達する。それはまさに純粋対位法による教会声楽曲の極致を極めた金字塔と呼んで良い業績であった。日本でも良く親しまれている四声のモテット《鹿が泉を慕うように Sicut cervus desiderat》や《バビロンの流れのほとりに Super flumina Babylonis》を聴いても判るように、彼の作品においては旋律の流れも、ハーモニーの動きも、すべてが自然で、磨き上げた珠玉のように完成されている。特に緻密な声部の絡み合い、巧みな模倣の手法の用法、完全に均整のとれた作品全体の構成は見事と言うほかはない。また彼の晩年の作品には、ポリフォニーによりながらもはっきりと歌詞が聞き取れるようよな努力が見られ、彼自身トリエント公会議における教会音楽の理想的な作品を目指していたことがうかがえる。以後ローマ・カトリック教会が彼の作品を礼拝に最もふさわしいと見なし、後の世代の模範としたことも十分納得できるわけである。
金澤正剛『キリスト教音楽の歴史―初代教会からJ.S.バッハまで―』(日本キリスト教団出版局、2005年)、219頁
特に、後半のところからも分かりますように、まさにパレストリーナの功績は、トリエント公会議での議論を受けて、礼拝にふさわしい教会音楽のモデルを示したことにあると言えるでしょう。とりわけ、「ポリフォニーによりながらもはっきりと歌詞が聞き取れるようよな努力が見られ」とあるように、その音楽は、美しい芸術性を保ちながらも、同時に歌詞が聞き取れるという信徒の必要に答えるものでした。そのようなこともあって、後代では教会音楽の父と呼ばれるようになっていったようです。
合唱コンクールの採点方法とは?
これは全くの余談ですが、今年の合唱コンクールにパレストリーナが生誕500年ということで選ばれたことは、冒頭でも紹介した通りです。私は、関係者ではないので、全くわからないのですが、やはりパレストリーナという人物は、教会内外でも知られている、むしろ合唱などの音楽業界ではより知られているのではないかと推察しています。
であるならば、パレストリーナの功績もそのような方々にとってはよく知られていることなのかもしれません。そのように考えた時に、合唱コンクールの採点基準には、パレストリーナのポリシーが反映されているのかが気になるところです。つまり、まず歌詞が明瞭で聞き取りやすいこと、しかし同時に、そこには美しい旋律、ポリフォニーがあること。これらが上手に表現されていれば、採点は高くなるのでしょうか。
しかし、このような技術的なことは結局のところ、どの曲にも通じている部分でもありますので、パレストリーナの曲に限ったことではないようにも思います。
それでも、強いて言うならば、パレストリーナがこの詩に込めた思いを、聖書全体から汲み取ることができ、それを曲に乗せて歌うことができれば、より豊かな表現になるのではないかと思います。
今年もクリスマスが近づいてきましたが、このような古き良き讃美歌を深く味わいながら、世界を照らす曙の光を待ち望む季節を過ごすのもよいのではないでしょうか。
参考文献:金澤正剛『キリスト教音楽の歴史―初代教会からJ.S.バッハまで―』(日本キリスト教団出版局、2005年)