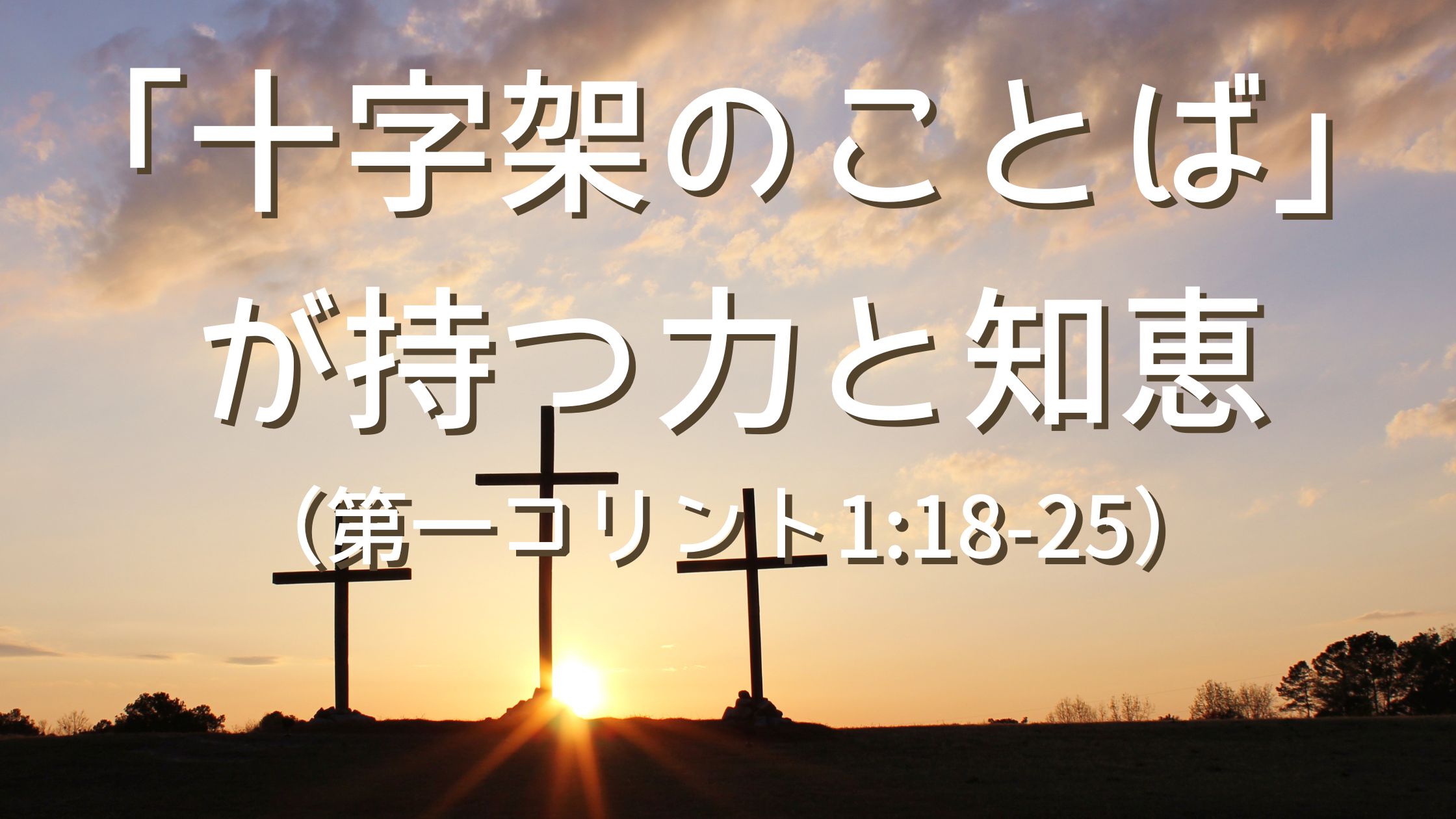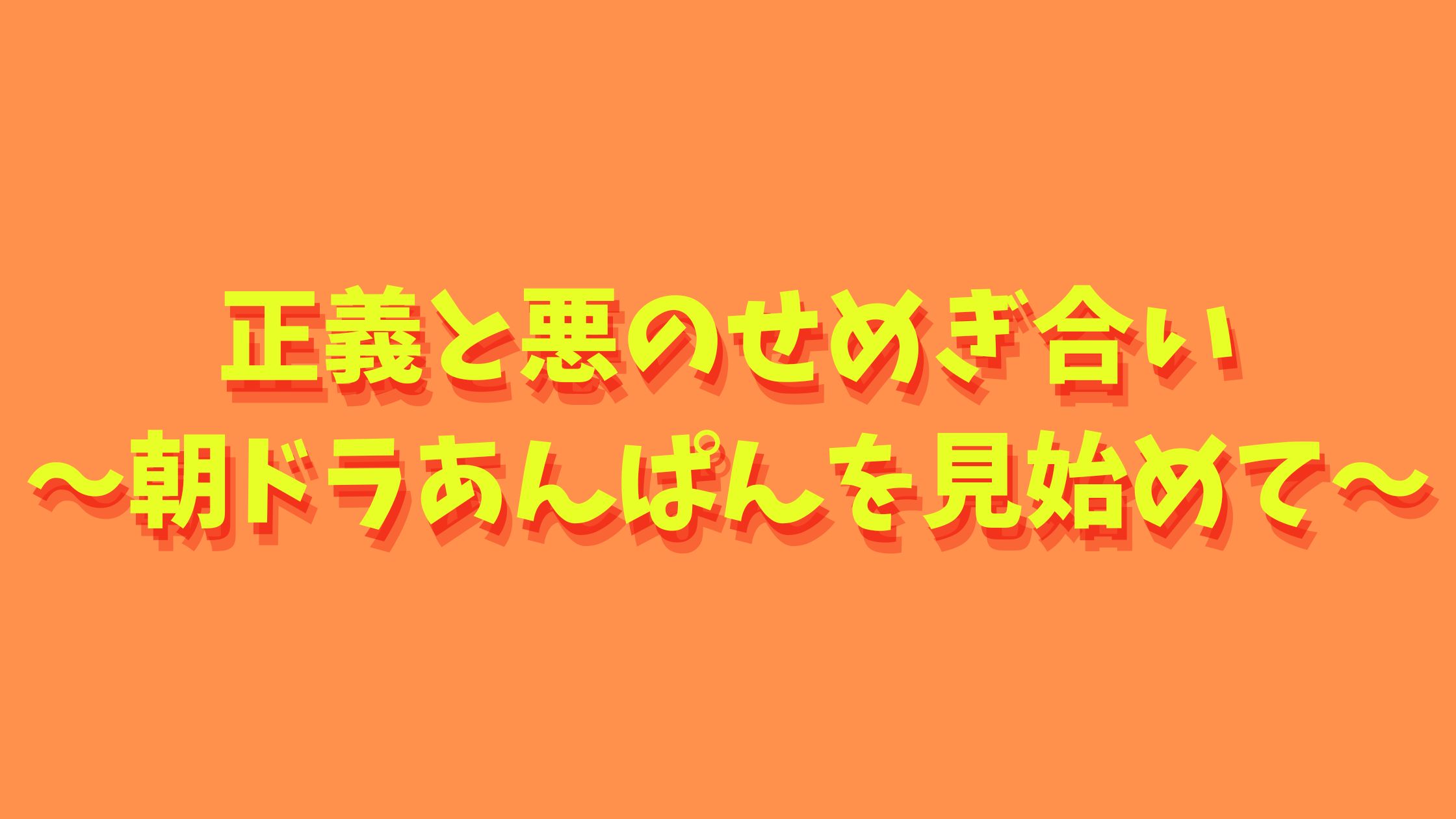受難週の金曜日に、改めて十字架の意味について考えてみたいと思います。
使徒パウロはこのように述べています。
十字架の言は、滅び行く者には愚かであるが、救にあずかるわたしたちには、神の力である。
コリント人への第一の手紙1章18節(口語訳聖書)
ユダヤ人はしるしを請い、ギリシヤ人は知恵を求める。
コリント人への第一の手紙1章22節(口語訳聖書)
十字架のことばは「愚か」とはどのような意味でしょうか。この手紙が書かれた当時の背景に目を向けると、二つの意味で十字架のことばが愚かであったことが分かります。
ユダヤ人にとって
「十字架のことば」はユダヤ人にとって愚かであり、つまずきでした。パウロが「ユダヤ人はしるしを請い」と述べているように、ユダヤ人にとって「しるし」は重要です。そして、ここで言われている「しるし」というのは、聖書(いわゆる、旧約聖書)に基づいているものでなければなりません。それでは、聖書は「十字架」についてどのように語っているでしょうか。旧約聖書には「十字架」という単語は言及されていませんが、申命記にはこのような一節があります。
木にかけられた者は神にのろわれた者だからである。
申命記21章23節(口語訳聖書)
つまり、この一節に照らし合わせるならば、十字架にかけられた者は神にのろわれた者と認識されることになります。それゆえに、のろわれた者が「キリスト」であるなどとは、ユダヤ人にとっては到底受け入れ難いことでした。多くのユダヤ人が待ち望んでいた「キリスト(すなわち、メシア)」とは、十字架で殺されるような弱々しい者ではなく、ダビデ王のような軍事的な力強さを伴ったリーダー的な人物がイメージされていたのでしょう。それに比べて、十字架で殺されたイエスはあまりにも正反対のイメージと言わざるを得ません。だからこそ、ユダヤ人にとって、十字架につけられたキリストを述べ伝える「十字架のことば」は愚かだったのです。
ギリシア人にとって
それでは、聖書には親しくないギリシア人にとっては、どのように十字架のことばは愚かだったのでしょうか。そのことを理解するためには、コリント社会に目を向ける必要があります。
当時の社会的な価値観として定着していたこととして挙げられるのは「評判」です。いかに人からの評判を得て、社会的なステータスを上げるのか。このことが当時の価値基準でした。特に、よく言われることとして、ギリシア社会で重んじられていたのは「名誉と恥」という文化があります。それは、名誉を受けることで地位を上げることが美徳とされる社会です。
そのような社会であったことを裏付けるかのように26節以降には、「知恵のある者」「権力のある者」「身分の高い者」などの社会的なステータスの高い人たちについて、またその反対として「愚かな者」「弱い者」「この世で身分の低い者」「軽んじられている者」「無きに等しい者」などの社会的なステータスの低い者たちについて言及されています。まさに、当時の価値観では、名誉こそが社会的地位を決定づけるものとして認識されていたということが伺えます。
したがって、このような社会的な価値観の中で、「十字架」というのはまさに「名誉」とは対極に位置付けられるものだと言えます。それは、恥の極みであるとさえ言えます。そのことは、十字架刑という処刑方法の性質にも合致するものです。当時の処刑方法は、様々なものがありました。中には、十字架刑よりも残酷だと思われるようなものもあります(例えば、2頭の動物に処刑人を縛り付けて引き裂かせるなど)。しかし、十字架刑とはそれらの処刑方法とは一線を画しています。それは、恥を与えるという点において、他の処刑方法とは比べ物にならないということです。十字架刑の特徴は、まず人目の付くところで行われることです(イエスの場合はゴルゴタの丘)。通りすがりの人たちから、罵倒され、晒し者にされます。また、死ぬまでに時間がかかるということも十字架刑の重要な要素です。その分、人々から屈辱を受け続けることになります。このように十字架刑の効果は、単に残酷な処刑方法ということではなくて、当時の社会で最も忌み嫌われていた「恥」を与えるという点において、他の処刑方法とは比較にならないほどのものであったと言うことができるかと思います。
それゆえに、知恵を求めるギリシア人にとって、つまり社会的なステータスが全てだと考えているギリシア人にとっては、十字架のことばは「愚か」だと言えるのです。
召された者にとっては、キリストは神の力、神の知恵。
このように、ユダヤ人にとっても、ギリシア人にとっても、パウロが語る十字架のことば、すなわちキリストは「愚か」なものでした。しかし、パウロはこのように述べています。
しかしわたしたちは、十字架につけられたキリストを宣べ伝える。このキリストは、ユダヤ人にはつまずかせるもの、異邦人には愚かなものであるが、 召された者自身にとっては、ユダヤ人にもギリシヤ人にも、神の力、神の知恵たるキリストなのである。 神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強いからである。
コリント人への第一の手紙1章23-25節(口語訳聖書)
ここでパウロが訴えていること、それは視点を変えることであるように思われます。つまり、「力」も「知恵」も神のものであるということに目を向ける必要があるということです。
ユダヤ人は木にかけられた者、つまりのろわれた者がメシアであるはずがないと考えました。ユダヤ人はローマ帝国の圧政から解放してくれる救い主を待ち望んでいましたが、このキリストと呼ばれる人は十字架の上で死にました。ゆえに、彼らにとっては「のろわれた者」であり、のろわれた者が救い主だとはどうしても思えません。ですが、彼らには自分たちが期待するイメージを変える必要があったのではないでしょうか。すなわち、彼らは、十字架にかかってのろわれたイエスが自分たちの期待したイメージ通りではなかったということしか目がいかなかったということです。ですが、彼らが目を向けるべきだったものは、十字架による死からイエスを復活させた「神の力」だったのです。パウロはこの神の力が、罪人さえも救うことができると言います。キリストの十字架による死、そしてその死から復活させたそのことに、神の力が鮮やかに現されていました。
また、ギリシア人は十字架にかけられた人は恥の極みだと考えました。そこには、人間的に評価される名誉など、どこにもありません。そんな人がメシアであるなんて、人間の知恵では到底理解することはできませんでした。ですが、神の知恵とは、十字架によってキリストをメシア(救い主)とすることでした。とすると、誰もがこう思うでしょう。「なぜそんな方法で?」答えはいたってシンプルです。当時の社会の人々が「名誉と恥」という価値観から脱却する必要があったからです。だからこそ、神はそのような人間的な名誉をイエスに与えることはせずに、むしろそれによっては理解することのできない、新しい価値基準を驚くべき方法で示されたのです。
パウロはこのキリストを宣べ伝えています。つまり、ユダヤ人にとっても、ギリシア人にとっても愚かである「十字架のことば」を宣教しています。この「十字架のことば」は2000年の時代を超えて私たちの耳にも届いています。それでは、私たちにとって「十字架のことば」は愚かでしょうか。たしかに、2000年前と同じように、十字架で死んだ人を救い主と信じることは愚かだという人もいるかもしれません。ですが、パウロは言います。「召された者自身にとっては、ユダヤ人にもギリシヤ人にも、神の力、神の知恵たるキリストなのである」。パウロが「十字架のことば」として宣べ伝えていることは、まさに十字架によって鮮やかに示されたキリストの生き方だと言えます。それは、普通に考えたら、社会的な地位も名誉もありません。ですが、そのような価値観を超えた新しい価値観が、十字架によって示されたのです。それはまさに、イエスに倣って生きる生き方です。召された者は、キリストの生き方へと招かれています。聖書(福音書)には、イエスがどのように人に接し、人に仕え、また父なる神の御心を求めたのかという「生き方」が記されています。その中でイエスが示された価値観とは、人に仕えてもらうことよりも人に仕える生き方でありました(マルコ10:45)。
もちろん、このようなメッセージはいつの時代の人であっても、受け入れることは容易なことではありません。それほど、人生の価値基準を大きく変えるものだからです。今までの生き方をやめて、新しい生き方をしなさいと言われても、今日の明日でできることではないでしょう。そのことは確かにその通りなのですが、しかし、だからこそ、命をかけて、十字架で恥の極みをその身に受けながらも示されたことに、意味があるのではないでしょうか。
2000年の時を超えて、今も「十字架のことば」が語りかけられています。そして、そのことばは、大きなチャレンジを与えます。それはすなわち、この世の価値観の転換です。この世において、知恵あるもの、力あるものを誰もが求める中で、十字架のことばが示すことは、「神の愚かさは人よりも賢く、神の弱さは人よりも強い」ということです。そのことばを深く思い巡らせる受難週となりますように。