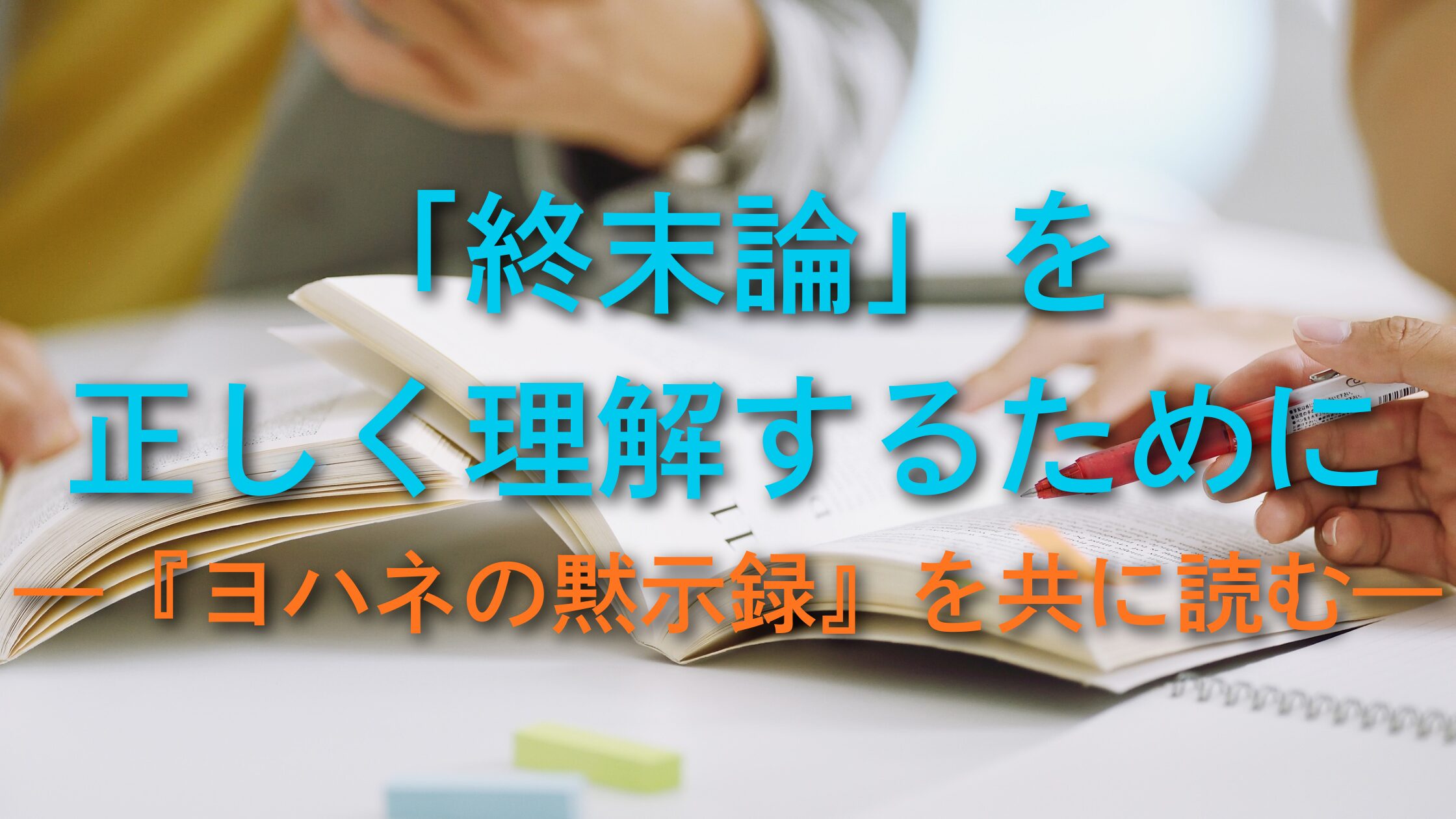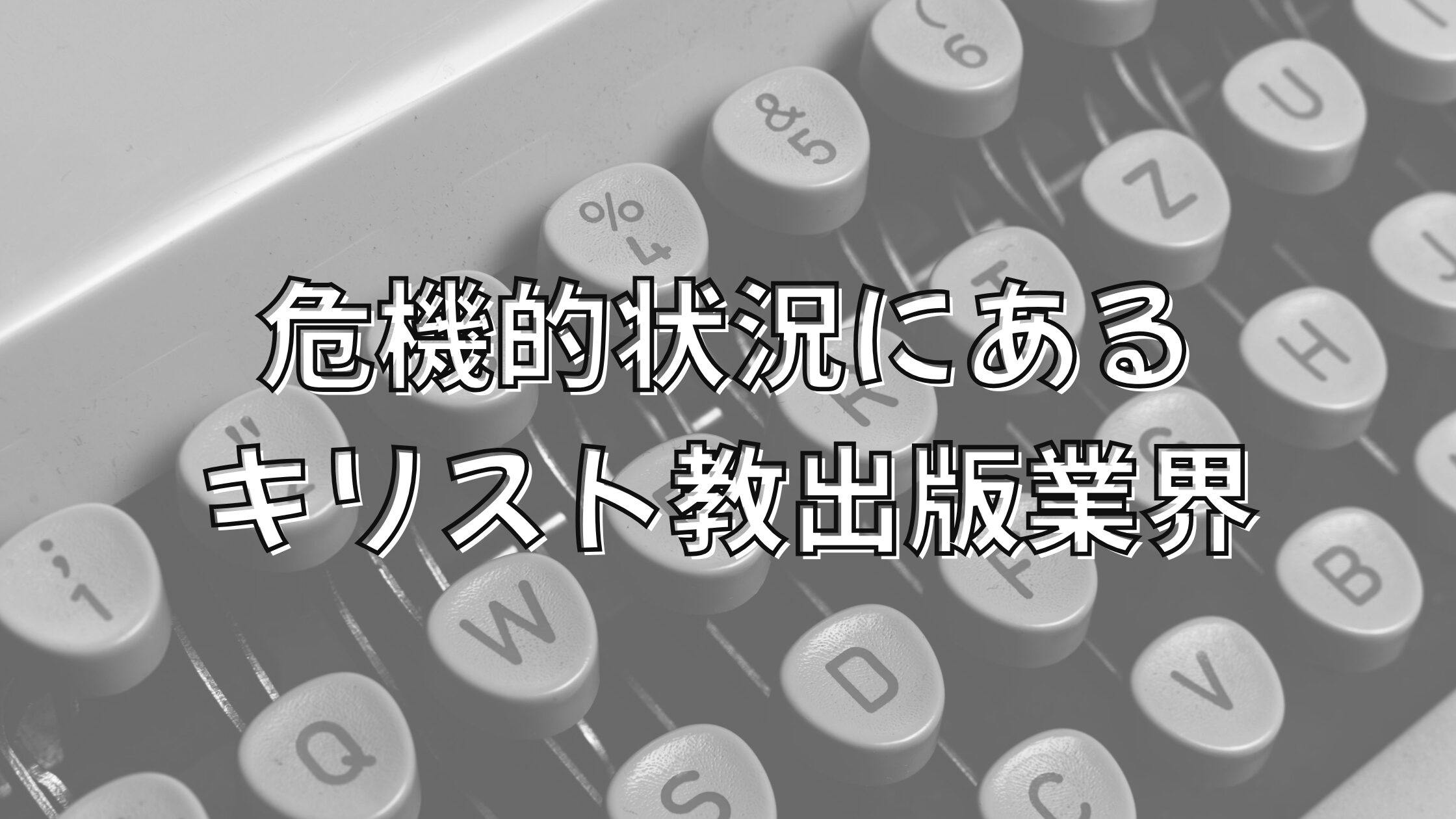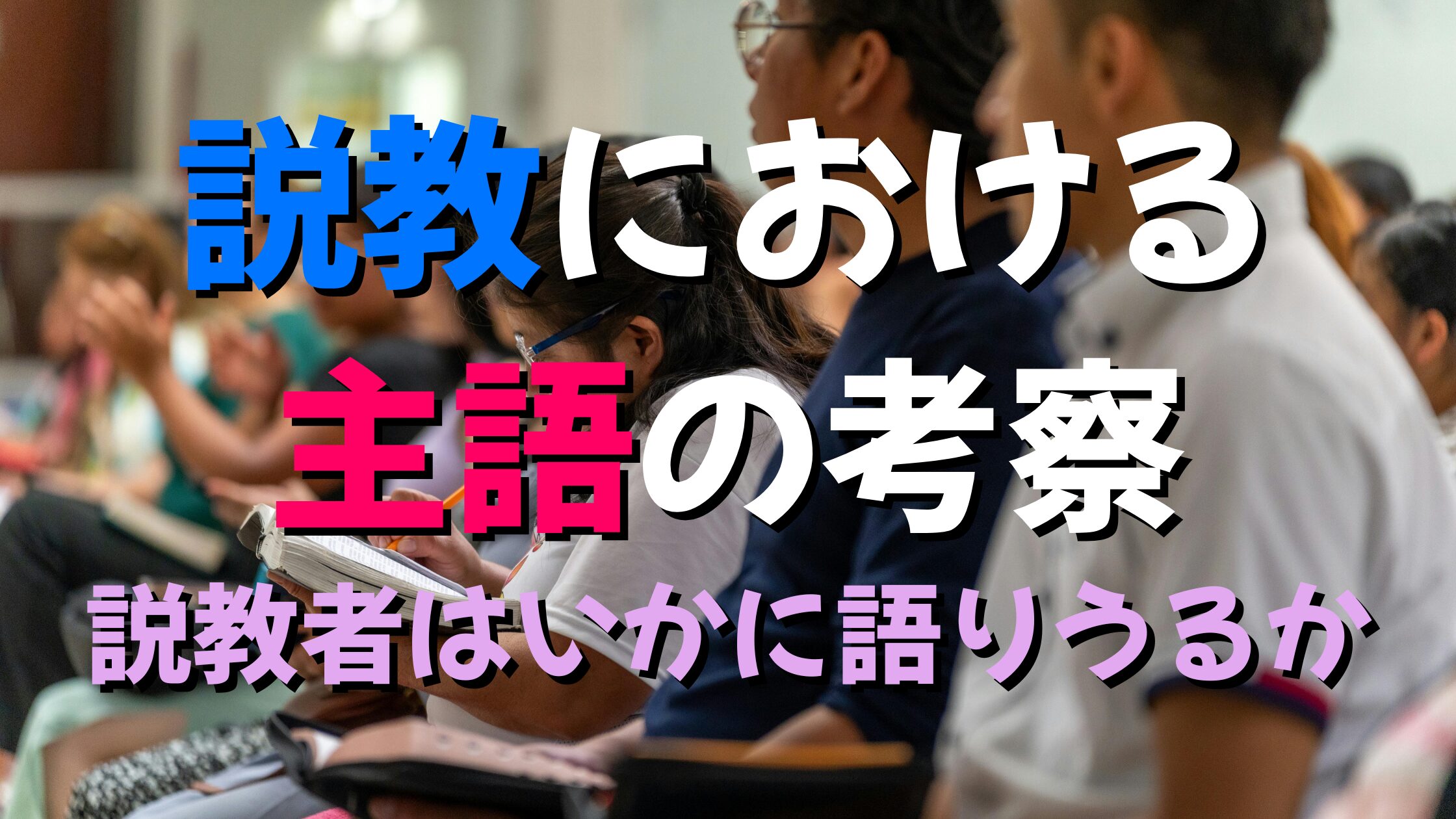今年の9月に、中公新書から、『福音派—終末論に引き裂かれるアメリカ』(加藤喜之 著)が出版されて、関心を集めています。
私もそこから教えられることが多くありました。Book Review:加藤喜之『福音派―終末論に引き裂かれるアメリカ社会』(中央公論新社、2025年)
アメリカでトランプ大統領が初当選した時から、日本でも「福音派」という言葉を聞くようになり、一般的にも浸透しつつあるように感じましたが、本書の出版により、アメリカにおける福音派の「実態」が明らかにされつつあります(と言ってよいのではなないでしょうか)。それは、すなわち、「終末論」との関係です。
そこから浮かび上がるイメージというのは、一言で言えば、「終末論に突き動かされた人たち」です。もちろん、本書をしっかり読めば、そのような安直な感想にはならないことは重々承知していますが、タイトルと副題のインパクトにより、「福音派=終末論」というイメージの定着は免れません。
しかし、終末論というのは、福音派の専売特許ではなく、キリスト教における重要な要素の一つであり、保守だけではなく、リベラルでも、神学の構成要素には終末論が必然的に含まれています。これは、キリスト教界では当たり前ですが、しかし、外から見たら、そこまで気にする人もおられないのではないでしょうか。とにかく、福音派は終末論と結びついていて、それゆえに時に過激な行動を起こすことがある、そこまでは思っていなかったとしても、そのような「イメージ」がもたれやすいという現状はあるのではないかと、思います。
しかし、そのように考えられることにも理由があると思っています。それは、終末論と深く関係している『ヨハネの黙示録』を正しく学ぶことができる環境が少ないからです。
昨今は、インターネットの普及により、誰でも、容易に情報にアクセスすることができる時代となりました。しかし、日本語で黙示録について学ぶことができる適切なソースはほとんどないように思われます。これはある人にとっては、暴論に聞こえるかもしれません。しかし、偏っているということは事実です。それも、そのようなものに限って、よく視聴されているという現状があります。多くの場合、人々の耳目を集めるために、極端な解釈がされているということに、注意深くある必要があると思います。
もちろん、だからと言って、完全に正しい解釈や説明というのは、容易ではありません。ですので、いろいろな文献や情報に当たることが望ましいわけですが、いかんせん、誰もがそのような時間を確保できるわけではなく、だからこそ、短くまとめられた動画や記事に目を通すわけですが、少なくとも、それが絶対ではないというクリティカルな姿勢は、大事にしたいと思います。
それでも、あえて、重要と思われる、あるいはこれをなくして黙示録を理解できないというおすすめの書籍を挙げるとすれば、それは、リチャード・ボウカム、飯郷友康・小河陽訳『ヨハネの黙示録—叢書新約聖書神学15』です。これは、数年前にオンデマンド版が出ていますので、在庫切れでも、注文できるのではないかと思われます。本書は少々アカデミックですので、難しくないとは言えないのですが、少なくとも、これを読めば、巷で話されるような終末論に傾くことはないと思います。
やはり、終末論が誤解されやすいところは、オカルト的な解釈がされることです。終末戦争やハルマゲドンなど、アニメやドラマの題材にもなっていて、誰もが「終末論」という言葉から連想されることでもあります。そのような終末的な危機感が、人々の感情を煽り、恐怖感を植え付けることになっています。
このような考え方は、もちろん、教会内でも散見されます。冒頭の『福音派』でも取り上げられているように、むしろ、そのような終末理解を前面に出している立場もあるわけです。そのような立場からは、この世で起きているいわゆる「悪」は、手のつけられないものとなっていて、むしろ、それらが終末の兆しであるとさえ理解されています。その場合、終末論、ひいては『ヨハネの黙示録』がどのように解釈されているのかと言えば、そこには「未来」に起こることが予言されていると考えられています。
ここが大きな違いを生み出す解釈の相違点です。『ヨハネの黙示録』を「未来」に起こる予言の書として読むのか、それとも別の読み方をするのか。このことが、あまり理解されないまま、そのインパクトだけが広まってしまった結果が、昨今のオカルト的な解釈、極端な終末理解であると言えます。これまで、この違いを明確に説明する本があまり日本語では読めなかったということ、また多くの日本のキリスト教会がアメリカ福音派の影響を受けてきたということが、その原因の一端ではないかと思います。
したがって、ここでご紹介するのは、黙示録を「未来」に起こるものとしてではなく、当時の人々に向けて書かれた手紙として理解するという立場です。そのことは、もちろん、ボウカムの立場でもありますが、より最近出版された本では、クニィ・ベルガー、三野孝一訳『開かれている門: ヨハネの黙示録のメッセージ』(教文館、2022年)でも踏襲されています。
本書の「訳者あとがき」にて、三野氏はこのように解説しています。
本書は黙示録という書物を、いわゆる、これから後に起こる歴史——未来——を「予言する」書物、すなわち、歴史の終わりまでに起こるさまざまな出来事を年代順に羅列したもの、また歴史的、地理的に時空を超えて、無時間的に語られたものとしてではなく、ある特定の状況の中に生きる教会のクリスチャンに向けて書かれたものとして読む。つまり、一世紀末の小アジア(現在のトルコ西部)においてギリシア・ローマ社会における苦難や誘惑の中にある諸教会に当てられた書簡(手紙)と定義している。それと共に、4-22章の特異な表象や表現で書かれた箇所をその時代(特にユダヤ教内部で)流布していた「黙示文学」と定義し、その文学様式の持つ特徴、趣旨を考慮した上で、そのメッセージに注目し、諸教会の信仰を正すために指示し、慰め、励まそうとしたものと理解する。訳者もこの読み方に賛同する。
クニィ・ベルガー、三野孝一訳『開かれている門: ヨハネの黙示録のメッセージ』(教文館、2022年)、265-266頁
本書は、アカデミックに裏付けられたメッセージ集です。中でも、本書における著者のお勧めは、『ヨハネの黙示録』を共に読むということです。
私たちがヨハネの教えに忠実に従おうとするならば、黙示録のメッセージを説教しただけでは十分ではない。それ以上のことをする必要がある。…これらの手紙は諸教会の指導者たちに宛てられたものであるが、興味深いことに1章3節の命令は、これらの手紙は教会全体で朗読されるべきものとしている。これらの手紙は、ヨハネがその時代に生きた諸教会と教会員に向けて書いたものであった。主がヨハネを通して諸教会とその指導者たちに多くの示唆と助言を与え、諸教会がそれを分かち合い、決断を促すことがその目的であった。まずは聞くこと、そして次にその情報と指示にどのように応えていくのかである。
クニィ・ベルガー、三野孝一訳『開かれている門: ヨハネの黙示録のメッセージ』(教文館、2022年)、257頁
実際、『ヨハネの黙示録』や終末論を学ぶことが、個人的になされているような現状があると思います。それは、時に、自分だけしか知らない神秘を知っているような錯覚を覚えさせます。しかし、それは『黙示録』が書かれた意図とは異なります。だからこそ、現代の教会においても、共に読み、話し合い、学ぶ姿勢が重要だと言えるでしょう。それは、極端な解釈に陥る危険性からも守ってくれます。
繰り返しになりますが、終末論はキリスト教においては重要な神学的課題の一つであり、福音派だけの特徴ではありません。しかし、福音派が陥りがちなのが、極端な誤った解釈です。それが、まさに今のアメリカで起きていることを引き起こす要因(あるいは遠因)になったことは紛れもない事実です。日本における福音派が、「アメリカ福音派」と全く同じであるとは思いません。同様に、アメリカにも、多様な福音派の方々がおられます。十把一絡げにするのは、横暴でしょう。とはいえ、日本でそのような福音派理解、終末論理解が浸透しつつある現状があります。だからこそ、改めて独善的な解釈になってしまわないように、注意深くある姿勢が重要であると思います。
このような終末論理解については、これからも折に触れて取り扱っていきたいと思います。
終末論と関係して、全体像を学びたい方は、こちらをお勧めします。