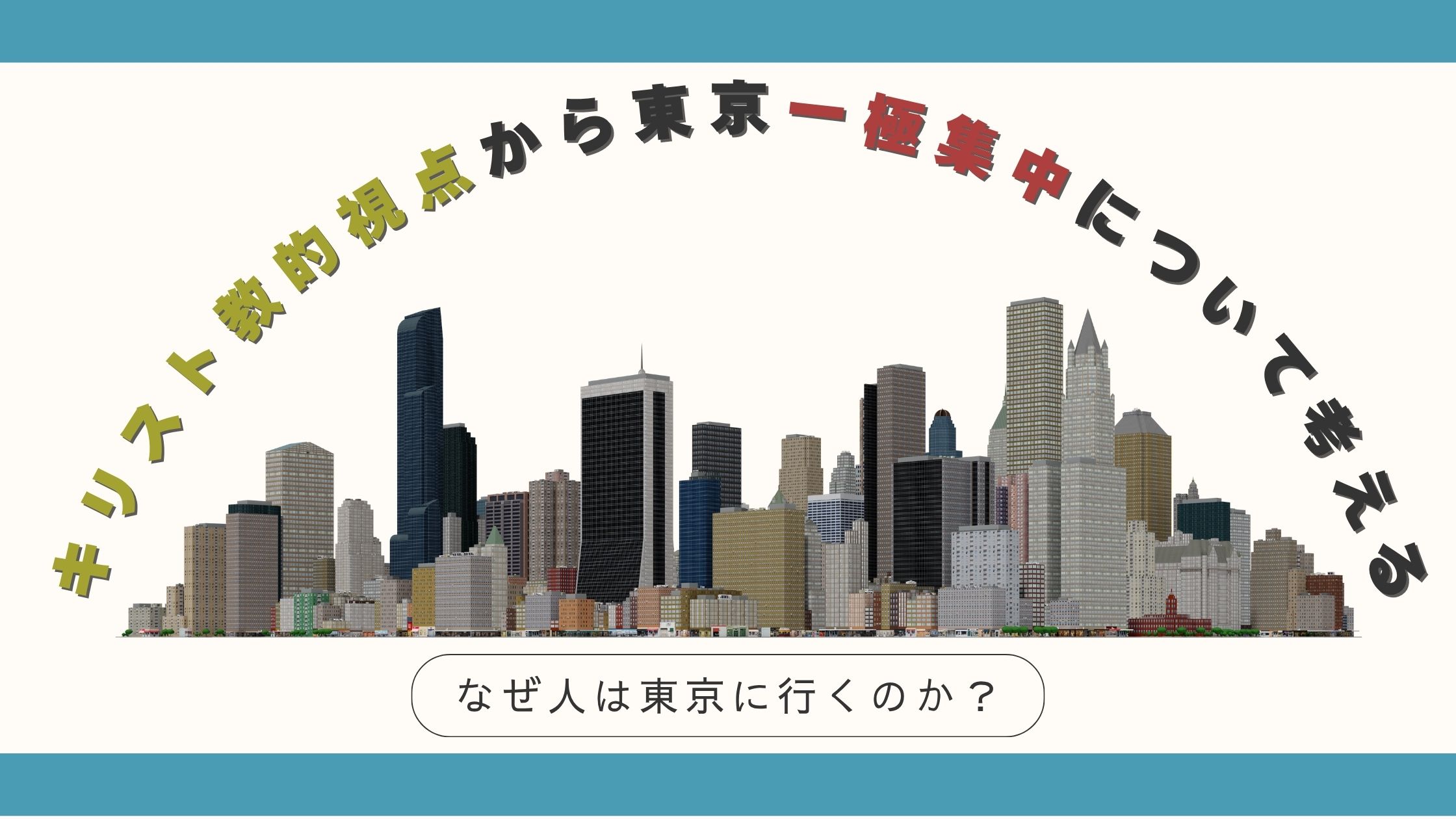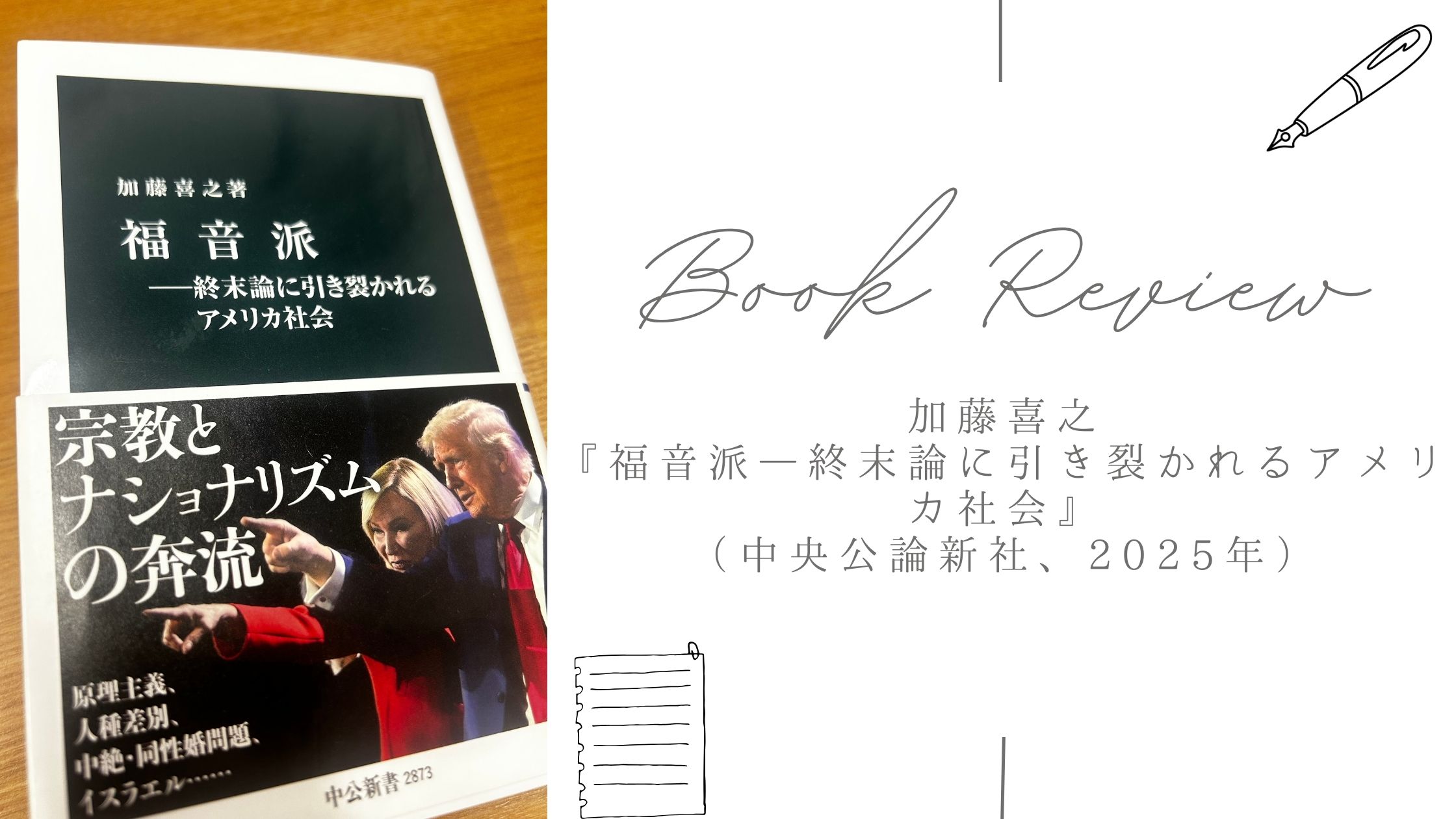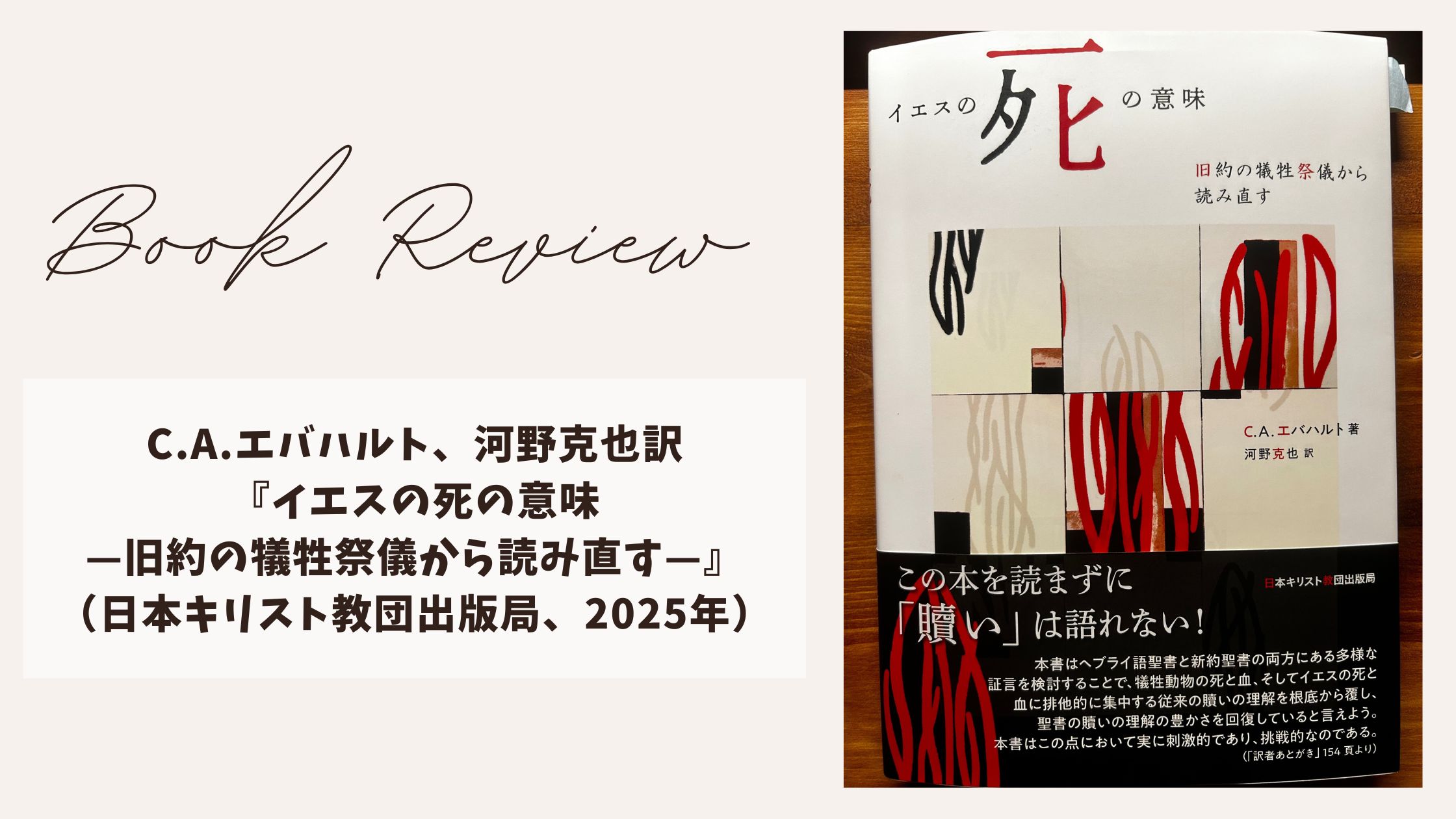増え続ける東京の人口
東京の一極集中はしばらくは続くと言われて久しいです。先日のニュースでも、転出よりも転入が超過していると報道されていました。人口増加の一方で、都市が機能不全に陥る危険性もあることは周知の事実でしょう。
とは言え、当然のことながら、実際、東京には魅力がありますので、東京で暮らすことは否定されるべきではありません。また、これまでも東京の基本的な方針は(これはどこでも同じだと思いますが)、人口を増やすということです。そのような大きな流れの中で、東京に人が集まるのはこれから先も続くことだと思われます。
そのような状況が続けば続くほど、都市部と地方にはギャップが生じ、ますます都市部が暮らしやすくなり、ますます地方では生活できないという状況になっていきます。この手のニュースは、連日見聞きしていますが、その問題是正のために、政治家たちをはじめ、あらゆる取り組みがなされているのだと思います。具体的には、地方の魅力を発信し、移住を勧めたり、などの実例も知っていますが、それだけでは限界があるということも浮き彫りになっているような気がします。実際、どれだけ地方の魅力を発信しても、古くからの風習、インフラ整備など、「田舎」ならではの問題が山積していることも一極集中が進む要因の一つとなっています。
そのような問題について、「キリスト教的な視点」から向き合うならどうなるでしょうか。今回は、その思考実験のような形で、考えてみたいと思います。
なぜ人は東京に向かうのか
まず、第一に東京一極集中は問題である、というところから始めたいと思います。一部に人が集まることで、日本全体の産業が停滞、衰退することは明らかです。また、人口集中により、様々な弊害が起こります。
では、なぜ多くの人は東京に行くのか。その理由は様々あると思いますが、その筆頭は、仕事があること、魅力があること、便利なことなどが挙げられるのではないでしょうか。
しかし、その一方で、人口集中により、地価や家賃の上昇が上がり続け、どれだけ仕事があったとしても、その生活が決して「楽」だとは言えない現実もあります。もちろん、それに見合った収入があればよいのですが、人が増えるということは、それだけ住む場所の取り合いになります。
それでは、地方の魅力を発信したら移住者は増えるのか。個人的には、ある程度(それも少ない)の移住者は見込めると思いますが、それには限界があると思います。なぜなら、東京に住む理由は、単に地方よりも魅力があるから、という単純なものではないと思うからです。おそらく、そこには極めて人間的な思いが潜んでいるように思います。
FOMO(Fear Of Missing Out):取り残されることへの恐れ
近年、耳にするようになった「FOMO」という言葉があります。Wikipediaによると、冒頭でこのように説明されています。
FOMO(英: Fear Of Missing Out、フォーモ、取り残されることへの恐れ)とは、「自分が居ない間に他人が有益な体験をしているかもしれない」、と言う不安に襲われることを指す言葉である。 また、「自分が知らない間に何か楽しいことがあったのではないか」、「大きなニュースを見逃しているのではないか」と気になって落ち着かない状態も指すことから、 「見逃しの恐怖」とも言う。社会的関係がもたらすこの不安は、「他人がやっている事と絶え間なくつながっていたい欲求」と言う点で特徴づけられる。
Wikipedia:”FOMO” https://ja.wikipedia.org/wiki/FOMOより引用
私は、多くの人が東京に行く理由、そこにはこのような「取り残されることへの恐れ」があると言えるのではないかと推察しています。みんなが東京で楽しいことをやっている、成功を掴んでいる。だから自分もその波に取り残されないようにしないと。そのようなある種の「恐怖心」が人を突き動かしているということはないでしょうか。
このような感情を抱くことは、誰にでもあることだと思いますけれども、しかし、このような感情に支配されてしまうことが、健全ではないと言えるのではないかと思います。
それでは、どうしたらそのような感情に呑み込まれずにいられるか、と言えば、やはりキリスト教的な視点を持つということではないかと思います。
相対的ではなく、絶対的
人と比べることは、時に害となりうることがあります。それは、結局、周りの人に振り回されてしまうことになるからです。人と比べて、いかに自分の「出来」がいいかによって、評価も変わってきます。しかし、そのような価値観というのは、極めて不安定であり、曖昧です。自分の価値はいつも「何か」によって左右されることになるからです。
しかし、キリスト教的な視点で言えば、そのような他者との比較はナンセンスです。特にこの点がよく表されているのは、使徒パウロの言葉でしょう。
12からだが一つであっても肢体は多くあり、また、からだのすべての肢体が多くあっても、からだは一つであるように、キリストの場合も同様である。
コリント人への手紙第一12章12-27節(口語訳聖書)
13なぜなら、わたしたちは皆、ユダヤ人もギリシヤ人も、奴隷も自由人も、一つの御霊によって、一つのからだとなるようにバプテスマを受け、そして皆一つの御霊を飲んだからである。
14実際、からだは一つの肢体だけではなく、多くのものからできている。
15もし足が、わたしは手ではないから、からだに属していないと言っても、それで、からだに属さないわけではない。
16また、もし耳が、わたしは目ではないから、からだに属していないと言っても、それで、からだに属さないわけではない。
17もしからだ全体が目だとすれば、どこで聞くのか。もし、からだ全体が耳だとすれば、どこでかぐのか。
18そこで神は御旨のままに、肢体をそれぞれ、からだに備えられたのである。
19もし、すべてのものが一つの肢体なら、どこにからだがあるのか。
20ところが実際、肢体は多くあるが、からだは一つなのである。
21目は手にむかって、「おまえはいらない」とは言えず、また頭は足にむかって、「おまえはいらない」とも言えない。
22そうではなく、むしろ、からだのうちで他よりも弱く見える肢体が、かえって必要なのであり、
23からだのうちで、他よりも見劣りがすると思えるところに、ものを着せていっそう見よくする。麗しくない部分はいっそう麗しくするが、
24麗しい部分はそうする必要がない。神は劣っている部分をいっそう見よくして、からだに調和をお与えになったのである。
25それは、からだの中に分裂がなく、それぞれの肢体が互にいたわり合うためなのである。
26もし一つの肢体が悩めば、ほかの肢体もみな共に悩み、一つの肢体が尊ばれると、ほかの肢体もみな共に喜ぶ。
27あなたがたはキリストのからだであり、ひとりびとりはその肢体である。
一人一人が「体」の器官であるというイメージは、決してここで初めて用いられたわけではありません。このイメージは、通常偉い人が立場の低い人を「手足」のようにこき使うイメージで用いられるものです。しかし、パウロが斬新的なのは、そのような上下関係を肯定する「体」のイメージを、すべての人が尊いという視点で用いている点です。体は、頭だけでも、目だけでも、手だけでも、足だけでも成り立たない。それら一つ一つが、体を動かす、人が生きるために用いられることに意味があるのだということを、パウロは言っているのです。
この箇所は、文脈を踏まえるならば、キリストの体、すなわち、「教会」に当てはめて解釈されるべきだという考えもあるでしょう。しかし、私はこの箇所は、まさにキリスト教的な価値観を示すものとして、あらゆる部分に適用できると考えています。個人主義が進んでいる現代社会にあって、「自分」の益が優先される時代です。しかし、そのような中で、共に一つの目標を目指して共同していくということが、非常に重要になってくると思います。その時に、遺憾なく発揮されるべき価値観が、ここにあると思います。
具体的な解決策
これらのことを踏まえた上で、それではどうしたら東京一極集中を改善できるのか。問題を提起するだけでは不十分ですので、具体的な解決策を提案したいと思います。もちろん、このようなことはすでに政治家たちによって議論されていることだと思いますので、私のような素人的な考えが箸にも棒にもかからないということは重々承知しています。
まず、そもそもなぜ東京に行きたくなるのかを十分に検討することが重要になってくるのではないかと考えます。もちろんそこには、積極的理由があることが多いと思いますが、中には、先に見たように「FOMO」と言えるような感情に動かされるといった消極的理由があるかもしれません。その場合、改めて動機を検討することも大切なことかもしれません。
また、現在は、誰もが競うように人よりも上に立ちたいという(隠れた)衝動に突き動かされている面があるのではないかと思います。しかし、そこで抜け落ちているのは、全体の視点です。もちろん、これは資本主義という社会全体の構造の中では仕方のないことなのかもしれません。新自由主義という言葉が広がって相当時間が経っていますけれども、競争が激しくなる中で、社会全体が成長していくということは全面的に否定されるものではないでしょう。しかし、その結果生じているのが格差の問題です。そこで、パウロの言うような「体」というイメージを持つなら、日本全体、ひいては世界全体が成長していくためにといった視点が生まれてくるのではないでしょうか。もっとも、ここでの「成長」というのは、単なる経済成長だけを指しているのではなく、あらゆる人が共に豊かな生涯を送ることができるような成熟した社会になっていくということです。
そのためには、例えば、人が集まり、豊かな資金を持っている都市部は、地方に還元していくということも具体的な実践として取り組むことができるのではないでしょうか。確かに、局地的に見るなら、それは損をすることになりますが、全体的に見るならば、それはメリットともなりうるように思います。結局は、地方が弱れば、都市部も弱るのですから、そのような連帯は決して無駄なことだとは言えません。実際、東京から地方へ移住する人には支援金を出しているとも聞いたことがありますが、そのような一部の人だけに関わるものではなく、東京全体から地方へ支援金を送る、みんなでサポートするという形を取ることはできないのでしょうか。実際に、そのように取り組んでいるという事例があるなら、詳しく知りたいと思います。このようにすることで、中には都市部に来ることを再検討する人も現れるかもしれませんが、それもまた人口集中を防ぐ一因になりうるかもしれません。
結局のところ、都市部への人口集中の問題は、あらゆるところに波及しています。そしてそれは、教会も決して例外ではありません。多くの学生は地方から都市部に行き、そこで就職する場合、当然、地方の教会ではなく、都市部の教会に通うことになります。そのことによって、都市部の教会は賑わう一方で、地方の教会は衰退していくということが、実際に起こっています。そのような現状がある中で、ある都市部の牧師から言われたことは、地方の教会への感謝を表すべきだということでした。都市部の教会が賑わうことの背景の一つには、地方から来た学生や移住者がいて、その方々の信仰を励まし、共に歩んできた地方教会を忘れてはならない。そのような趣旨の話を聞いたことがあります。さらには、どのような形であれ、都市部の教会が地方の教会をサポートできないかという意見もありました。
教会というのは、一つだけの教会が大きくなることを目的としているわけではありません。使徒信条において、「公同の教会」と告白されているように、教会は一つなのです。それは、キリストの体が一つであるのと同じです。教会の頭はキリストであるゆえに、私たちのこの地上における目に見える教会はたくさんあっても、一つなのです。だからこそ、互いに重荷を担い合いながら歩んでいくという姿勢が教会には欠かせません。
それと同じような視点を、国全体で、あるいは世界全体で共有することができたら、何かが変わってくるのではないかと、淡い期待を抱いています。