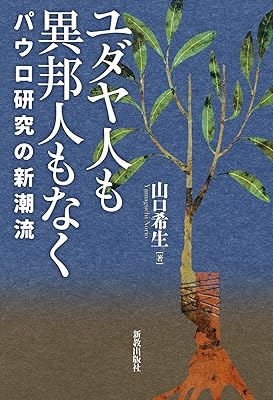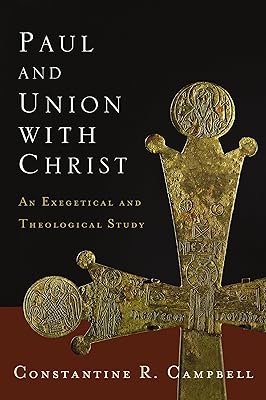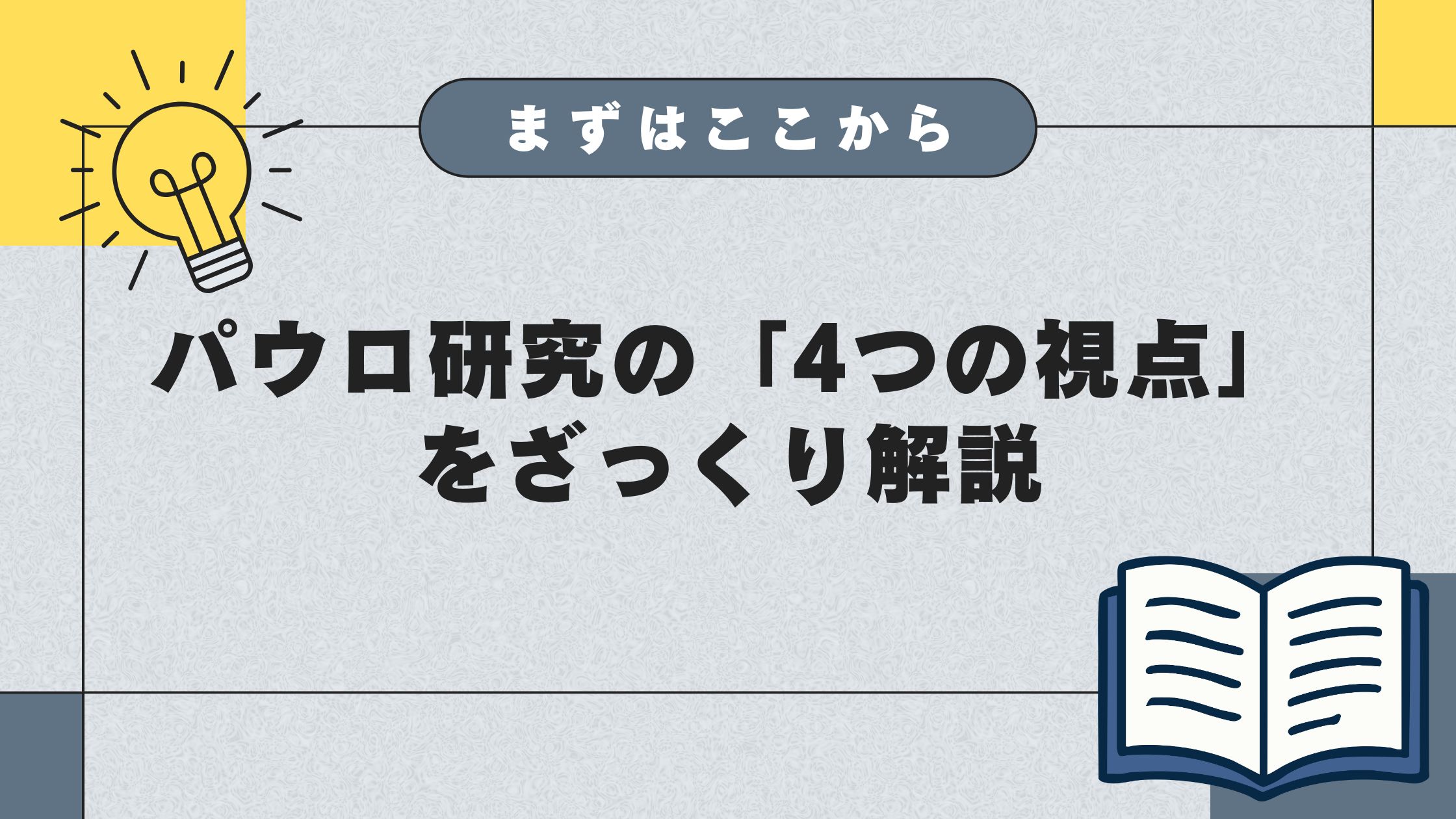今でこそ日本でも広く知られている「New Perspective(s) on Paul(パウロ神学の新しい視点)」(NPP)ですが、その発展の経緯を学ぶには、本書は必読と言えるでしょう。
1. 論文の質を左右する「研究史」
しばしば「論文はテーマ選びで50%が決まる」と言われたりしますが、残りの半分は、先行研究をどれだけ深く理解しているか、つまり「研究史」の整理にかかっていると言っても過言ではありません。NPPの研究史を、これほどまでに緻密に、かつ日本語で読める本は他にないと断言できます。
とはいえ、そんなことを言われても自分にはあまり関係ないと思われることもあるかもしれません。ですが、そのように敬遠するのは非常にもったいないです。なぜなら、著者の語り口は、学術的な内容に裏付けられながらも、同時に誰にでも理解できるようなものとなっているからです。
本書の重要な指摘の一つは、NPPの萌芽がすでに19世紀の神学者 F.C.バウルに認められるという点です(P.206)。そこからA.シュヴァイツァーやW.D.デイヴィスを経て、どのように議論が発展してきたのか。著者の優れた手腕により、後代の研究者がいかにして先人の知見を補完し、乗り越えていったのかが、まるでドラマのように興味深く描かれています。このことによって、単なる小難しい研究史としてよりも、興味深く、好奇心を掻き立てられながら読むことができました。
2. 「神聖視」されないパウロと、ユダヤ教の視点
本書の特徴の一つは、パウロを(良い意味で)神聖視しすぎない点にあります。 最終章では、パウロの主張に一方的に肩入れするのではなく、当時のユダヤ人キリスト者の立場にも真摯に配慮した結論が導き出されています。このバランス感覚こそ、現代のパウロ研究において極めて意義深いものだと感じました。
と言いますのも、現代のキリスト教界において、一般的にパウロは偉大な人物として、認識されているからです。もちろん、その認識は間違ってはいないのですが、あまりにもパウロを神聖視し過ぎると、それは聖書全体の教えというよりも、パウロの教えということにもなりかねません。その意味において、パウロはあくまでも聖書の執筆者の中の一人という位置付けを保つこと、特にパウロがユダヤ教を背景に持つことを踏まえることで、パウロ神学をより広い視点から見ることができます。
「パウロの言い分は、当時のユダヤ人から見てどう映ったのか?」 この「公平な視点」があるからこそ、私たちはパウロの言葉をより人間味のある、血の通ったものとして受け取ることができます。パウロが葛藤し、時には無理をしながらも必死に守ろうとしたものは何だったのか。その輪郭が、本書によって鮮明になります。
3. 「ポストNPP」の戦国時代へ
本書に関する素晴らしい書評はすでに多くの方々によってなされていますので、ぜひそれらを参照していただきたいと思いますが、ではなぜ今、この本を取り上げたのかと言いますと、それは、パウロ研究がすでに 「ポストNPP」 のフェーズに入っているからです。
現在、NPPに関する邦訳書籍は、極端にN.T.ライト氏の著作が多いように思われます。これは仕方のないことでもあります。NPPについて全く土壌がなかった環境で、まずは何から訳そうかと考えたら、NPPの主要提唱者の一人であるライト氏になるのは必然でしょう。それでも、ライト氏の貢献は計り知れませんが、それ一色に染まってしまうのは、パウロ神学という広大な森の一部しか見ていないことにもなりかねません。その先には、まだ邦訳されていない刺激的な地平が広がっています。
本書の第3部では、その旗手として ダグラス・キャンベル と ジョン・バークレー が挙げられています。「バークレーの研究は、NPPの議論をその先へと前進させた」と指摘するように(P.204-205)、バークレーの「恩寵(恵み)」理解は、パウロを研究する上で、今後の必須テーマとなるでしょう。
第3部冒頭で、ポストNPPの旗手として二人の名が挙げられていますが、著者はこのようにも述べています。
第3部では、NPPの考え方が学界に浸透していった後に、その洞察をさらに深めて前進させようと試みる気鋭の研究者たちを、ほんの一部ですが紹介します。ポストNPPの学者の名前は数多く上げることができますが、ここでは代表的な二名のみを取り上げます。
山口希生『ユダヤ人も異邦人もなく パウロ研究の新潮流』(新教出版社、2023年)、178頁
ここで著者が「ほんの一部」と述べている通り、ポストNPPの戦国時代には他にも多くの重要な研究者がいます。その中で私が個人的に注目しているのが、Constantine R. Campbell(C.R.キャンベル) 氏です(D.キャンベル氏とは別人です)。
4. 個人的に注目している神学者:Constantine R. Campbell
彼の代表作 『Paul and Union With Christ: An Exegetical and Theological Study』(Zondervan, 2012) をはじめとする著作に惹かれる理由は、彼が数多のパウロ理解を「調和」させようと試みている点にあります。ただ、「調和」というのは少し言い過ぎかもしれませんが、少なくとも、極端になりすぎる解釈に対して、微調整をしているように思われます。どのような研究であれ、次第に極端になっていくことは常です。
C.R.キャンベルの核心にあるのは、“Union with Christ”(キリストとの結合/合一) です。 N.T.ライトの物語論も、J.バークレーの恩寵論も、この「結合(合一)」という「参与論(Participation)」の視座、つまり、キリストの生き様に参与するという、キリストと信仰者の関係性から説明できるというのが彼の主張です。
もちろん、この「参与論」の主張はC.Campbellの専売特許ではなく、R.ヘイズやM.ゴーマンなどの巨匠たちがいます。C.Campbellもその系譜に連なるわけですが、なぜ個人的に推しているかと言うと、それは彼の研究スタイルです。特徴の一つは、ギリシア語の緻密な研究に裏付けられた神学です(最初の博士号はancient Greek language and linguisticsで、近年はギリシア語の文法書も出しています。”Basics of Verbal Aspect in Biblical Greek”)。また、かつてシカゴにあるトリニティ神学校で教えていましたが、今はオーストラリア神学大学で教えています。私はその経緯は知りませんけれども、いわば神学研究の中心地の一つでもあるアメリカからオーストラリアに移ったことに彼の個性を感じます。また、キャンベル氏はジャズサックス奏者でもあります。二つ目の博士号はジャズに関する研究であるとオーストラリア神学大学のサイトでは紹介されていました(2024年)。
いずれにしても、今後パウロ研究をする上で、C.キャンベル氏やヘイズ氏、ゴーマン氏らの提唱する参与論(Participation)は、NPPをさらに深く理解し、私たちの実存に結びつける上で、重要な鍵の一つになるのではないでしょうか。先ほど、ポストNPPは「戦国時代」と表現しましたけれども、さまざまな立場がある中で、この視点はそのような理解をまさに「結合(Union)」するものであるように思われます。
今回、ご紹介した本のタイトルにあるように、パウロが目指したのは「ユダヤ人も異邦人もない」世界です。ですが、それはどのように実現されるのでしょうか。人種も、立場も、考え方も違う人間が、どうやって一つになれるのか。 この問いを解決しうる糸口が、この参与論的解釈にあります。ライトの物語論も、バークレーの恩寵論も、すべてを一つに繋ぎ合わせるキーワード。それが、”Union with Christ”です。
5. 終わりに
本書は、まさに日本の読者にNPPを学ぶための現在最も重要な著作であることは間違いありません。それでも、研究は世界中で今もなお進み続けています。もちろん、そのような最先端の研究に、私たちは飛びつく必要はありませんけれども、少しでも世界の動向に関心を持っていることは決して無駄なことではないようにも思います。なぜなら、パウロ研究はクリスチャンの信仰生活にとっても、密接に関わるものだからです。
著者は「あとがき」にて、このように述べておられます。
私自身は、NPPを初めから抵抗なく受け入れることができました。その理由の一つは、クリスチャンホームで育つ中で「信じるだけで救われる」と教え込まれてきたものの、他方で聖書そのものを読むと、行いの必要性が強く訴えられているので、いったいどう考えればよいのか、と子供ながらに疑問を抱いてきたことがあります。NPPはこの長年の疑問に一つの道筋を与えてくれました。
山口希生『ユダヤ人も異邦人もなく パウロ研究の新潮流』(新教出版社、2023年)、222頁
ここに、私たちが、学者であってもなくても、研究する理由があります。クリスチャンとして歩む上で、疑問を持つことは当たり前であり、日常茶飯事です。それは、何も問題ではありません。ですが、その疑問がモヤモヤしたままで、教会を離れる、聖書を読むのをやめてしまうというのは、非常にもったいないことです。その疑問を糧に、神学の営みを続けていくこと。その中で、信仰というものは育まれていくのではないでしょうか。
まさに、著者にとってNPPの研究が大きな信仰の転換点となったのではないかと思うと、私たちもまた、日々の研究、学びをすることに大きな意味があるのだと思わされます。