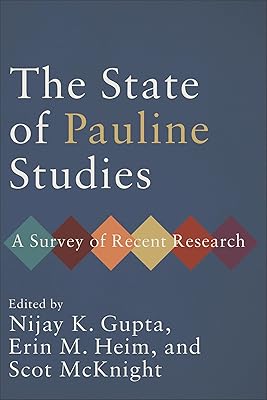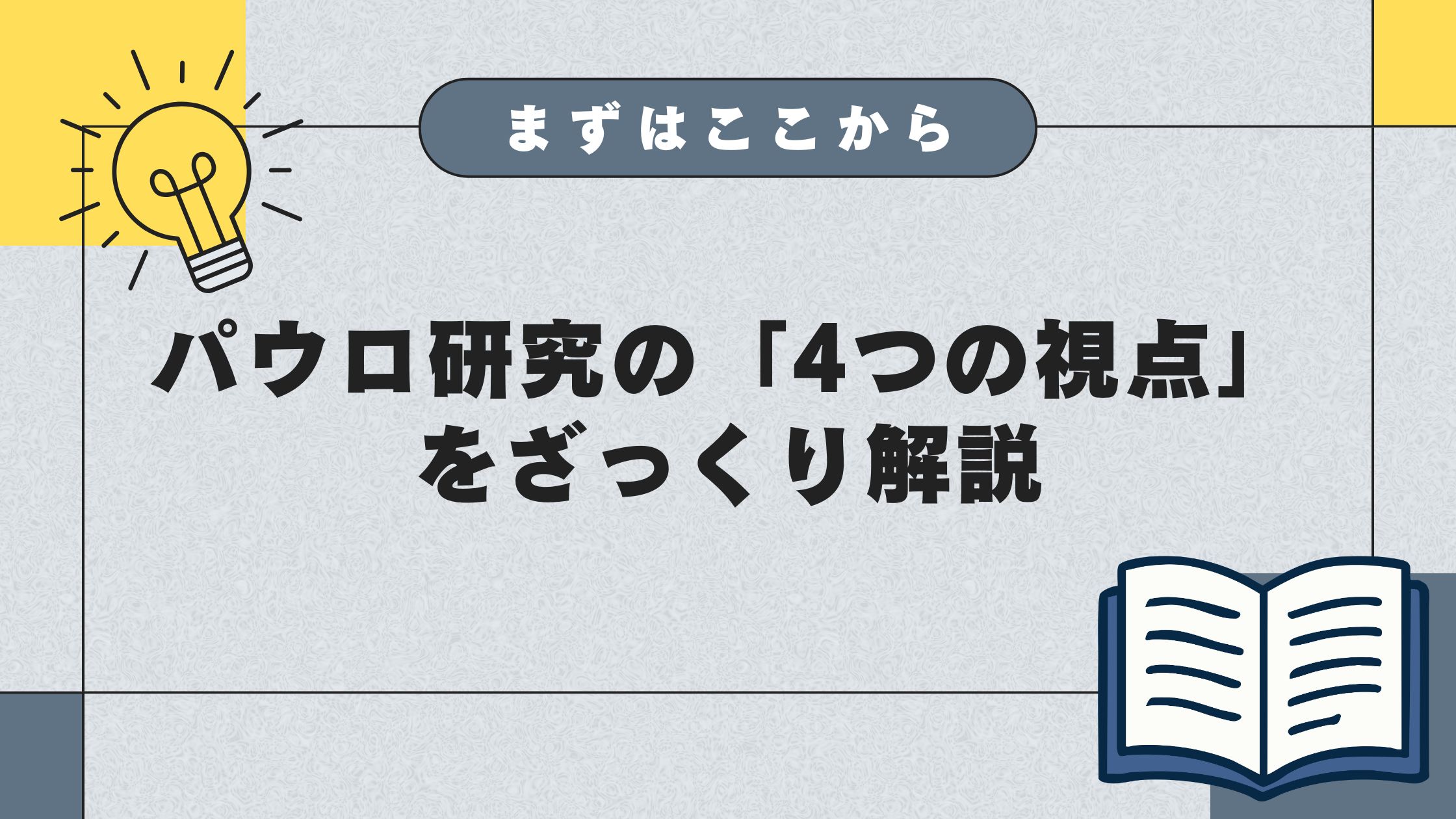日本では、ここ数年の間に、NPPの主要提唱者であるE.P.サンダース、J.D.G.ダン、そしてN.T.ライトらの著作が邦訳出版され、特にN.T.ライトに関しては続々と出版されている状況にあります。NPPを理解する上では欠かせないサンダースの著作『パウロとパレスチナ・ユダヤ教: 宗教様態の比較』(浅野淳博訳、教文館、2025年)の出版が1977年ですので、約50年の時を経て、日本でも翻訳されたことになります。
そうした状況で、日本でもNPPが一部の学者だけではなく、一般的にも浸透しつつあるように思われます。しかし、世界のパウロ研究はさらに進んでいて、もはやNPPというのが、パウロ研究の中でも数ある視点の中の一つとして見られているようです。
やっとNPPについて理解し始めたのに、もう新しい解釈が出ているの?!と思うと、ついていけないよ…というのが、自然な反応かもしれません。
そこで、今回は2024年に出版された『The State of Pauline Studies: A Survey of Recent Research』(Nijay K. Gupta, Erin M. Heim, Scot McKnight編)』を簡単にではありますが、ご紹介したいと思います。本書は、特定の自説を展開するものではなく、17人の学者による現在のパウロ研究が「どのような状態(State)」にあるのかを俯瞰した、地図のような一冊です。ですので、個別の神学者の著作を読むことはハードルが高いとしても、全体を学びたい方にはお勧めできる一冊です。
2025年末にもN.T.ライトの2005年の著作が邦訳出版されましたけれども、ここは一気に最新の動向を翻訳するのもありではないでしょうか。当面の間は、パウロ研究の標準ガイドとして保存版になりそうな気がします。
全体の構成
本書は二部構成になっています。
- 第1部:パウロ研究の主要トピック(メシア、ユダヤ教、救済論、聖霊、ジェンダー、帝国、ポストコロニアル的アプローチなど)
- 第2部:パウロ書簡ごとの研究動向(ローマ書からピレモン書まで、全13書簡)
主要なトレンドと特徴
本書が浮き彫りにしている、現在のパウロ研究の大きな特徴は以下の通りです。
手法と視点の多様化
かつてデフォルトだった「西洋的な歴史的批評(Western historical-critical approach)」は唯一の手段ではなくなり、現在は文学的、修辞学的、社会科学的、考古学的なアプローチなど、多様な「Tools」や「Methods」を使って研究されています。また、グローバルな視点やジェンダー、帝国(empire)/政治、過去の解釈史(受容研究:Reception study)への関心が高まっているのも特徴です。
パウロ書簡における著者性の再定義と正典的アプローチ
本書では、かつてのパウロ研究が「本人が書いた真正書簡(7通)」と「他人が書いた偽名書簡(6通)」を明確に切り分け、後者を研究対象から外したり、二次的なものとして扱ったりする傾向があったことが指摘されます。しかし近年、この「真正か、偽名か」という単純な二項対立(二つのカテゴリー)に対して、より繊細なニュアンスを持たせる動きが出てきています。本書が挙げている具体的なポイントは以下の通りです。
「著者(Authorship)」の定義の見直し
「パウロ本人が筆を執ったか、それとも偽パウロが書いたか」という白黒ハッキリした議論ではなく、古代における「著者」のあり方について、以下のような多様な可能性(グラデーション)が検討されています。
- パウロ学派(Pauline School): パウロの死後、彼の弟子たちが師の教えを継承・発展させて書いたものではないか。
- 編集者の存在: パウロが残したメモやノートを基に、死後に編集者が完成させたものではないか。
- 筆記者の役割: パウロは通常、筆記秘書(amanuensis)を使って手紙を書いていました。もし筆記者が文章作成に大きく関与していた(共同執筆に近い)としたら、手紙によって文体(スタイル)が違うのは当然であり、「文体が違うからパウロではない」という従来の判定基準自体が揺らぐことになります。
「本当のパウロ」は誰か?
上記のように筆記者が関わっている以上、私たちが分析している「パウロらしい文体」とされているものすら、実は筆記者の文体かもしれず、「本当のパウロの文体」などそもそも特定できないのではないか、という疑問も提示されています。
「正典としてのパウロ(Canonical Paul)」への回帰
こうした著者の特定に関する不確実性がある中で、多くの学者が「正典として受け継がれてきた13書簡すべて」を一つのまとまり(corpus)として研究することに意義を見出しています。 「誰が書いたか」という歴史的な人物の特定よりも、教会がパウロの教えとして受け入れた神学を全体像として読み解こうとする姿勢が見られます。
※補足:本書では、個々の手紙の真贋(authentic/pseudonymous)を分けるのではなく、書簡集全体を一つのまとまりとして扱う際に、この “corpus” という言葉が重要なキーワードとして登場します。
本書は、「著者の判定(誰が書いたか)」という歴史的な問いから、「テキストの機能(どう読むか)」や「古代の執筆慣習(筆記者の役割など)」への関心へと、研究の焦点がシフトしていることが説明されています。ただ、「エペソ書やテモテ書などはパウロの教えへの裏切りだ」として厳しく区別する学者も依然として存在しますが、以前ほど「真正か偽名か」の境界線は絶対的なものではなくなっている、というのが本書の示している現状だと言えます。
救済論における「5つの視点」
これが本書において傑出している部分ですが(第一部、第三章)、現在の救済論はかつてのような二項対立ではなく、以下の「5つの視点」に整理されています。
1. 改革派の視点 (Reformational Perspective)
「法廷での無罪判決」:罪人を義とする神の一方的な恵み
この視点は、ルターやカルヴァン以来の伝統的なプロテスタントの解釈を現代に継承するものです。 ここでの最大の問題は、人間が罪によって聖なる神から断絶され、その怒りと有罪判決の下にあるということです。人間は自らの行いによってこの状況を覆すことはできません。
そこで神が用意した解決策が「法廷的義認」です。これは裁き主である神が、被告人(罪人)に対して「無罪(義)」を宣言する法的な行為です。この判決は、人間が立派だからではなく、キリストが獲得した「義」が、信仰を通して信者に「転嫁(imputation)」される(つまり、キリストの正しさが信者のものとして扱われる)ことによって起こります。
この立場で特に強調されるのは、J.バークレーが言うところの「不釣り合い(Incongruity)」な恵みです。神は価値のない者、ふさわしくない者に、その価値とは無関係に一方的にギフト(恵み)を与えてくださるのです。
代表的な学者: S.ウェスターホルム、D.ムー、T.シュライナー
2. 新視点の視点 (New Perspective / NPP)
「契約共同体への回復」:ユダヤ人と異邦人が一つの神の民となる
1970年代以降に登場したこの視点は、パウロを「個人の救い」よりも「神の契約と民族」の文脈で読み解きます。 ここでの問題は、イスラエルがアダム以来の呪いの象徴である「捕囚」の状態にあることです。
解決策は「契約の回復」です。救いとは、アブラハム契約の成就として、神の民の家族の一員として回復されることを意味します。したがって、義認の定義も法廷での無罪判決というよりは、「誰が契約のメンバーであるかの確認・宣言」という意味合いが強くなります。特にパウロが強調したのは、異邦人が律法(割礼や食物規定などのユダヤ的な境界線)を守らなくても、信仰によってユダヤ人と同等のメンバーになれるという「民族的一致」でした。
代表的な学者: J.ダン、N.T.ライト、S.マクナイト
3. ユダヤ的視点 (Paul within Judaism / PwJ)
「ユダヤ教内部のパウロ」:異邦人のための特別なルート
近年急成長しているこの視点は、パウロを「キリスト教への改宗者」と見るのは間違いであり、彼は生涯「ユダヤ教徒」であったと考えます。 この立場では、ユダヤ人にはすでにトーラー(律法)と神殿という罪の解決手段が与えられていると考えます。したがって、パウロが論じる「義認」や「救い」は、主に「律法を持たない異邦人が、どうやって神の民に加えられるか」という異邦人特有の問題への対処だと理解します。
NPPと似ていますが決定的に違うのは、ユダヤ人と異邦人の境界線を消そうとしない点です。**「ユダヤ人はユダヤ人のまま(律法を守る)、異邦人は異邦人のまま(律法を守らなくてよい)」という区別を維持したまま、共に神の民となる道をパウロは説いたと主張します。
代表的な学者: M.ナノス、P.フレドリクセン、M.ティーセ
4. 黙示的視点 (Apocalyptic Perspective)
「宇宙的な解放戦争」:敵の支配からの神の劇的な救出
この視点は、救いを個人の罪の赦し以上に、宇宙的なスケールでのドラマとして描きます。 人間の問題は、単なる個人の過ち(sins)ではなく、「罪(Sin)」「死」「肉」といった宇宙的な悪の諸力に、奴隷として支配されている状態だと捉えます。
解決策は「解放(Liberation)」です。神はキリストを通して、敵(悪の諸力)が支配する領域に侵入し、捕虜となっている人間を解放します。これは神の単独行為による救出劇です。そのため、人間の応答(信仰)よりも、キリストが誠実に成し遂げた「キリストの信実(faithfulness of Christ)」こそが救いの根拠であると強調します。神が一方的に介入して世界を変える、劇的な「新しさ」に焦点を当てます。
代表的な学者: J.L.マーティン、D.キャンベル、B.ガヴェンタ
5. 参与的視点 (Participationist Perspective)
「命への参与」:キリストと結ばれて生かされること
この視点は、救いを「関係性」と「命」の回復として捉えます。 人間にとって最大の問題は、罪悪感や法的な罰よりも、「死(神の命からの分離)」にあると考えます。
解決策は「命への参与」です。キリストと結び合わされる(Union with Christ)ことによって、信仰者は神の命を共有し、死から命へと移されます。この視点では、「義とすること(義認)」を、単なる法的な宣言にとどめず、実質的に「生かすこと(making alive)」と密接に関連づけて再定義します。法的に正しいとされるだけでなく、キリストの命によって内側から変えられ、生かされていくプロセス全体を救いとして描くのが特徴です。
代表的な学者: M.ゴーマン、R.ヘイズ、B.ブラックウェル
パウロとユダヤ教の関係
かつての「置換神学(教会がイスラエルに取って代わった)」はほぼ退けられました。現在は、パウロがユダヤ教から「離れた」のか、ユダヤ教と「並んで」新しい共同体を作ったのか、あるいは完全にユダヤ教の「内部」に留まったのか、というグラデーションの中で議論が行われています。
メシアとしてのイエス
「キリスト」という言葉を単なる固有名詞ではなく、「メシア(油注がれた王)」という称号として読み直す動きが主流です。これにより、パウロの言葉はローマ帝国の政治的文脈(皇帝崇拝との対比など)において、より政治的・王権的な意味を持つものとして再評価されています。
パウロ研究の意義
パウロ研究の進展は、単純な分裂を乗り越える上でも、重要な意味を持っています。これまで、「行いか恵みか」という対立がありましたが、 「ユダヤ的視点(PwJ)」や「黙示的視点」の登場により、NPPですら「まだ十分にユダヤ的ではない(キリスト教的偏見が残っている)」と批判されたり、逆に「契約」の枠組み自体がパウロの急進性を損なうと批判されたりするようになり、単純な二項対立では説明がつかなくなりました。
また、プロテスタントとカトリックの間でも義認の解釈について、法廷的か変容かという対立がありましたが、「参与的視点(Participationist)」の台頭により、義認を「キリストとの結合(Union)」や「命への参与」として捉える新しい(実は古代教父的な)理解が広がりました。 これにより、「法的な宣言(プロテスタント)」でありつつ、「実質的な命の変容(カトリック)」でもあるという、両者の懸念を統合するような解釈が可能になったため、かつてのような硬直した対立は解消されつつあるようです。
まとめ
このように、パウロ研究は様々な解釈が提唱され、活発な議論が続けられています。しかし、本書の特徴は一つの「正解」を示すのではなく、改革派、新視点、ユダヤ的視点、黙示的視点、参与的視点などが、互いに批判し合い、また影響を与え合いながら、パウロのテキストからより深い意味を汲み出そうとしている現状が描かれているということです。
特に、本書の重要な貢献は、現在のパウロ研究の救済理解について、5つの視点がまとめられていることにあるように思われます。ですが、先述のように、本書は、パウロに関する白熱した議論やこれまでの二項対立を5つの視点へと多角化させることで、パウロ神学の豊かさをより立体的に捉えようとしていると言えるでしょう。
ますます研究が進んでいるパウロ神学を学ぶ上で、ここはあえて最先端の研究に触れてみるのはいかがでしょうか。