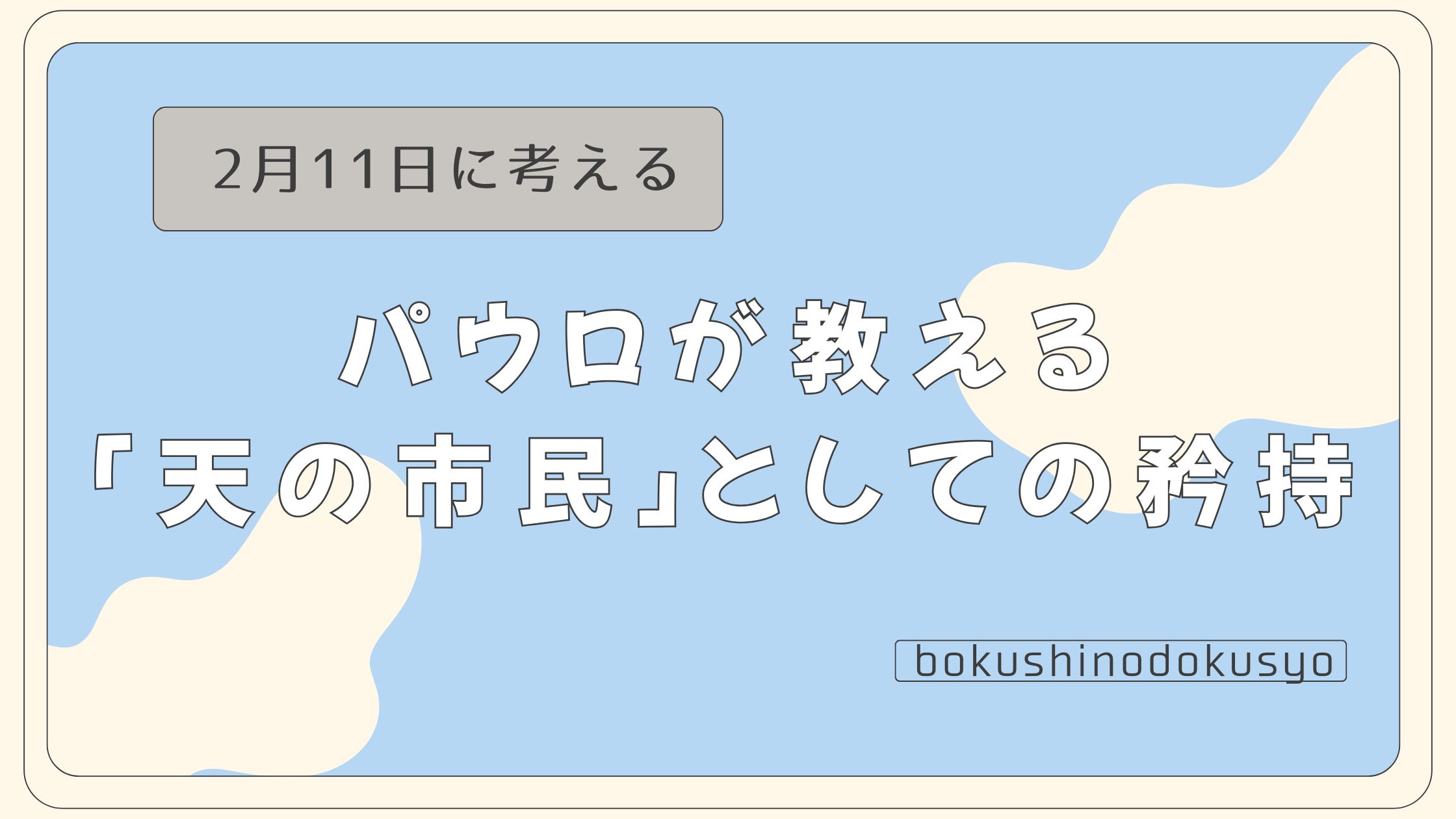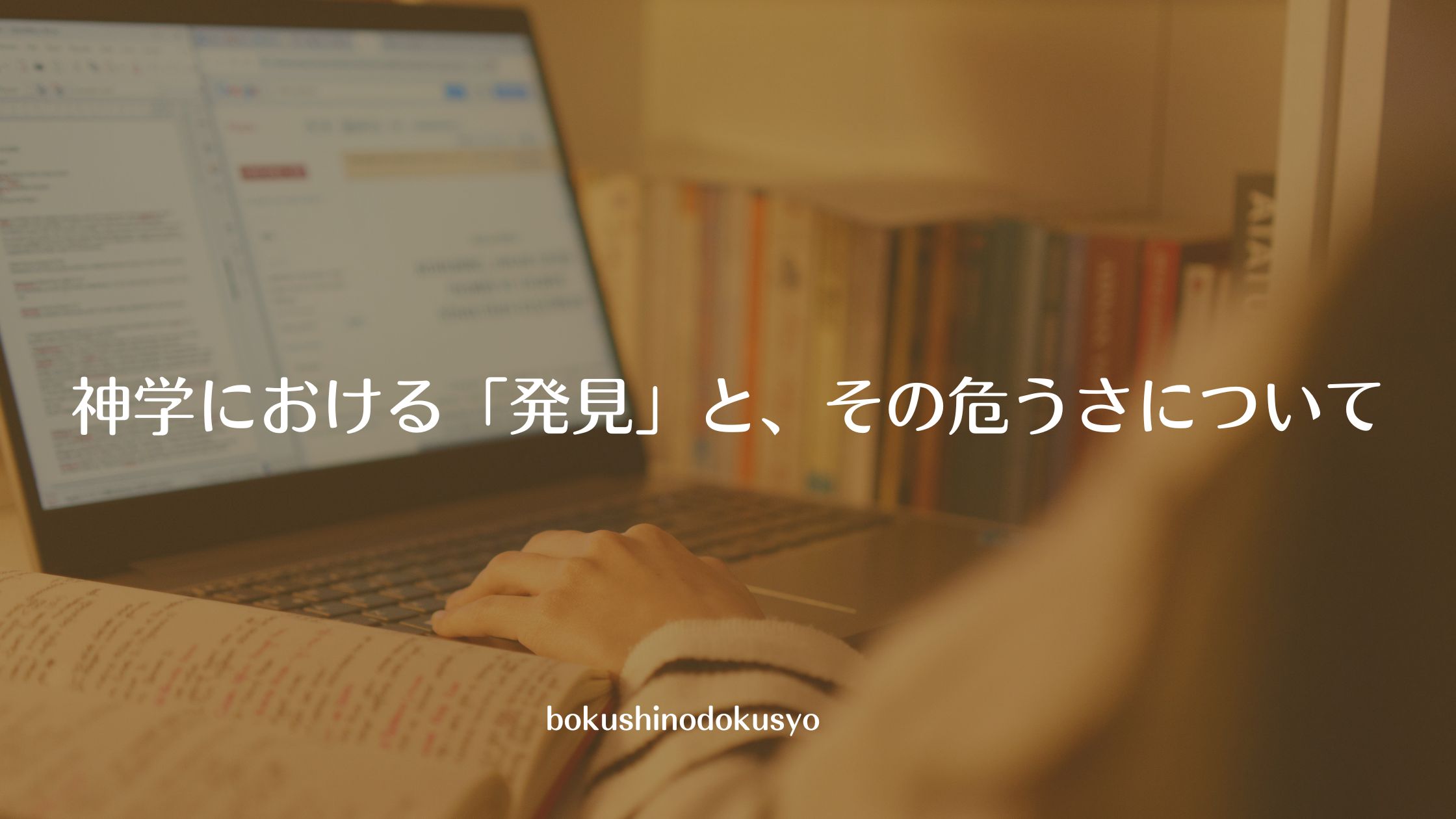「死海文書の発見が、パウロ理解を根底から変えた。」
近年のパウロ研究の専門書を読めば、必ずと言っていいほど目にするフレーズです。しかし、初めてこの言葉に触れたとき、私はある種の「突き放された感覚」を覚えました。
それは、「確認しようがない」という事実です。
死海文書に何が書かれているのか。そのヘブル語やアラム語の断片を、自分の目で読み解き、検証できる人が世界に何人いるでしょうか。多くの信徒にとって、最先端の神学とは「少数の専門家が、私たちが触れることのできない密室で導き出した結論」に過ぎません。そこには、ルターが掲げた「万民祭司(万民神学者)」の理想とは程遠い、巨大なギャップが存在しています。
1. 権威への「盲信」か、「信頼」か
私たちは今、神学者の言葉を「ブラックボックス」として受け入れるしかないのでしょうか。 研究者が提示するエビデンス(証拠)にアクセスできないまま、その結論だけを鵜呑みにすることは、キリスト教がかつて戦ってきた「権限の独占」へと逆戻りすることに他なりません。
しかし、ここで立ち止まって考えたいのは、神学を学ぶ目的は「研究者と同じ知識を持つこと」ではない、ということです。 神学を学ぶ真の目的は、専門家の結論をただ暗記することではなく、彼ら(彼女ら)が掘り起こした事実によって「私たちの手元にある聖書が、どれほど豊かに、立体的に立ち上がってくるか」を、自分自身で検証することにあります。
2. 「地図」としての神学、その手触り
確かに、私たちは死海文書を直接読むことはできません。「読む」ことはできたとしても、それを高い精度で読み解くことは、難しいでしょう。しかし、学者たちの知見を借りて聖書を読み直したとき、今まで平面的だったパウロの言葉が、当時の「生きた人間」の苦闘として鮮やかに色づき始める瞬間があります。
その時、神学は「遠い国のニュース」ではなく、私たちの人生を歩むための「精度の高い地図」へと変わります。 地図が正しいかどうかは、それを持って実際に歩き、目の前の景色と照らし合わせることでしか確認できません。その「歩く」という作業、つまり日々の生活の中で神の言葉を生きるプロセスにおいて、私たちは誰もが等しく、自分自身の人生における「最高の神学者」となるのです。
3. 「翻訳者」の誠実さについて
伝える立場にある者がすべきことは、専門知識を権威として振りかざすことではありません。 「なぜその発見が重要なのか」「それが私たちの現代の悩みとどう繋がるのか」を、アクセス可能な言葉へと翻訳し、ブラックボックスの中身をできる限り透明にしていくことです。
アカデミックと一般の断絶を埋めるのは、単なる「わかりやすさ」ではありません。 「私にもわからないことはある。けれど、この発見によって、これほどまでに神様の愛の奥行きが見えてきた」という、知的な誠実さと、発見の喜びの共有です。
私たちが聖書を学び、神学を齧るのは、賢くなるためではありません。 誰かに預けっぱなしにしていた自分の信仰を、自分の手に、自分の言葉に取り戻すため。その「自由」への戦いこそが、神学という営みの本質なのです。
4. 【個人的な回想】書き換えられた「地図」を歩く:私の転換点
正直に告白すれば、私が初めて「パウロ研究の新しい視点(NPP)」という言葉に触れたとき、最初に抱いた感情は「知的好奇心」ではなく、一種の「反発」に近いものだったように思います。
死海文書に何が書かれているのか。その断片を自分の目で読み解き、検証できる術を、私は持っていませんでした。専門家が「証拠がある」と言えば、それを信じるしかない。その心境は、確認しようにも確認できない、どこか心もとない感覚でした。
しかし、その「ブラックボックス」への違和感を抱えたまま、私はある一つの変化を自分の中に発見することになります。
1. 「救い」の定義が広がった瞬間
それまでの私の「信仰の地図」において、救いとは、極めて個人的な「私の罪がどう赦されるか」という一点に集中していました。しかし、NPPが提示する「神の契約への誠実さ」や「共同体のアイデンティティ」という視点を通して聖書を読み直したとき、今まで見落としていたパウロの言葉が、驚くほど鮮明に立ち上がってきたのです。
それは、単なる「個人の魂の救済」を超えて、「この歪んだ世界の中で、どのように神の民として共に生きるか」という、極めてダイナミックで公的な希望の物語でした。
2. 「イエスは主である」という言葉の重み
特に私の地図を根底から書き換えたのは、「主(キュリオス)」という言葉の政治的・社会的な響きを再発見したことでした。 当時の人々が、「イエスは主である」と告白することが、どれだけ大きな意味を持っていたのか。それまで知らなかった世界が一気に開けたのです。死海文書を直接読めずとも、当時の時代背景という「レンズ」を借りることで、「イエスは主である」という告白が、当時のローマ帝国においてどれほど危険で、かつ誇り高い「忠誠の誓い」であったかが理解できました。
それは、現代の日本という「目に見えない同調圧力」が支配する社会において、私がどこに軸足を置いて生きるべきかを指し示す、確かな羅針盤のようなものとなったと言えるかもしれません。専門家の結論を鵜呑みにしたのではなく、その知見を借りて歩き出したとき、「私の目の前の景色」が確かに変わった。それが、私にできる「検証」でした。
5. ギャップの間に架ける橋
学問の世界から切り出されたばかりの知見は、そのままでは無機質で、少し扱いにくいものかもしれません。けれど、そこに一つの光を当てることで、私たちの手元にある聖書が、再び「生きた言葉」として動き出すように感じています。
私がこのブログで、時に難解な学説を紹介し、時に自らの泥臭い回想録を綴っているのは、その二つを繋げたいと願っているからです。専門的な知見という「硬い石」を、今日を生きるための「温かなパン」のように分かち合うこと。その間にある溝に橋を架け続けることが、牧師として、そして一人の「神学する者」としての私の役割なのだと考えています。
たとえ死海文書の文字を直接読み解くことはできなくても、その言葉の奥にある「神の真実」は、私たちの日常という現場で、今日も確かに経験できるものだと信じています。
関連するおすすめの本