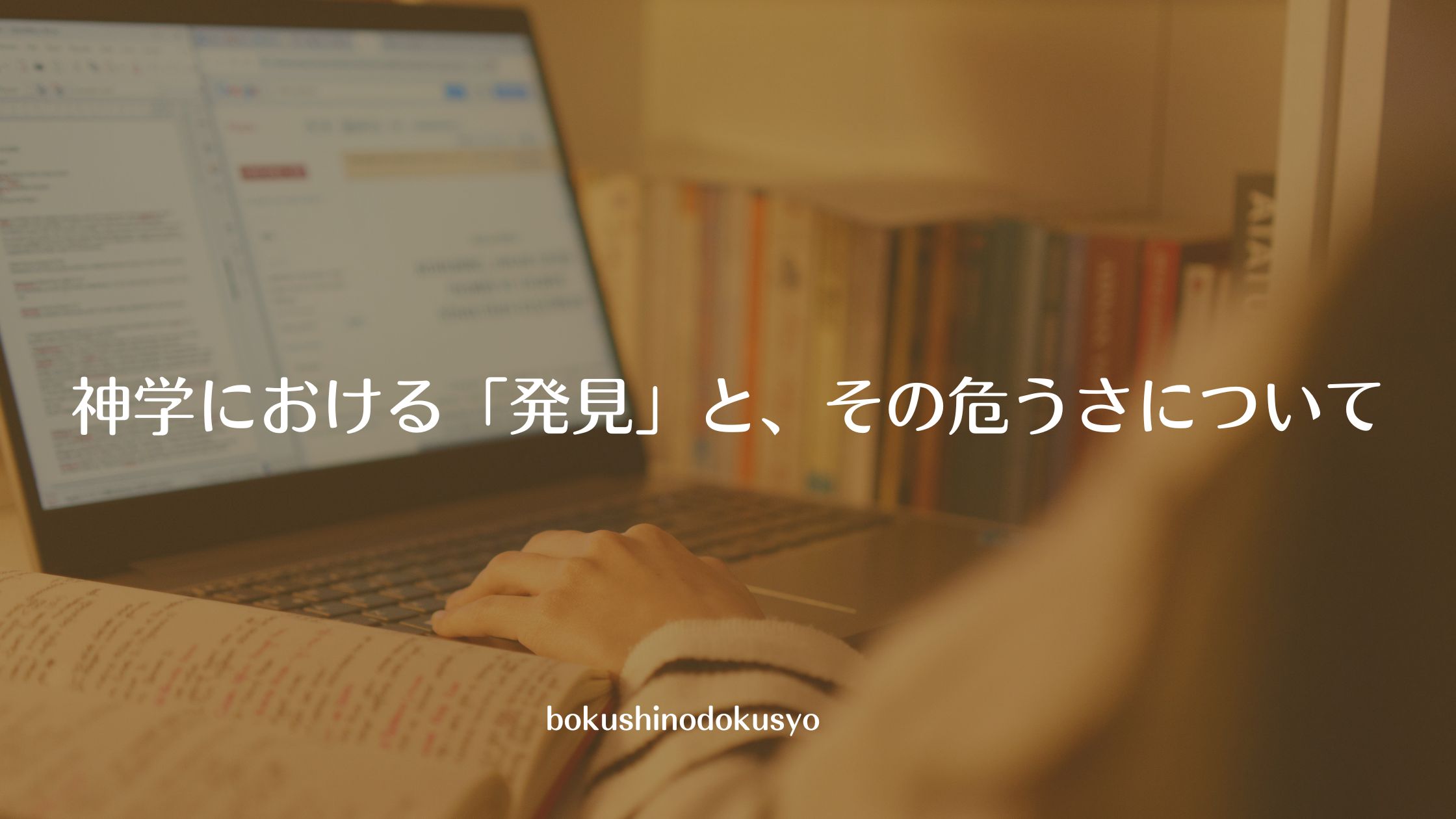ようやく扉が動き出したと思った矢先のことだった。私の前に立ちはだかったのは、目に見える障害物ではなく、あまりに真っ当で、あまりに冷徹な「正論」という名の壁だった。
食堂の喧騒と、静かな刃
お昼時の食堂。食欲をそそる食事の匂いと、誰かが運ぶコーヒーの香り。多くの学生や職員で賑わうその空間で、私は一人の教授と向き合っていた。
「日本にいても、できることはたくさんあるんじゃないのかね?」
教授の眼鏡の奥の瞳が、静かに私を見つめていた。その声は決して荒らげられたものではなかったが、だからこそ、石のように私の胸の底へ沈んでいった。
「今の時代、英語の文献ならいくらでも手に入る。神学を学ぶなら、まずはここで腰を据えて取り組むべきではないか。何より、日本の食事は世界で一番美味しい。それなのに、休学してまで、今、海外に行く必要があるのかい?」
それまで大切に温めてきた思いが、その鋭い刃の前で、無力なガラクタのように思えてきた。用意してきたはずの「広い世界を見たい」「生きた信仰に触れたい」という言葉は、急に幼いわがままのように響き始め、喉の奥につかえたまま、声にならなくなってしまう。
(確かに、その通りだ。先生の言うことは、100%正しい。)
周りのテーブルからは、他の学生たちの楽しそうな笑い声が聞こえてくる。しかし、私たちのテーブルだけは、まるで時間の流れが止まったかのように重く、冷ややかだった。
言葉にならない「飢え」
実際、他の先生のところに休学の相談に行けば、十中八九は「反対」か「無関心」だった。もっともな意見だ。ぐうの音も出ない。
けれど、私の心の奥底には「数週間や数ヶ月の『体験』では意味がないんだ」という、言葉にならない飢えのようなものがあった。単なる「見学」で終わりたくなかったのだ。その土地の日常に身を浸し、言葉の通じない孤独の中に身を置き、そこからしか見えない景色を掴み取りたい。根拠はない。しかし、今の自分にはそれが必要だという、破壊衝動にも似た切実な渇望が、胸の内で渦巻いていた。
思えば、高校を卒業してそのまま神学校に進む道を選んだ時も、同じような正論の嵐の中にいた。「社会を知らなすぎる」「もっと広い世界を見てからでも遅くない」。家族をはじめ、手放しで応援してくれる大人は周りにはいなかった。知り合いの牧師たちも、一様に心配そうな、あるいは懐疑的な視線を私に向けていた。
しかし、今振り返れば、その理由が痛いほどわかる。牧師という歩みは、生半可な情熱だけで務まるほど甘いものではない。あの時の私に、その重荷を一生背負い続ける覚悟が備わっていたかどうか。周りの大人たちは、私の「本気」を、そしてその言葉の奥にある「忍耐」を試していたのかもしれないと、今更ながらに思う。
結局、私は周囲の懸念を背負いながら、神学校という門をくぐった。その選択が本当に正しかったのかどうか、その答えが出るのはまだずっと先のことだろう。しかし、あの時の「反対」が、皮肉にも私の内側にある決意を研ぎ澄ませてくれたことも、また事実だった。
暗闇に灯った一言
「……ちゃんと、戻ってくるのか?」
沈黙を破ったのは、普段は誰よりも気難しく、厳格に思われていたあの先生の声だった。うなだれていた私を見かねてのことだったのかもしれない。手放しで応援してくれる者などいないと思っていた暗闇の中で、その一言は、私にとって唯一の「光」のように差し込んだ。
「休学した学生が戻ってくるケースは少ない。だから、必ず帰ってくると約束すること。」
この時、先生がそれを「条件」と言ったかどうかは忘れてしまった。しかし、この言葉が、私にとっての「絶対的な条件」となったことは確かだ。そして、これ以上の条件なんて、必要なかった。いつの間にか食べ終えていた先生は、そのまま颯爽と席を立って行ってしまった。
一人残された私は、冷めかけたご飯を口に運びながら、目の前の自動ドアが、再び、ゆっくりと、しかし確かに動き始めたのを感じていた。
(続く)